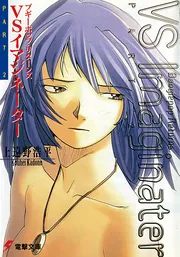イントロダクション Introduction
障子を開けて、薄暗い茶室の畳の上に、少年は一歩目を踏み出した。
「…………」
彼は声もなく、その座布団や座卓が乱雑に散らばっている室内の中心を見つめていた。
室内は、欄間からかすかに射し込んでくる光だけで、すべてはおぼろにしか見えない。だが、それで充分だった。
部屋の真ん中で少女が一人死んでいる。
逆さまになって、白い厚手の木綿ソックスをはいた細い脚を宙に「万歳」の両手のようにあげていた。床に肩が接していて、首が胴体と同じ向きにまで曲がっていた。血は一滴も流れていない。
長くて流れるように綺麗な黒髪が畳の上に広がり、その目は虚ろに少年を見つめ返している。
「…………」
少年は一歩、後ろに下がった。
その瞬間、彼の鼻先を何か熱いものが上から下にかすめていった。
彼はぎくりとして、その方向──天井を見た。
絶句した。
「見たな」
天井に張り付いていた殺戮者が言った。それは少女のような姿をしているが、男でも女でもない生き物だった。
「見られたからには、生かしてはおかぬ」
生き物は笑うように、歌うように言った。
次の瞬間、少年の身体は飛びかかってきたそいつに弾き飛ばされた。
(……ああ!)
なぜか、少年はそのとき奇妙な快感を感じていた。
●
……起こったこと自体は、きっと簡単な物語なのだろう。傍目にはひどく混乱して、筋道がないように見えても、実際は実に単純な、よくある話にすぎないのだろう。
でも、私たち一人ひとりの立場からその全貌が見えることはない。物語の登場人物は、自分の役割の外側を知ることはできないのだ。
私の名前は
県立深陽学園の二年生だ。よく中学生や、時折は小学生にさえ間違えられることもあるようなチビだけど、学校じゃいちおう風紀委員長なんかをやっている。
「敬ってさあ、なんというか、姉御って感じよね。見た目ガキっぽいけど頼りになるわあ」
とか、友達はからかい半分で言う。
私自身はあんまり自分を真面目な人間とは思っていないのだけれども、周りはなんだかそうは見ていないみたいだ。よく相談事を受けたり、困ったときに頼られたりする。
そして私には、ちょっとした〝病気〟があって、頼まれると嫌とは言えないのだ。
「なんとかならない、敬?」
「新刻、なんとかなんねーの?」
……そう言われると、どうにも気持ちが落ち着かなくなるのだ。
しかしそれと風紀委員長という仕事は、実のところあんまり関係がない。
うちの学校は、県でも中ぐらいの、進学校だかなんだか、という程度のレベルだが、ほとんどの高校のご多分に漏れず、生活指導は教師の仕事で、風紀委員はただの飾りだ。先生達だって、たとえば今年に入ってから家出して行方知れずになっている子がもう何人かいるけど、よくあることなので慌てたり一生懸命探したりとかしない。担任の先生が、自分たちの失点になるので頭を痛めているくらいだ。
私自身は、そういう投げやりな風潮に、やっぱりすこし腹を立てているけれども、でもそんなちっぽけな正義感なんて、実際には何の役にも立ちはしない。
どうせ私たちには、本当に大変な事態が起きたなら、どうすることもできないのだから。
そう、私は何にも知らなかったのだ。
私や、私のごく親しい人たち──彼や彼女たちが、何に苦しみ、何と戦っているつもりだったのか、まったく知らなかったり、見当はずれの思いこみしかできていなかったのだ。
天から降りてきた男と、彼を模して造られた少女──あの二人をめぐる奇妙に歪でいくつもの事態が互いにすれ違うこの事件は、たぶんあのへんから始まっていたのだと思う。
そう、それは私が失恋したあたりのことになる──