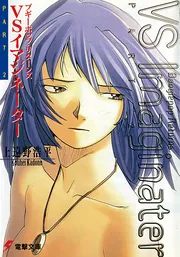第一話 浪漫の騎士 Romantic Warrior 2 ①
翌日、僕はいつもより早く学校に行った。
僕の通っている深陽学園には、他の高校にはちょっとないモノがある。生徒はIDカードを持たされ、登下校の際に校門にある駅の改札みたいなチェックゲートに記録を入れなくてはならないのである。高度情報管理学園システムってやつだ。子供が少なくなったので、システムの充実によって生徒数を確保しようとしたためらしい。
でも実際に通う僕らからすれば、ほとんどどうでもいい話だ。だいたい、そんなご大層なものがあっても、今年に入ってから何人かの生徒が家出してどこかに行ってしまった。自慢のシステムも、学園外でなんかする生徒の自由意志まではどうすることもできないってわけだ。
校舎は山の中にあるので、僕らは毎日緑の多い坂道をてくてくと歩く。まだ人はそんなにいない。部活の朝練の連中はとっくに来ていて、一般生徒はこれからって時間なのだ。
「ハーイ!
てれてれ歩いていると、後ろから明るい女の声が掛けられた。
振り向くと、同じクラスの
彼女は人を呼ぶとき、ふざけてあやしい横文字っぽい発音をする。いつも陽気な女だ。
「ヘイヘイ、爽やかな朝なのに顔が暗いわよォ」
追いついてくると、彼女は僕の背中を、どーん、とどやしつけてきた。
僕も紙木城も、お互い校則違反の男女交際をしている。だからと言うか、同類、という気安さがある。おたがいに同性の友人には言えないような共感があるのだ。いつもくだらないことを言ってふざけあっている。しかし今朝は僕の状態がよくない。
「なんだよ、おまえにしちゃずいぶん早いじゃんか。いつもの重役出勤はどうしたんだよ」
僕はぶっきらぼうに言った。紙木城は遅刻の常習犯だ。低血圧だと本人は言っている。教師に叱られると大げさに「ごめんなさあい」とかしなつくったりして、男の教師だとそれでまごついてしまってウヤムヤにされてしまう、というワザを持っている。
「まあねぇ。ふふ、ちょっと野暮用がねぇ。それより昨日はどうだったの、カノジョとデートだったんでしょ?」
「……いいだろ別に」
「なーに、喧嘩でもしたの?」
彼女は興味津々という顔で僕の顔を覗き込んできた。どうも彼女は感情表現がストレートすぎるところがある。けっこう美人なのに、無防備にニカニカ笑ったりする。それで人に変に誤解されることも多い。根はいいヤツなんだが。
「喧嘩かあ、喧嘩でもできりゃいいんだけど」
僕はため息をついた。
「おー、なになに? やけに深刻じゃん」
「まあな」
そのとき他の生徒がうしろから自転車で走ってきたので僕らは口を閉じた。
校門前では、風紀委員の当番が生徒たちを効率よくチェックゲートに入れるため整理をしている。ほとんど駅員だ。
「あら、竹田先輩。早いんですね」
僕を見つけて、今朝の当番の新刻敬が声を掛けてきた。彼女は風紀委員長でもある。そのモノモノしい役職名に似合わず、童顔で背の低い、かわいい娘である。
「ああ、ご苦労さん」
僕は軽く手をあげた。僕と彼女は、去年も保健委員で一緒だったので二年越しの顔なじみだ。
「おはよ、
紙木城も彼女とは知り合いだ。遅刻を何度か見逃してもらってるうちに仲良くなったそうである。
「なんです? 二人そろって。仲いいんですねぇ」
「あなたに言われると怖いわね」
紙木城はにやにやと笑った。
「いえ、別にそういう意味じゃないですよ。大体そうだとしても、黙認してあげますから」
「恩を売る気ね。高そうだわァ」
「そうですよ」
委員長も笑った。
しかし、彼女も紙木城が二年と一年の男子を二股かけてると知ったら、とてもこんな返事はできないだろう。根が真面目だから、頭から湯気たてて怒るに違いない。
僕らはカードをゲートに差し込んで、校門をくぐった。
「先輩、今日はミーティングがありますからね!」
委員長の声に、僕は振り返らず手だけあげた。
紙木城がくすくすと笑った。
「かわいいわねえ」
「誰が?」
「敬よ。あの
「……おめでたいな、おまえは」
自分はほとんど修羅場の恋愛を何度もしてるくせに、よくそんな冗談を言えるよ。
「それで? どうしたって?
「デートをすっぽかされた」
「あらら。そりゃ胸が痛いわぁ、あはは」
自分もやったことがあるらしい。
「あのさ、女の子ってそういうの、相手のことどう思ってやるんだ?」
「一言じゃ言えないわね。うーん、ケースバイケースよ。別に会うのが
「でさ──その間、男の格好するってのは、どうなんだ?」
「はあ? なにそれ。どーゆー意味?」
紙木城は目を丸くした。
無理もない。僕もいまだに何が何だかわからない。
「いや、いいんだ。うん。きっと目の錯覚だ」
「よくわかんないけどさア、せっかく啓司、あなたはヒマなんだから、まじめに恋をしなさいよォ、うん」
紙木城は歌うように言った。
「なんだそりゃ」
僕が顔をしかめると、彼女はほんとに歌いだした。
「〝生命みじかし、恋せよ乙女
あかき唇あせぬまに
あつき血潮のひえぬまに
明日の月日はないものを〟……」
「妙に浮かれてんな。また好きな男でもできたか」
「まあねぇ、ふふん」
「何人目だよ、好きにしろよもう」
校舎に入る直前で、僕らは自然に離れてよそよそしい素振りになった。つきあってるわけでもないのに、男子と女子のツーショットだと色々気を使う。
僕はその足で、藤花のクラスに向かった。
行ったって声を掛けられるわけでもないし、何のために行くのかよくわからないが、行かずにはいられない。
藤花のクラスである二年C組には、まだ誰もいなかった。
僕は、なんとなく力が抜けて、がらんとした教室の席のひとつに腰をおろした。
そして、あの黒帽子の言った言葉を、ぼんやりと思い返した。
〝君たちは、泣いている人を見ても何とも思わないのかね〟
「…………」
あれは、ほんとうに藤花だったのだろうか?
彼女の双子の兄貴とか──そんな話は聞いたこともないが。
人の気配がしたので、僕はあわてて席から立って、教室から出た。
少し離れた渡り廊下に何気なく立って、こっそりと見張り続ける。そうしていると、なんだか自分がすごくみじめに思えてきた。
(あーあ、なさけねー……)
藤花は、だいたいクラスの二十番目ぐらいにやってきた。
いつもの彼女と変わらない。別にヘンな帽子とかはかぶっていない。
だがなにやらスポルディングのでかいバッグをいつもの通学カバンとは別に持っている。体操着かスニーカーでも入れているのだろうか。
そして、彼女は僕に気がついた。
ん? とあどけない顔で僕を見つめてきた。
僕は何となく笑って、うなずいた。
彼女も少しだけ微笑んで、うなずいた。
ぜんぜん、いつもと変わらない。
約束を破ったことなど、まるでお構いなしって感じだった。
目立つと何なので、校内では僕らは話もロクにしない。でもなんつうか、サイン、みたいなものがある。
で、僕はそのサインのひとつである〝人差し指をたてる〟というのをやった。これは、放課後に校庭の裏で、という合図だ。
彼女も同じことをやる。OKということだ。
まるで、いつもどおりである。
煙に巻かれたような気持ちで、僕は自分の教室に戻った。
紙木城はまだ教室に来ていなかった。どっかで〝野暮用〟とやらにかまけているのだろう。お互いに忙しいことである。
風紀委員会のミーティングは昼休みにあった。