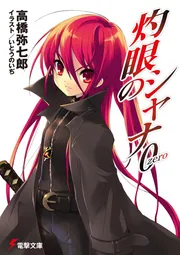4 信奉者
彼ら[
ただ奉じる『師』、その一要素だけで彼らは間接的に繋がり、また誰もが己を『一番弟子』と自認していた。ゆえに彼らは、自分たちのことを上下のない『同門』と呼び合う。
誰もが『一番』を自認するため、総じて傲慢で、同門にも非協力的で、なにより己を特別視していた。そんな彼らは、自分たちを一纏めに呼ばれることにすら不快感を覚え、『師』の教えを歪んで受け止める他の愚か者どもと一緒にされては敵わない、と考えていた。
彼らにとって組織とは、力を合わせる必要が生じた際――多くは『師』の聖遺物の探索や奪取――に招集される手段の呼称に過ぎず、誰もが、そこいらの有象無象(同門含む)と同列では有り得ない、と思っていた。
それでも今回、この地に世界中から全ての同門が集った(集う前に死んだ間抜けもいたようだが)のは、目的の偉大さゆえである……と、『大計画』の首謀者にして主導者たる〝
この偉大なる目的を前にすれば、他のどの同門も、絶対に文句は言えない。
どんなに無茶な命令であろうと、彼ら自身の在り様として受け入れるしかない。
世界に散らばっていた同門を一人残さず、この作戦のために動員することもできる。
膨大な自在式の断片を刻む作業に従事させることも、身命すら消費させることもできる。
それを指揮する己こそ、まさに『師』に最も近き『一番弟子』と言えよう。
そして今まさに、指揮する者から成就した者へと変わる、待ちに待った時が来る。
(土壇場になって、どこぞの腕っ節の強い邪魔者に侵入されたが……それも、まんまと囮の方に引っかかってくれた)
ククッ、とケレブスの忍び笑いが、伴添町外れに位置する無線基地局の暗がりに漏れた。
そこは携帯電話や無線を中継する施設である。局、施設といっても、アンテナを備えた巨大な鉄塔と、その下に付随するコンクリ箱状の電源設備、というだけの簡素な建物。電子技術に少々覚えがあれば電波ジャックするのは容易かった。特に、彼ら[
(地震さえ起こせば、囮は用済み……そして、邪魔者どもの右往左往する間に)
基地局から町中へ無数、発信された彼の自在法『ストマキオン』は、同じく町中に無数、刻まれた自在式の断片を、意味成す形に構成してゆく。本来は、一定の法則に従い自在式を組み合わせるだけの力、せいぜいが自在法の効率化程度にしか使えない力、だった。
(真の『一番弟子』たる私が、偉業を成す)
その力は今、断片の核として機能を発揮している。不定形だった力のたゆたいを、重々しいうねりへと、圧倒的な怒濤へと、方向性を与え導いてゆく。人は誰も知覚できない、自在法による力の怒濤は、徐々に全体の高度を上げる、巨大な環を形成していた。
「さあ、今こそ偉大なる……この私と『師』のためだけの、栄光の儀式の始まりだ!!」
環になった力の怒濤は、どこまでも加速してゆく。そうして、自在法を光の帯と錯覚するほどの極みで、唐突に実体化した。ケレブスの炎と同じ、老竹色の火の粉を撒き散らして、環は町を囲む外輪山の頂部をなぞるほどの威容を、曇天の夜空に低く浮かべる。
その様に陶然と浸っていた彼を、劈くような爆音が揺るがした。
「なっ、なんだ!?」
基地局の狭い窓から外を窺って、驚愕する。もう存在など欠片も気に留めていなかった、出し抜いたはずの邪魔者らが、まっしぐらに彼の許へと飛来していた。
「な、なぜここが分かった。いや、いや、いやいや、そんなことはどうでもいい!! 私の栄光は、すぐそこに迫っているのだ! 絶対に、邪魔はさせんぞおおお!!」
作業着姿の貧相な男が、人化の自在法を解いた。
本性を現し、膨れあがりながら絶叫する。
「我が『師』――〝
基地局を内から砕いて現れる巨大な三つ頭の烏に、ではなく、その叫んだ内容――なにより最悪の〝紅世の王〟の名――に、シャナは灼眼を一杯に見開き、悠二は顔を強張らせた。二人は思わず飛翔の軌道を捻って頭上、盆地を睥睨するように浮かぶ環を見上げる。
悠二は『オベリスク』による分析より早く、既視感を声にしていた。
「これは……『神門』の模造品だ!!」
『神門』とは、旧世界と〝
「なんという、ことだ」
驚愕に声を揺らすアラストール、
「――ッ!!」
息を吞むシャナも、その後背に現した『
主な構成要素は二つあった。
一つは〝徒〟であれば誰もが使う初歩的な自在法、現在では新世界と〝
町全体を覆い尽くすほどにばら撒いた、これら二つの構成要素を、ケレブスは自在法『ストマキオン』によって結合し、無理矢理な、数の力で、強引に、稼働させているのだった。
両界の狭間への門をこじ開け、狭間の彼方へと誘導の信号を送るために。
彼ら[
悠二は大いに焦った。
「じょ、冗談じゃない!! ようやっと大流入の戦乱も収まって、手探りの協議も始まろうかっていう大事な時期なのに!」
シャナも、心底から焦っていた。
「もし、もしあれが生きていて、ここにやって来たら!!」
アラストールまでもが、本気で焦っていた。
「この新世界――『
恐らくは、信奉者たる[
底なしの探究心と天井知らずの好奇心、天才という以外に形容不可能な頭脳と
教授――〝
新世界の創造へと到る激戦の中、自身の超兵器によって両界の狭間へと消えた彼が、もし生き長らえて、無限の〝存在の力〟で満ちた新世界『
そんな彼を迎え入れるための環が、囲いの内をゆっくりと、暗夜の雲よりなお暗く翳らせてゆく。かつての『神門』がそうであったように、狭間への口を開けつつあるのだった。
シャナは逸る気持ちを抑えて、叫ぶ。
「悠二、まずは!」
「分かってる!」
悠二も最低限に答え、基地局の鉄塔を押し倒して翼を広げた巨大な三つ頭の烏――〝頒叉咬〟ケレブスへと、並んで突進した。
途上、町に潜んでいた[
「我が『師』の帰還を阻ま」「貴様らを我が炎で飾っ」
全てが即座に、斬り裂かれて消えた。
その中でシャナが、
(『師』? さっきもそんなことを……あんな奴が?)
と疑問に思ったのは当然で、教授の性格は、およそ教育者や指導者に向いているとは言えない。あの天才は、自他を探求と実験の材料としてしか見ておらず、他者からの信望や評判などに一切の関心を払わない人物なのである。巻き込まれ、利用され、被害を受ける……それが彼と対した全員が受け取る報酬のはずだった。
が、悠二は、
(『師』……それに『同門』……そうか、こいつら[
かつて〝
「彼から迷惑を被る機会は、彼に接する時間と正比例する。つまり、付き合いが短ければ短いほど、彼は素晴らしい人物に見えるのだよ。行きずりの〝
もう一人の天才的な自在師から、教授の意外な一面を聞かされたときは、そんなまさか、と思ったものだが……今まさにその『そんなまさか』が、大挙して襲いかかってきている。
「おのれ!」「やらせるか!」「食らえ!」
群がり立って迫る彼ら、数十もの[
同門らは、各々自認する〝
そしてシャナは、その最後の一人、
「私を他の同門と――」
何事か言いかけたケレブスの三つ首を纏めて刎ね飛ばし、巨体を薙ぎ倒していた。
さらに悠二が、刎ね飛んだ三つ首が空中で燃え尽きる前に、
「はあっ!!」
素早く展開した『グランマティカ』で、それら老竹色の炎を捕らえる。箱状になった透明の煉瓦には、次々と自在式が移し込まれ、並べ立てられていった。頭上、今にも口を開けそうな環の分解に必要なパーツを拾い出すための、高速の解析作業である。
「急ぐ!」
「お願い――、うっ!?」
その背後に付こうとしたシャナ、すぐに悠二も、突如発生した突風に顔を顰める。
「な、なんだ!?」
ただの突風ではない、奇妙な違和感があった。
その根源は、まさに彼らの頭上――
アラストールは、世界法則の体現者としての怖気を覚え、叫ぶ。
「二人とも、近場の物に摑まれ!!」
「「!?」」
突然の叫びにも二人は従おうとするが、しかしもう、それは始まっていた。
空気だけでなく、濛々と上がる土砂、無数に舞う木の葉や枝、さらには見える全てを包括する一帯の空間までもが歪んで、ゆっくりとそこに引きずり込まれてゆく。
環の内に、無限の洞である両界の狭間が、暗い口を開けていた。
もはや作った者も、出迎える者もないまま、環は稼働を続ける。
膨大な数を集めて組み上げられた、行く先を定めない『
その結果、開いた口は、かつて創造神をも追逐した究極のやらいの刑『
歪む空間自体が、悠二とシャナを痛打する。
「ぐっ!」
「うあっ!!」
それでも悠二は拉げた鉄塔を強く摑み、かつシャナとより強く手を繋いでいた。まるで天地が逆転したような狭間への落下を、二人してなんとか堪える。
が、それも数秒、
空間の歪みが、繫がれた手を、砕いた。
「が」
「あっ――」
二人が離れた。離れて、遠ざかる。
悠二は躊躇わなかった。自分も鉄塔から手を離した。
「シャナ!!」
「悠二!!」
どちらも互いの名前だけを叫んで、危機を乗り越える力を得る。
勢いを増して天へと落ちる中、シャナは砕かれた手の代わりと、
「――『
具現化させた炎の腕を、長く伸ばす。
これを残った手で摑んだ悠二は、意識を研ぎ澄ませた。
(まだだ!)
辺りに散らばり、共に吞み込まれつつあった『グランマティカ』を再び結集させ、環を分解するための解析を再開する。高速で切り替わる自在式を、一つ、また一つと試し続けた。
シャナは悠二を強く抱き締め、背に燃やす紅蓮の双翼を全開にして落下に抗うが、それでも二人はジリジリと環の方へと引き擦られてゆく。周囲に、瓦や拳大の石が混じり始めた。
その、全てを吞み込む下方、あるいは彼方に、
(……っ)
シャナは、ふと誰かの気配を感じた――瞬間、
ビシッ!
と環の内に開いていた暗い口に、亀裂が入る。
(!!)
戦慄が途切れ、その裏返しの安堵が、フレイムヘイズの身に、どっと汗をかかせた。
吞み込む力が一気に弱まり、二人は逆さまだった姿勢を、クルリと元に戻す。
「ふう……なんとか、なったかな」
抱き締められていた悠二が、シャナとは真逆の、素直な安堵の吐息を漏らした。
その傍らには、解析によって得られた分解の自在式を込めた『グランマティカ』が、誇らしげに浮かんでいる。
自在法は稼働を停止し、やがて広がった亀裂が縁の環にまで到るや、外輪山をなぞるほどの威容全てが、呆気なく砕け散った。欠片は夜の闇へと溶け、消える。
いつしか晴れていた満天には、星が吞気に輝いていた。
紅蓮の双翼だけが、その中に異なる光を浮かべている。
かつて両界の狭間へと消えた『師』――〝
全く、胸を撫で下ろすような勝利だった。
シャナは抱き締めていた少年を離すと、
「お疲れ様、悠二。アラストールも」
改めて正面から、顔と顔を向き合わせた。
悠二もアラストールも、どこか力の抜けた様子で、ゆるりと答える。
「こちらこそ、ってところだね」
「うむ。一時は肝を冷やしたが……ともあれ無事で何よりだ」
そんな二人の声を聞いて、シャナは安堵だけでは足りなくなった。無事で終わった嬉しさを表そうと、二人が驚くほど急に、腕の痛みにも構わず、もう一度悠二を抱き締めた。
「うん、良かった」
夜半の地震と突風の噂に騒がしい、しかし何事もなく迎えた、翌日の昼下がり。
早くも
悠二は、シャナのために残念がる。
「別に急ぐ旅じゃないんだし、もう一週間くらい学校生活を楽しんでても良かったのに」
隣に在るシャナは、頓着なく首を振った。
「ううん、いい。元々、悠二が来るまでの退屈凌ぎだったんだし。それに――」
「?」
「皆には『またね』って言ったから」
悲しむでも寂しがるでもない、転校を告げる彼女のあまりな眩さに、悠二は――窓の外からこっそり窺っていた――別れを惜しむ級友らと同じように、ほろ苦く笑っていた。
と、そこに、珍しくアラストールが口を挟む。
「そんなことより、シャナ」
「なに?」
「次からは『坂井シャナ』という名前はよせ」
その主張は、育ての父として大いに真剣なものだったが、
「んー、どうしようかな」
娘の方は、あらぬ方を向いて誤魔化した。
悠二は、自分に飛び火しそうな話題への対処を考えかけて、気付く。
「
「うん」
シャナは平然と楽しげに、頷いてみせた。さらには坂道を上る軽やかさまで加えて、しかし決してふざけることなく、語り始める。
「ずっと悠二に考えさせてばかりだから……久しぶりに高校に潜入する、って決めたときに、私も少し、やり方を変えてみようと思った」
「やり方を」
「変える?」
悠二とアラストールによる、器用なバトンリレーの問いかけに、やはり軽く頷いて、
「うん。今までは色々と誤魔化して、真実が見えないようにしてきたでしょ? その方が、なにも後に残さないから、って理由で」
「――!」
「……?」
悠二は察して、アラストールは分からない。
シャナは、答えを待たず続ける。
「でも、こうして私の真実を見せて、なにかを残しながら進んでいけば……いつか、そのおかしさに誰かが気付くかも知れない。おかしさを、誰かが追いかけるかも知れない」
「それは不都合――」
言いかけてアラストールも感じ取り、彼の感じ取ったものをシャナが声にする。
「そんな人を、少しずつでも増やしていく。私たち皆を、近付けていくために。それを、この新世界『
「……」
悠二は、少女からの福音に耳を傾けつつ、涙を堪えていた。
分かってもらえる、というのは、こんなにも嬉しいことなのか。
他には決していない、これほどの子が、自分の傍にいてくれる。
この子に応え、自分は自分の道を、迷うことなく進んでゆこう。
そんな諸々の想いがこみ上げて、とても声を返せなかった。
アラストールもそれ以上は問わず、歩みは町を出る峠、外輪山の頂へと到った。
下ってゆく道は遙か遠くまで延び、果ては山間に隠れている。
どこまでも続いて見えるこの道に終点があるのか、今はまだ分からない。
しかし、終点があろうとなかろうと、歩いた分だけは確実に進んでゆける。
その一歩一歩をこの皆で踏み出そう、この皆で進もう、と悠二は思っていた。
やがて、
アラストールが苦々しく、
「おおよその話は了解した。だが、せめて姓はカルメルかサントメールにしろ」
シャナが明るく朗らかに、
「そういえば、狭間が開いた後から、この『コルデー』に少しだけ反応がある」
悠二が考え考え披露して、
「連中が
口々に語りながら、彼らは進んで行った。
どこまでも続く道を、確かに、一歩ずつ。
日々の想いを重ねながら、
果てなき歩みは続いてゆく。
今在る世界を、変える先へと。