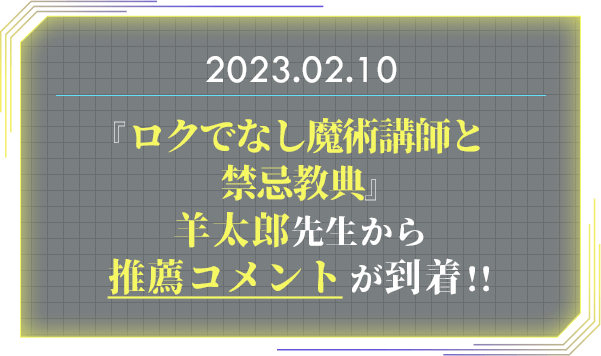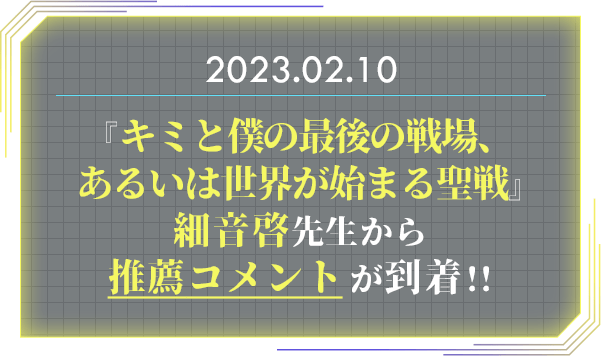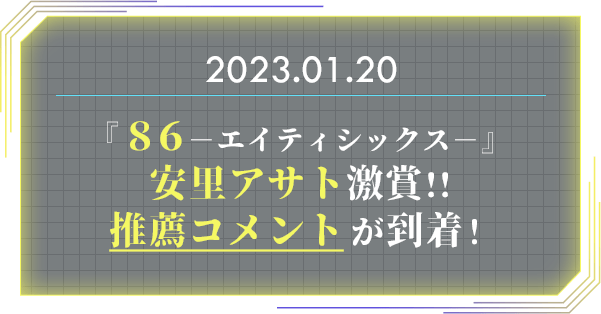気付いたら見知らぬ場所に居た――というとなんだか抜けている気がするが、実際そうなのだから仕方ない。池袋駅のホームで電車を待っていたある少年は、瞬きしたら見たこともない場所に立っていた。
「……え? 何? どこだここ」
初めて見る風景をきょろきょろと見渡す。ゲームなんかでよく見る、中世ヨーロッパ風のお洒落な街の公園だ。晴天の下、簡素な服を着た人々が行き交っている。
明らかに日本ではない非現実的な光景に、少年はぽかんと間抜けに口を開けた。
何かのドッキリ?
テレビの企画?
あるいは誘拐?
様々な可能性をひととおり考えて、どれもしっくり来ずに首をひねる。
ドッキリにしては地味だし、自分がテレビの企画の対象になるとも思えないし、誘拐なら犯人が近くにいないのもおかしい。そもそも自分を誘拐するメリットなんてない。
つまり最後の可能性。
「……うん、夢だ」
というかそれしかありえない。これは恐らく電車の席で見ている夢とかだろう。乗り込んだことも覚えていないのは意味がわからないが、まあ夢なんてそんなものだ。
「凄いな。これ明晰夢っていうんだっけ。明晰夢だとなんでもできるってマジかな?」
少年は辺りを見渡してみる。よく見れば中世ヨーロッパというより、知っているゲームの世界にも似ていた。
「しかしまたよく出来た夢だなぁ――この噴水の水とかちゃんと冷たいし」
手を伸ばしてみる。サラサラと冷たい水が手に当たって気持ちが良い。
噴水の水たまりも綺麗で、自分の顔がよく映っていた。自分でも凡庸だと思う、どこにでもいる高校生の顔だ。
「なんだよーせっかく夢ならもうちょっとかっこよくしてほしいなあ」
そして彼はもう少し周囲を見渡す。かなりの大きな公園で、後ろ側には森が繁っていた。
凄いな、と思わず感嘆する。
輝くばかりに美しいその森に、彼は近づいていった。夢の中の森とは思えないくらいリアルな香りだ。
なんだか懐かしい気がする香りだな――と思い、手前にある葉っぱに触れようとして。
ぷよ、と彼の手に柔らかいものが当たった。
「――ん?」
ふわっとした、マシュマロのような手触り。
夢にしてはどうにも感触がリアルなような。少なくとも植物ではないような。
恐る恐る視線をやると、森の中に深緑の髪に銀色の瞳の少女がむすっとした顔で立っていた。
自分の手の先には、その少女の豊満な、まぁいわゆるバストというやつが。
「……えと、これはゆ──」
「何するんですかああ!」
「すみません! ほんとすみません!!!」
少年はその場に思いっきり土下座をした。
「違うんですこれは事故で、夢だと思ってて、決してわざとじゃないというかなんというか」
「ええ!? 夢だったら胸を揉んでいいとでも思ってるんですか!?」
「いや決してそんなことは! とにかくこの通りですすみません!」
「すみませんで済んだら警察いらないんですよぉ!」
ひとしきり叫んだ少女。そしてため息をつく。
「……はあ。もう分かりましたから、頭上げてください」
必死に謝る彼の姿に、少女は少しだけ笑った。
「というかそもそも、私は夢ではなく現実ですから。それを教えに来たんですよ?」
「現実?」
顔を上げる。現実という言葉にさらに混乱した。
「現実って、夢かと思ったけどやっぱりドッキリ――」
「ちがいます! ほらあれですよ、分かりませんか? 異世界転生、ってやつです」
「い――異世界転生!?」
その言葉を聞いて、少年は目を輝かせる。
「ほんとにあった異世界転せ――って、んなわけないよな……」
と思ったら一瞬で目が曇った。
「普通に考えて異世界とか転生とかあるわけないし。どうせ夢だろうなぁ」
「だから夢じゃないんですってば。ほら、一度あっちを見てみてください」
少女は噴水広場の入口の方、街の方を指差す。
つられて視線を向けたが、何もない。ただ街の人々が行き交っているだけだ。
「? いったい何が――ん?」
言いかけて彼は気付いた。行き交う街の人々は何かに怯えている。誰もが青い顔をして、足早に街を通っていた。
「なんだ? 怯えてるような……」
「もっとよく見て。人間じゃないモノがいます」
よく見てと言われ、目を細めて街を覗く。何か黒い物があちこちに居るような気がした。子供のような体格で、棍棒のようなものを手に持っている。
「何かい――って、おわ!?」
覗いていると左から急に何かに襲われた。黒い身体を持つ小鬼のようなモンスターだ。
「なんだこいつ!?」
「それが証拠です! 勇者様!」
「なに!?」
襲われたこの痛みは夢じゃない――少年はそれを実感して、本当に自分が異世界に来てしまったのだと思った。こんなので実感したくはなかったけど。
小鬼は少年というより、少年がいつの間にか腰に差していた「剣」を狙っていたようだった。
「な――なんなんだこいつらは!?」
「それはゴブリン。この世界を脅かす魔族の一種です!」
気付くと、ゴブリンが何体も街の入口に現れていた。
街の人々が悲鳴を上げて逃げまどっている。
「ゴブリン!? 本物だ!」
「何を感心してるんですか! あれはとても弱いですが、この世界を脅かす魔族ですよ!?」
「へえ。『魔族』ね。なるほどな。だんだん読めてきたぞ」
つまり少年はその魔族を倒すために召喚されたのだ。
「そういうことなら話が早い。とりあえずアレを倒せばいいんだな」
「ええ、お願いします! 今の貴方には召喚特典で色々スキルがありますから、あの程度は難しくはないはずです!」
「よし、ならまずそのスキルを発動するぞ」
手を前に伸ばす。何故か発動のやり方は理解していた。
手のひらに魔力(?)を集中させる。この魔力を練って手から放出させるのだと、感覚で分かっていた。
「なんだ結構簡単なんだな。スキル・ドラゴ――」
ちゃりん、とその時、音がした。
「……ん?」
勢いよく手を伸ばした動きで、腰のポケットに入っている何かが音を立てたようだ。
なんだと思いポケットに手を入れ、取り出して目を見開く。
「兎……?」
兎のキーホルダーがあった。どこにでもあるプラスチック製の。
自分のポケットに入っていたキーホルダーなのに、彼には全く見覚えがない。自分で手に入れたものではない、というのはなんとなく覚えていた。
ならどうして自分が持っているのか――一瞬混乱したものの、そんなことを考えている場合ではないのでポケットに再びそれを突っ込む。
改めて彼は目の前のゴブリンを見た。そこにいるのは、現実からは程遠い姿をした醜い化け物。これから自分が倒すべき敵――
「――え?」
そのゴブリンの姿が一瞬、ノイズのように揺らめいて見えたのだ。
ほんの瞬きくらいの時間だったが、暴れるゴブリンの頭や手足が一瞬違う姿に見えた気がした。その姿に強い違和感を覚え、少年はそれに攻撃の手を止める。
「……なあ。今あいつらの姿が――」
「いつまでぼーっとしてるんですか。ゴブリンくらいちゃちゃっと倒しちゃってくださいよ」
覗き込む少女に視界を遮られて、少年は我に返る。次にゴブリンを見たときは、そんな面影など全くなかった。
少女は惚けている彼の耳元で囁く。
「せっかく理想の世界に来れたんですから。遠慮することなんてないんですよ?」
妖しい声に、少年は段々と思考をかき乱されていく。理想の世界に来れたんだから――
「ここには貴方を傷付ける者なんてどこにもいない。ずっと楽しい世界に居られるんです。前にいた場所なんてもう必要ないじゃないですか」
混乱する彼を励ますように、《女神》の手が彼の手を取る。
「念じれば叶う。望めば手に入る。それが貴方のスキルです。唱えてみてください。貴方が手に入れたその力を」
少年は自分の心に耳を澄ます。ようやく手に入れた自分の「力」。
念じれば確かに様々なイメージが浮かんでくる。これは――炎? 龍の形をしている。ということは。
「スキル――龍炎発動!」
龍の形をした炎が右手から出て思わず感嘆の声を上げた。
大質量の炎が空気を薙ぎ払い、逃げ腰になるゴブリンたちに突っ込んでいく――
・・・
「――突っ込んで来るぞ! 衝撃に備えろ!!」
同時刻、池袋駅。野戦服を纏った少年少女が、誰かの号令と共に散開した。
ある者は接近した状態から、類稀なる身体能力で。
ある者はそれまで持っていた銃を捨て、身を護るように。
ある者は持っていた刀を軸にし、踊るように。
彼等がそれぞれに退避した後の空気を、大質量の炎が薙ぎ払う。焼け焦げる匂いが嫌でも鼻についた。
巨大な龍の形をした炎は、高さにして数メートルはあった。もはや消火活動も意味をなさない中、少年少女は熱さに耐え顔を上げる。
そのうちの一人、大人びた顔付きの少年は、炎が出現したあたりの空間をじっと睨み付けた。視線の先、人のいない終電間際の池袋駅山手線ホームに。
「……化け物め」
異形がそこに居た。
二本の触覚を頭から生やし、顔は黒く塗り潰されていて見えない。二足歩行で、一見普通の人間と大差ない姿をしているが、体長は三メートルを超え、身体からは無数の突起が露出している。
明らかに自然界には存在しない生物だ。先程の炎を撃ったのもこの異形の生き物で、少年少女の討つべき敵でもあった。
その異形から決して視線を切らず、大人びた少年は無線イヤホンに静かに声を掛ける。
「こちらは問題ない。……各員、状況を知らせろ」
『おう隊長。こっちは無事だ』
『私も無事だよー。あっついけど当たってない』
数人の声が返ってきて、少年はホッと息を吐く。声の調子から考えても怪我もなさそうだ。
通信の向こうから、少しふざけた声が聞こえる。
『いやぁしかし相変わらず凄いねー、戦士型は』
『やっぱりあれ戦士型か。雰囲気的に魔導師型の感じがしたんだがな』
『魔導師型はこんなにパワーないよ。厄介な能力持ってなくて、単純な力押しの攻撃で済ませようとするのが戦士型だからさ』
『おー、じゃあ今日はしっかり楽しめそうだなぁ』
その声にやめろ、と少年は軽く制す。
「終電後とはいえターミナル駅だ。いくら人が少ないとはいえ、早めに片付けたい」
『冗談だっての。堅いなぁアズマは』
嗤うような軽薄な声に、アズマと呼ばれた少年はふ、と呆れたように目尻を下げる。
終電後の山手線ホームに人はほとんどいなかった。生きていない人間はちらほら見かけるが、ホームの周囲には人ひとり近づかない。その内側にいるのは、駅の職員でも警察でもないのに点在する少年少女。
「奴が現れてから既に三十分。これ以上の被害を出すわけにはいかない」
鋭い瞳でそう言った少年の背後で炎が上がった。先程の化物が発した炎だ。池袋駅で停車していた歪な形の車両が燃え上がり、ホーム上のスプリンクラーが発動――撒き散らされる水滴と熱でうだるような空気の中、彼等はただ冷徹にその化物を睨む。
今まさにホームを燃やし、それ以前に何人もの乗客を死に追いやった、その化物の名は。
「《勇者》……」
【シャアアアアアアアアア!!】
蟲が翅を擦り合わせた時に出るような、寒気がする不気味な音だった。そんな音を口――と思われる場所から発する「それ」を、少年は睨む。睨んだまま無線イヤホン型通信機に向かって声を発する。
「時間がない。――最低でも五分以内に仕留めるぞ」
それぞれ返事が戻り、彼の作戦指揮のもとに少年少女は作戦を開始した。
【ガギィイイァ! アアア――ゴギグアア――】
「煩いな。人間の言葉を喋れよ」
誰に言うでもなく、アズマは忌々しく吐き捨てる。
異形が動きを見せた。二本の触覚がピンと張り、異形の後方に複数の何かが出現する気配。
全員が警戒する。その「何か」は渦を巻くように出現――水だ。直径が数メートルもある水の球体が複数、空間に出現していた。
その球体は形作られてすぐ、全員が予想した通り前方に射出された。全員がそれぞれに可能な回避を取り、水球はホームに衝突して反対側の線路を吹き飛ばす。
相当な威力がある水球らしい。掠っただけでもひとたまりもない。
「警察が来るまで三分といったところか――それまでに片を付ける」
まるで泣き叫ぶように咆哮する化物。また新たなエネルギーを放出しようとしている。
「《勇者》は基本的に皆異常だが、唯一弱点がある。そこを叩けば終わりだ」
『わかってる。あいつらの心臓部、でしょ』
砲撃音。溌剌とした少女の無線から。
ほぼ同時に化物の側頭部が吹き飛んだ。その隙にと、アズマは腰に提げていた刀をすらりと抜く。通信の向こうで少年の笑い声が聞こえた。
『ハハ、相変わらずお前のそれは見応えあるなぁ』
「煩い。お前も大して変わらないだろう」
美しい――そして醜い刀だった。銀色の刃のところどころに血のようなものが張り巡らされ、まるで生きているかのようだ。血はただの返り血の類ではなく、まるで血管が張り巡らされているようにも見える。純然たる生き物ではなく、――しかし確実に人工物ではないそれ。
一瞬目を瞑り、アズマは呟く。
「『卵』は左胸前部、ちょうど人間の心臓に当たる部分」
『おっけー。アズマが近いね。頼――ってもう行ってるか』
少年は誰よりも早く単身で突っ込んだ。瞳に映るのは明らかな異常を持つ化け物。
耳に届くのは、その心臓の鼓動。
煩いくらいに響く。今の彼にはどんな騒音よりも、小さな心臓の鼓動が耳に響いていた。弱った心臓を無理やり動かしているような、儚く悍しい音。
刀を振り抜いた。少し遠い化物の肉体に、的確に斬、と刃を突き立てる――左胸前部。
【ギャア――アアアア!】
突き立てられた方は目を見開き、何かをかきむしるような動きをしている。
「さっさと死んでおけ。――誰かを殺すその前に」
【ダ、レ――ギ、ガ、ナニガ――】
最後に何かを言おうとする化物の肉体から、構わず彼は刀を抜いた。およそ通常のものとも思えない刀の先端に、小さな球形の何かが刺されていた。まるで生き物のように蠢いている。
ザッ、と蠢く球形の心臓を踏み潰し、少年はその動きを止めた。
それと同時に異形も動きを止めて、ゆっくりと仰け反った。顔を纏う闇が晴れて一瞬あどけない顔が覗き、同時に消えてゆく。
凡庸な、どこにでもいる高校生の顔だった。そんな「彼」に、少年は視線すらやらない。
憎らしく。それでいて無関心に――まるで最初から、そこに何もなかったかのように。