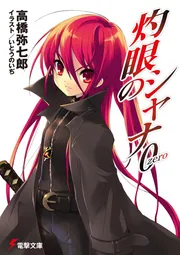プロローグ
その日。
その日も、
高校一年の四月末。新しい環境にもそこそこ慣れ、受験や将来について深刻ぶる時期は、
家庭は中流。一人っ子で両親は健在。ただし、父・
成績は中学のときから、中の上下を行ったり来たり。自分を
彼女はいない。隣席の
目下の悩みは、迫るゴールデンウィークでの金の使い道。親しい友人たちとどこかに出かけたくもあるが、買いたいゲームやマンガもいくつかある。
その日の放課後に、学校を含めた住宅地の対岸、大鉄橋で結ばれた市街地に足を向けたのも、ゲーム店と本屋を巡って、そのあたりの
その日、
そのときまで、
悠二はそんな日常が永遠に続くと思っていた。
いや、そこまでの自覚さえ持たず、当然のように、無根拠な確信の中にいた。
しかし、その日、そのとき、
血のように赤い夕焼けの中で、彼の日常は、確信は、あまりに
あるいは、燃え上がった。