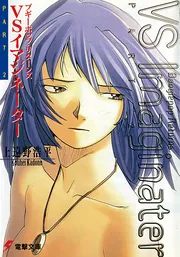ブギーポップ・リターンズ VSイマジネーターPart1
プロローグ
それは、春とは名ばかりでまだまだ寒く、雪さえ降っている三月の初めのことでした。
私の学校、県立高等学校深陽学園の屋上からひとりの少女が飛び降りたのです。その少女の名は
「
彼女がまだ生きていた頃、私にそんな風に話しかけてきたことがありました。私はその当時流行っていたポップスナンバーの歌手の名前を何気なく口にしました。
「へえ、ああいうのがいいの?」
「うん。なんかカッコいいじゃん」
私としては気軽な気持ちでそう言ったのですが、透子さんは「ふうん……」と軽く息を吸うと、夕暮れの空に向かって口笛を吹き始めました。
私の学校は山の中にあるので、ほとんどの生徒はバス通学です。そのとき通学路を下校のために歩いていたのは私と透子さんだけでした。
その口笛の曲は、いま私が好きだと言った歌手の代表曲でした。それはとってもうまくて、そしてすごく綺麗な音になっていました。本物の曲よりも、ずっとずっと素晴らしく、彼女が吹き終わると、私は思わず拍手していました。
「──すっごおい! 透子、うまいのねぇ!」
「いや、綺麗に聞こえたとしたら、それはあなたの〝この音が好き〟という気持ちがそうさせたのよ」
彼女は、こういうすこし芝居がかったようなことを、割合すらすらと言う人でした。そして、それが似合う人でもありました。
「練習したんでしょうね。なにか楽器とかやってるんだっけ?」
「いいえ。もっぱら聞く方ね」
「じゃあ、音感ってヤツ? あれがいいのかもね。──じゃあ、普段はどんなのを聞いているの?」
「あまり、人が聞かないようなものが多いかもね」
「どんなの?」
「そう、たとえば──」
と、また一息吸うと、透子さんはふたたび曲を奏ではじめました。
今度は口笛だけでなく、ハミングが主体でした。彼女はまるで、どんな音でも再現できる魔法の楽器であるかのようでした。
「…………!」
私は息をするのも忘れるほどでした。
それは、さっきの曲などとは比較にならない、胸が高鳴り、心に響き、そしてなんだか、とても切なくなるような──それでいて、とてもリズミカルな力強い不思議な曲でした。
終わっても、私は拍手できませんでした。胸がいっぱいで、涙ぐんでいたからです。
「──どうかしら? あまり好みじゃなかった?」
「ううん──ううん! なんか、なんか──恥ずかしいわ。さっきの曲が、なんだか
「あなたが好きな曲じゃなかったの?」
「……いいえ。たぶん、本気じゃなかったのよ。今の曲を聴いて、本当に音楽がいいってはじめて思ったような気がしたわ。そう、流行りだとかそういうのとは全然関係なしに!」
私は興奮して大きな声を出してしまいました。
「そう──良かったわ」
そう言って微笑む透子さんは、今の曲と同じくらい──いいえ、それ以上に美しく、まるで夕焼けの赤い光の中で、そのシルエットは女神のようでさえありました。
「なんていう曲なの? 教えて!」
私が聞くと、彼女はくすくすと笑いました。
「笑わない?」
「え? どうして」
「曲のタイトルは〝サロメ〟、バレエ音楽よ」
「──それがなんでヘンなの?」
「作曲が、
「?」
「このひと、怪獣映画の曲で有名なのよね──」
そう言って、透子さんは口元に軽く握ったこぶしを当てて、肩を上下に揺らして笑いました。
その仕草はとっても女の子らしくて、私はなんだかどきどきしました。私にはとっても、そんな風に自然に笑うことはできないと思ったからです。──いいえ、他の誰にも、彼女のように、ただただ素敵に、純粋に笑うことはできないでしょう。
でも、その彼女はもういません。
私には不思議でなりませんでした……どうして彼女が死ななくてはならないのでしょう?
彼女は遺書も何も遺さなかったと言います。だから彼女が苦しんでいて、それで死んだのか、それとも彼女なりの何らかの意思表示のために死んだのか、私たちにはまるでわかりません。
でも、私はわかりたかった。
彼女と私は、実のところそれほど親しいと言うほどの仲ではありませんでした。
時折、彼女と二人きりになる機会があって、そこで親しく話してもらっていた──それだけです。
でも、彼女は間違いなく、私の短い人生のなかで、私が〝ほんものだ〟と思えたひとだったのです。他には何もありませんでした。みんな、他のものを真似して、無理矢理にそれが自分のものだと思いこもうとしている偽物ばかりでした。
だから、その彼女が飛び降りたのなら、きっとそこには何かがある、と私は思います。
だから、私も彼女を追ってみます。
跡追い心中? ──かも知れません。
でも、私は彼女のことが好きだったのか、それさえもうよくわからないのです。結局、私は何もわからないままに終わるのだ、と思います──。
──小宮
空は暗い。
夕暮れはとうに過ぎ、世界から光は急速に失せていく。
「…………透子さん」
彼女は屋上から下を見おろす。
その下には、まだ水乃星透子が叩きつけられた跡の、白い線が残されている。半ば闇と化した地上で、それだけが妙に光って、浮かび上がって見える。
ごくり、と唾を飲み込む。
いつか、水乃星透子が言っていた言葉を思い出す。
〝小宮さん、この世の中には、決まりごとなんてホントは何もないのよ。すべては不確定で、どんなことだって「不自然」なことはない……鳥が空から落ちることもあるし、四月に雪が降ることだってあるのよ〟
どういう意味だったのだろう?
それが、この柵を越えればわかるかも知れない……!
白い線が動いて、彼女を手招きした。その幻覚は幻と言うにはあまりに自然で、真理子にはごく当たり前のものに見えた。
そう、もう自分の人生は、そこに行く以外にまともな可能性はない──そういう衝動が湧き上がってきた。ぶるぶるぶる、と恐怖でなく、興奮で身体が震えた。
「透子さん……!」
小宮真理子は、思い切って手を鉄のフェンスに掛けた。
そこに、声が掛けられた。
「──君は水乃星透子の跡を追いたいのかい? だったら、そいつは無理だよ。それじゃあ不可能だ」
少年のような、少女のような、どちらでもないような奇妙な声だった。
「───?!」
真理子はびっくりして振り返った。
なかば闇に隠れた屋上の一画に、そいつはいつの間にか座っていた。
筒のような黒い帽子を目深に被って、鋲のたくさん付いた黒いマントを着ている。白い顔に、黒のルージュが引かれている。
「君がそこから飛び降りたところで、彼女のいるところには行けまいよ」
黒帽子は静かに言った。
「──あ、あなたは……?」
真理子は絶句した。黒帽子のことを知らないからではない。逆に、そいつのことはよく知っていた。彼女の学校の、女子の間でだけそいつのことはさんざん噂になっていたのだ。
でも、本当にいるなんて……?
「ぼくのことを知っているみたいだな。ならば話は早い」
黒帽子は左眼を細め、右の口元を吊り上げる、左右非対称の奇妙な表情を見せた。
「ど、どういうことなの? なんで私が透子さんのところに行けないのよ?」
「それは簡単だ。君は自らの意志で命を絶とうとしている。しかし水乃星透子はそうではなかったからだ。もしも天国というものがあったとしても、君の行くところは彼女の行った先とは別のところになるだろう」
黒帽子は、ほとんど冷ややかと言ってもいいような突き放した声で言った。
「〝そうではなかった〟って──どういう意味?」
真理子は足下が崩れ去るような不安感を覚えていた。
「君は、ぼくの名前を知っているのだろう。だったら、ぼくの〝役目〟も知っているはずだ」
黒帽子の姿は闇に半分塗りつぶされている。それは、まるで空間に溶け込んでいるようにも見える。
「ま、まさか──それじゃあ」
「そうだ。ぼくは死神──水乃星透子は、自殺じゃなくぼくが殺したのさ」
「ど、どうして?!」
「彼女が世界の敵だったからだ」
きっぱりと言った。
「…………!」
「どうする? それでも死ぬかい? 悪いけど、ぼくは君の方は殺す気はないよ。残念ながら君にはそれだけの価値はない」
「で、でも……だって──」
真理子は混乱していた。なにがなんだか、まるでわからない。
世界の敵だった? 透子さんが? いったい何のことだ? どういうことなのだろう?
「──あるいはこういう言い方さえできる。水乃星透子はまだ〝あの世〟とやらに着いてさえいない、とね。彼女はぼくと違って〝分裂〟していなかったが、それでも〝自動的〟であったことには変わりない。果たして今どこにいるのか──ぼくにもわからないままだ」
黒帽子の言葉は、真理子にはまったく理解不能のものだった。
あの世に着いていない──?
真理子は反射的に、柵の向こうの地面に目を向けた。もう、闇が深くなっていて白い線さえ見えなくなっていた。
そんなバカな……真理子は確かに、血の滲んだ白い布で覆われて、外に運び出されていく彼女を、かつて彼女だったものを見ているのだ。あれは何だったというのか。
「どういうことなの?! ブギー──」
振り返った真理子だったが、既に黒帽子の姿はそこにはなかった。
「え……?」
あわてて周囲を見回す。しかし、もう闇が深すぎて、あの黒い姿がどこにまぎれたのか判別は不可能になっていた。
いや、それとも──最初から実体がなくて……。
「…………」
ここでやっと、真理子の心に恐怖が湧き起こってきた。
ばっ、と再び地面の方に向き直る。
だが、さっきまではあんなにたやすく越えられそうだったフェンスが、今では何百メートルもの高さに変わってしまったかのようだった。
「うう……」
〝そいつは無理だよ〟
〝彼女のいるところには行けまい〟
〝まだあの世に着いてさえ──〟
「ううう……!」
がくがくがく、と足が震えていた。
そして真理子は、ずるずるとその場に崩れ落ちた。あとからあとから涙が出てきて、どうしても止まらなかった。それは、水乃星透子が死んでから、彼女が流したはじめての涙だった。
泣くくらいなら死んだ方がましだったのに、真理子はもう、泣いてしまったのだ。
「ごめんなさい、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい……」
お経のように、真理子はぶつぶつと呟き続けた。その声はかすかで、夜の中にすぐに拡散して消えていくしかなかった。
「…………」
その姿を、いつの間にか下に降りていた黒帽子が、地面から見上げていた。その足下には人の形をした白い線が引かれている。
黒帽子は膝をついて、その線の上を撫でる。
「……しかし、もう
囁くように言うと、黒帽子は立ち上がる。
「まだ続いているのか〝イマジネーター〟……」
黒いマントが、夜の風に巻き上げられて激しく踊った。