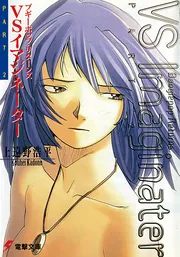ブギーポップ・リターンズ VSイマジネーターPart1
Ⅰ ①
「ときどき、夜中にはっと目が醒めてしまうことがあるんです」
そう言う少女、
「ふむ」
「よくある、つまんない怪談みたいなんですけど、なにかが胸の上に乗っかっていて、自分を覗き込んでいるような気がするんです。でも目を開けてみると……」
「なにもない、というわけか」
「はい。いや、きっと夢なんだろうって自分でもわかってるんですけど、でも何度も何度もあるんです。だから──」
佐和子は肩を震わせた。その髪は二ヶ月前あたりにかけたソバージュがかろうじて残っているだけで、およそ気を使っていない。無理もなかった。入試まであと四ヶ月しかないのだ。寸前になるとストレートパーマをかけたりして、面接採点者の印象をよくするように気をつけ始めるだろうが、今はまだそんな余裕もない。
「その〝影〟だが」
飛鳥井は彼女の言葉を途中でさえぎるようにして言った。
「君に何か話しかけてくるんじゃないのか?」
佐和子はびっくりした顔で飛鳥井を見上げてきた。
「そう──そうなんです! どうしてわかるんですか?!」
彼女の疑問には答えず、飛鳥井はさらに訊ねる。
「なにを言っているのか、覚えているかい」
「……いいえ、それが」
「どうしても思い出せない、というわけか」
「はい」
彼女はうなずく。
狭い室内にいるのは二人だけだ。ただでさえ少ないスペースに大人数を押し込めるようにつくられている予備校の、さらに校舎の端にある進路相談室は、ほとんど牢屋の独房なみに狭苦しい。
ひとつしかない、それも縦に細長く横幅がほとんどない窓から線のような光が射し込んできている。その色は赤い。もう、夕暮れなのだ。
「……ふむ」
飛鳥井は口を閉ざして、少女の胸元のあたりに目をやった。
(……根がないな)
彼は心の中でひとりごちる。
(葉も少ない……つぼみばかりが大きい。そのくせ幹は今にも折れそうだ)
飛鳥井が黙ってしまったので、佐和子は不安になったらしく、膝の上でやたらと指を組みかえはじめた。
「──あ、あの、飛鳥井先生」
「…………」
話しかけても、彼は返事をしない。
彼は、顎の尖った細面の、物静かなイメージの綺麗な顔をしている。それに年齢も佐和子とほとんど変わらない。まだ二十歳そこそこだ。国立大学に在学しながら、アルバイトで予備校の美術講師をやっている。
そして、あまり他の者がやりたがらない進路相談担当も。
「…………」
彼女は、おそるおそる飛鳥井の顔を見上げた。いつのまにか、彼は彼女から視線を外して窓の外を見ている。
「ど、どうもすみません。ヘンなこと相談しちゃって──」
佐和子がいたたまれなくなってそう呟いたとき、飛鳥井は静かに話し出した。
「仮にも予備校の講師がこういうことを言うのも何なんだが……君は、あんまり受験というものを
「え?」
「一流大学に入ったって、悩みがなくなる訳じゃないし、幸せな将来が保証されるわけでもない。ムキになってがんばって、それで入った大学で何もすることがなくて呆然としてしまう人間というのは多い。勉強ばかりしていたので、他に何をしていいのかわからなくなるんだ。しょうがないから、一級公務員試験とか目指したりして、自分の将来を意味もなく狭めてしまったりする。たとえ目の前に愛すべき
淡々と、詩を詠うようにして彼は話す。
「大学に在籍していても気持ちは受験生のままだ。それでストレートに受かる人間というのは、これは稀だ。だいたいは落ちる。そしてまた浪人となる。貴重な青春を、浪人ばかりして過ごす羽目になって、精神をねじくれさせてしまう──」
彼女はぽかん、として彼の話を聞くしかない。
「──わかるかな」
飛鳥井は少女の方を向いた。
「い、いえ、その……」
「君は、なんとなくそういうことを、もう知っているんだ。それでもそういうことを考えないようにして、必死でがんばっている。しかし──がんばるということと、現実から目を背けるということは別なんだ。無理をするな、とは今の受験体制ではとても言えない。無理して勉強しなければ合格できない。でも、だからと言ってその成果に過剰な期待をするのはよくない。ひどく陳腐な言い方になってしまうが、大学に入るだけが人生じゃないんだ。影の夢は、君が無意識にしてしまっている〝大学に入ること〟に対しての〝ちょっと待て〟という心の奥底からのサインなんだよ。君は、少し冷静になるべきなんだろうと思うよ、僕は」
「──はい」
彼女は神妙にうなずいた。
「でも、やっぱり……」
「うん。だから努力はしなくっちゃならない。大学に入りたいと思うこと、それ自体は別に悪いことでも無理のあることでも何でもないんだから。ただ、君が思い詰めるのがよくないと言うことだ。それに、今のままだとどうせプレッシャーがきつすぎて入試にうまく対応できないと思うよ」
「──わかった、ような気がします」
佐和子は神妙だ。
(……すこし、つぼみがゆるんできたな)
また、飛鳥井は心の中でひとり呟く。
(もう少し葉がつけばもっといいんだが……そうすぐに苦しみは消えないか)
彼の眼差しは、また少女の胸元に降りている。
そこにあるものを見ているのだ。
少女自身にも、他の何者にも見えないものを。
それからしばらく、二人はもっと具体的に佐和子が行き詰まりを感じている科目への対処法を話し合った。
「──ありがとうございました!」
そう言って少女が席から立ったのは二十分後のことだった。
「君の努力は本物だよ。だから、あとは落ち着いて進めることを考えればいい」
「はい! ……でも、先生、すごくすっきりしました。先生は何かやってらっしゃるんですか? セラピストとかカウンセラーとか、なにかそういうの」
「いいや、別に」
「向いてますよ、すっごく! 先生顔も頭もいいし」
飛鳥井は苦笑した。彼女は「あ!」と口元を押さえた。
「ご、ごめんなさい。失礼なこと言っちゃった」
「考えておくよ。絵描きじゃ食えないって言うしね」
飛鳥井は笑って言った。
それじゃ、と立ち去りかけて、彼女はふっと思い出したかのように振り返った。
「ああ、そうだ。先生、〝時には四月にも雪が降る〟ってなんです?」
「え?」
飛鳥井はぎくりとした。
「なんだって?」
「いえ、例の夢の中で、その一言だけ覚えてるんです。──ああ、でもきっと大したことじゃありませんよね! 失礼しました!」
相談に来たときとは正反対の明るい声を残して、佐和子は去った。
「……四月にも、雪が降る……?」
なぜだろう──その言葉を聞くと、飛鳥井の心の中で何かがざわめくような気がした。