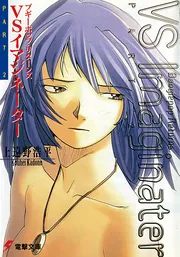ブギーポップ・リターンズ VSイマジネーターPart1
Ⅰ ②
*
飛鳥井仁は〝人の心の欠落しているものが見える〟自分の奇妙な能力について考えるときに、いつも思い出すのはサン‐テグジュペリの『星の王子さま』である。たしか三歳か四歳頃に読んだと思うのだが、その中の一節で「この子がきれいなのは、心の中に薔薇を一輪持っているからだ」というようなことが書いてあったのを覚えている。
それが、彼の中にイメージとして刻み込まれ、刷り込まれたような気がするのだ。
彼の目には、人はみな胸元に一本の植物を差しているように見える。その
たとえば花がない。葉がない。幹がない。そして今の少女のように根がない。どんな人間でも完全な植物を自分の胸の内に持っている者はいない。
必ず、何かが欠けているのだ。
だから、彼の〝相談〟というのは、その相手の欠けているものを補うようなことを言ってやるだけでいい。〝根〟がないものには、もう少し自信を持て、というような、ごく単純なことをだ。しかし、みんなそれで満足して、生き生きと生気を取り戻す。
予備校での仕事を終えて、アパートへの帰り道、にぎやかな繁華街の雑踏の中を歩いていると、みんなの胸に何かが欠けているのが嫌でも目に入る。
時々、うんざりすることがある。
人間の努力というのは、つまるところこの自分に欠けているものを手に入れようとすることである。彼にはそれがわかる。だが、人々に本当に足りないものは初めから心の中にはなく、決して手に入らない……。
彼はたまに、自分の胸元を見てみることがある。
だが、自分の心の中の花は見えない。おそらく彼自身にも欠けているものがあって、それが彼を切なくさせているのだろう。でも、それを彼が手に入れることはないのだ。
「……だからよぉ、俺ぁ言ってやったんだよぉ……」
「……なにそれぇ……」
「……きゃはは、バッカじゃねーの……」
老若男女の酔っぱらい達がげらげら笑いながら彼の横を通り過ぎていく。
彼らは、自分たちに根がなかったり、花がなかったりすることなど考えもしないだろう。
(知らない方が幸せかもな……)
彼は幼い頃から、ずっと孤立感を感じて生きてきた。これからもそうだろう。
「……お、見ろよ。雪だぞ」
「ああ、ホントだあ! わあキレイ!」
みんなが歓声を上げだしたので、飛鳥井もうつむいていた顔を上げた。
夜空から白いものが降ってきていた。
(ああ、いいな。雪は……)
なにもかも白くしてしまう雪は、彼が好きなもののひとつだ。雪の下では花が咲くことがないからかも知れなかった。余計なことを考えなくてもすむようにしてくれるような……そんな気がするのだ。
だが爽やかな気持ちで空を振り仰いだ彼の表情は、途中で強張った。
近くのビルの五階あたり、その窓のひとつに少女がひとり立っていた。
足は窓枠の上で、身を完全に外に出して、今にも飛び降りそうな態勢になっている。
下を見おろしている彼女と、空を見上げている飛鳥井の目と目が合う。
少女はかすかに、眼だけで微笑んだ。そして、
「危な……!」
と飛鳥井が叫びかけたところで彼女はその身体を宙に躍らせた。
飛鳥井は、反射的にそっちの方へ走った。
だが足がもつれて、彼はぶざまにすっ転んでしまった。
あわてて起きあがろうとして上を向いた彼は、そこにあり得ないものを見た。
〝ふふふ……〟
少女が、笑ったまま、まだ宙に浮かんでいたのだ。
その笑顔は独特の表情を持っていた。口元は真一文字に切り結ばれて、眼だけが妖しく、甘く笑っている。
落ちかけたところで、ぴたり、と空中に固定されたように、動かない。
「……え?」
彼が呆然としていると、
「おい、何寝てんだ! じゃまだよニイちゃん!」
という濁声がした。酔っぱらい達が彼に進路を妨害されて、それで怒っていた。
「あ、あんたたち、あれを──」
と彼は、宙に浮かぶ少女を指さすが「ああん?」と誰一人取り合わない。
「なに言ってんだ?」
「おい、飲み過ぎたんじゃねえのか?」
確かに他の者も彼が示す方を見るのだが、少女の姿は彼以外の誰にも見えていないらしい。
(……ど、どういうことだ……?)
彼は立ち上がり、啞然として少女を見上げた。
よく見ると、少女はごくわずかなスピードで、今も落下しているようだった。舞い乱れている髪が、ふわり、とかすかに揺れている。
〝ふふふ〟
笑うその両眼は、そこだけが空にあいた穴のように光を吸い込む。
〝人に見えないものが見えるというのは、決して楽しいことではないわね、飛鳥井先生〟
少女が囁く声が耳元で聞こえた。
「なんだって……?」
〝あなたの気持ちはとてもよくわかるわ……私も昔はそうだったものよ〟
飛鳥井はふらふらと、落下中の少女の真下にまで近づいていった。
「き、君も、って──」
〝あなたの超知覚と同じように、私には人の死が見える〟
少女の表情はまったく変わらない──固く結ばれている口も動いていない。彼女の周囲だけ時間が極端に遅くなっているかのようだった。
「〝死〟だって……?」
〝正確に言うなら、生命とされているものが燃え尽きる寸前に生じるエネルギー体、と言うべきかしら──〟
また、ふふ、と笑う気配がした。
〝──私は、人が死を使うことができるようになる可能性。そういう風に世界を造りかえるのが、私の使命。私は今の世界にとっての敵。春になってもまだ世界に冷たさを運ぶ、四月に降る雪〟
「……え?」
〝私の仕事に協力していただけません? 飛鳥井先生〟
「──なんのことだ? いったい君はなにを言っているんだ? 君は誰なんだ?!」
彼は叫んだ。
周囲の人間が訝しげに、何もない空に向かって怒鳴っている彼を見やったが、酔っているのだと思われて何とも言われない。
その上空で、少女は笑ったまま言う。
〝敵は私のことを〈イマジネーター〉と呼ぶわ〟
そして消えた。
「ま、待て!」
彼は手を伸ばした。だがその指先は何もない虚空を摑むだけだ。
「…………」
彼は愕然として、がっくりと肩を落とした。とうとう自分は狂ってしまったのだ、と思った。幻覚だ。そうに決まっている──と、足下に目を落として、彼はあっ、と声を上げそうになる。
降ってきていた雪が、彼の周りだけ切り取られたように、積もらずに道路の地を露出させていたのだ。
その形は、さながら影絵のように、空から落ちてきていた少女の姿を写し出していた。
……飛鳥井がアパートに帰ってくると、待ちかねていたように隣室の窓からひとりの娘が顔を出した。
「──やっと帰ってきたあ! おかえりなさーい!」
明るい声と表情の、彼女はアパートオーナーの娘、
「……な、なんだい?」
彼はまだ半ば自失状態だったので、琴絵にうろんな返事をした。
「仁にいさん、ご飯まだでしょう? 今日、あたしシチューつくったから、分けたげようと思って」
「う、うん──ありがとう」
「じゃ、あとで部屋に持っていくから!」
彼女は窓から顔を引っ込めた。
彼女はいつもこんな調子だ。飛鳥井の父親が二年前に死んでから、彼は叔父のアパートに部屋を借りているのである。といっても世話にはなっていない。大学の学費は奨学金を取っているし、画材などの諸雑費や生活費、そして部屋代も予備校で稼いでいるからだ。保証人なしでも部屋を貸してもらえたのが唯一の面倒だろう。