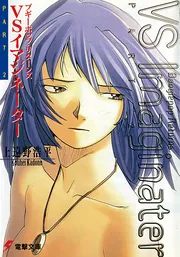ブギーポップ・リターンズ VSイマジネーターPart2
Ⅰ ③
その夜は飲み会になり、仁も父親と一緒に琴絵の家に泊まった。
琴絵は、なんとかして仁に話しかけようとしたが、彼は父親たちの横から離してもらえず、きっかけをつかめない。
だが一度だけ、仁が父親に胃薬を飲ませなきゃと言い出して台所に水をもらいに来たとき、やっと琴絵は、
「あ、あの……」
と彼の前に立つことができた。何年も前から願ってきたことだった。
「あ、すみません。水をいただけませんか」
と仁は丁寧な口調で言った。
「は、はい」
と琴絵は返事した。そこに彼女の母親が、
「仁君はえらいわねぇ」
と顔を出して、彼にコップ一杯のお冷やを渡した。
「ありがとうございます」
彼は頭を下げ、そして戻っていってしまった。
琴絵は呼び止めたかったが、どうやって話しかければいいのかわからず、そのまま見送るしかなかった。
しかし、その夜、琴絵が夜中に目を覚まして台所にジュースを飲みに下りていったら、庭に仁が一人、夜空を見上げて立ちつくしていた。
季節は冬であり、外はひどく寒いはずなのに、彼は用意してもらったパジャマ姿であった。
その表情はひどく悲しげだった。いつもすましている顔しか見たことがなかったので、琴絵は戸惑った。
彼が何を考えているのか知りたかったが、なんだか自分にはわからないむずかしいことのようにも思えて、どうしていいのかわからなかった。
しばらく立っていると、やがて彼が彼女の方を振り向いた。
「あ…!」
思わず声を上げると、彼は彼女にちょっと頭を下げた。
そして彼女の方にやってきた。
琴絵はあわてて、鍵のかかっていたアルミサッシを開けた。
「な、なにをしてたんですか?」
琴絵が口を開けると、白い息がほうっ、と広がった。
「ごめんね、おどかすつもりはなかったんだ。ただ雪でも降らないかな、と思って」
「雪?」
「うん。降りそうだと思ったんだけどな……」
「雪、好きなんですか?」
「まあね。ちょっと子供っぽいけどね」
彼はにっこりと笑った。
「寒くないんですか?」
訊いてから、琴絵はなんて間の抜けた質問だ、と後悔した。でも彼は嫌な顔ひとつせず、
「そうだね。寒いね。そろそろ戻ろうと思っていたんだ」
とさわやかに言い、彼女にそれじゃ、と会釈してその場から離れていってしまった。
琴絵はぼんやりと彼の後ろ姿を見送るだけだった。
このときの彼と琴絵は親戚でしかなく、それ以上の接点はまるでなかったのだ。
そしてまた、彼女と仁の間には何もなく、会うこともなく月日が過ぎていった。
(……でも)
琴絵は、パーク建設予定地の中でも、特に目を引く〝ザ・ラダー〟という名前が付けられるはずだった螺旋型のタワーの前で立ち止まって、そしてあの日の少年だった頃の飛鳥井仁がしていたように空を見上げた。
無論、雪など降るわけもない。今はもう四月なのだ。
(でも……あの、仁にいさんのお父さんの、あの不幸があって……)
死因は、今に至るも不明だ。
彼が街を歩いていると、突然血を吐いて、そして倒れたというのである。まるでなにか毒でも盛られたのではないか、と警察が疑ったほどの、それは唐突な死に方だった。
しかしそれらしい痕跡はなかったというし、何よりそのお父さんは、その直前にどこにでもあるファミリーレストランでランチを食べていたという証言もあって、毒殺の線は消えた。レストランやその関係者と彼にはなんの関係もなかったのだ。
それで、飛鳥井仁は天涯孤独の身の上になった。
助けてあげよう、と琴絵は言ったし、彼女の母親も「養子にしてもいいんじゃない?」と言ったのだが、父親は入り婿の身で兄の子を迎えるのは対外的にまずいと言いだし、そしてなによりも飛鳥井仁本人が「お気遣いなく」と言って辞退してしまったのだ。
仁の父親の商売は人手に渡り、遺産もいろいろな債務やらなにやらでろくに残らなかったというが、仁はさっさと美大に特待奨学生として入学してしまい、生活費も予備校の講師の口を見つけたりして、実に手際がよかった。
実は琴絵は、半分はほっとしていた。
養子になってしまったら、彼女と仁は兄妹である。そうなったら……まあ、半分は夢であるが、従兄妹のままならその可能性が残ってはいるのだ。
しかし、飛鳥井仁はやっぱり、うまい具合に立ち回っているようでいて、どこかあの夜空を見上げていた悲しげな少年のままであった。琴絵にはそう見えた。
何かを耐えている。それもすごく長い間ずっとずっと──。
(それなのに……)
最近の仁はおかしい。
夜中にうろつきまわったり、時々服に血の痕らしきものをつけて帰ってきたり……それより何より、妙に明るいのだ。
もともと如才ない人であった。誰にでもそつなく接し、人に好感を持たれる人であった。それは変わらない。変わらないのだが……
そんな彼女の悩みを聞いてくれたのは、今のところ同じ学校の末真和子だけだ。友達というほどのつきあいはないのだが、親切に話を聞いてくれて「ちょっと任せてくれない?」とまで言ってくれた。
彼女が「わたしがはっきりさせるから、それまであの人にはできるだけ近づかないように」と電話をかけてきたので、琴絵は仁に最近は会っていない。
末真和子は信用できそうだし、少なくとも琴絵が自分でどうにかしようとするよりも遙かに適切な判断をしてくれるだろう。でも、やはり……彼に会えないのは寂しい。
「仁にいさん……」
彼女は赤い空を見上げて、ぽつりと呟いた。
そのときである。
「──それがおまえのオトコの名前か?」
背後から、いきなり声をかけられた。
びっくりして振り返ろうとした彼女の頭部を、目にも留まらぬ速さで伸びてきた電撃怪人の両手が挟んでいた。
ばしっ、と脳の機能が強引に断ち切られる感覚とともに──
「…………ッ?!」
──衣川琴絵は意識を失った。
*
「──名前は衣川琴絵。年齢は十七歳か」
スプーキーEは手に入れた獲物のポケットを探って、少女の学生証を見つけた。深陽学園のものだ。
「なるほど、それでマスターキーか」
と呟いた怪人の視線の先には、パークに立てられた看板がある。そこには〈衣川興業〉という名が記されていた。
「お嬢様ってわけか……」
スプーキーEは、少女が目覚めていたらぞっとすること間違いなしの、唇の端が耳にまで裂けようかという邪悪な笑みを浮かべた。それでも丸くて大きな眼はちっとも細くならない。奇怪な笑みであった。
「なら、金には困らんだろうな。ちょうどいい。コイツを軸にして〝イマジネーター〟とやらを探るとしよう……」
怪人は指先をべろべろと舐め上げて、きれいにトリートメントされた琴絵の髪の毛を、唾液でべったりと汚れた手で乱暴にわしづかみにした。
*
……気がつくと、衣川琴絵は夜の街を歩いている自分を発見した。我に返った。
「…………」
しかし、彼女に自分がそれまで何をしていたのか、という疑問は湧かない。彼女は驚きや戸惑いを感じなくなっていた。
「…………」
街は、一日の緊張から解放された人々の群でにぎわっている。酒場では早くも気炎を上げるおじさんがいるし、喫茶店では待ち合わせていた恋人たちがうれしそうに喋っていたりする。
彼女は、そんな平和な世界を横目にキャッシュディスペンサー機の設置所に入ると、金をおろしはじめた。月の頭なので、利用者は彼女の他にはいない。
一度に三十万までおろせるその機械を、彼女はフルで十回使った。全部で三百万である。
顔色一つ変えずに、札束を通学カバンの中にしまい込む。
そして彼女はそのまま場末のライヴハウスへと向かった。