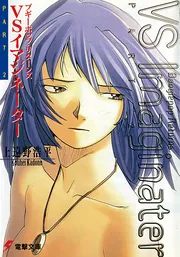ブギーポップ・リターンズ VSイマジネーターPart2
Ⅰ ②
(……あいつは〝マンティコア〟と言っていた。あの逃亡体はたしか〝タルカス〟の担当だったはずだ。それを、もうヤツは仕留めてしまったらしい……だが〝
彼は屋上に置かれている七本のボンベを睨みつけるように見つめる。
それらは各種資材が放置されたままの屋上でそれほど目立つものではない。だから、これが他の者の目に触れたとしても、後からここに運び込まれた物だとは気がつかないだろう。だが、そのボンベの中には、この近隣の人間すべてを〝消毒〟──すなわち抹殺するだけの〝死〟がつまっているのだ。
(いざとなったらコイツを使ってでも仕留めてやる!)
また耳の痕から血が吹き出す。彼はそれを手で押さえながら「だが──」と呟いた。
「だが、ヤツの言っていたもう一つの名……〝イマジネーター〟とは、一体なんだ?」
しばらく憮然とした顔でいたスプーキーEは、突然顔つきを厳しくして下界の方へ振り向いた。
「……む」
パークの入り口の、閉鎖されたゲートに一人の人間がやってきていた。
女──それも少女だ。学校帰りの女子高生らしく、制服姿だ。
そいつはゲートをいじっていたが、驚いたことにがちゃり、と鍵を開けてしまった。合鍵を持っていたらしい。
「……ふふん?」
スプーキーEは、パークの中に入ってきた少女を意味ありげな微笑とともに見つめた。
*
「
「なにやってんかしら、私って……」
通学鞄からいつも持ち歩いている兎のキャラクター絵入りカットバンドを取り出して傷口に巻く。
ひどく幼稚な感じがした。自分が三歳児にでもなったような気分だった。
彼女がこのペイズリー・パーク建設予定地の鍵を持っていることは誰にも内緒だ。この土地の権利にからむ無数の債権の一つを彼女の親の会社が持っているのであるが、父親がそのマスターキーを自宅に持ち帰ったとき、琴絵はそれをこっそり持ち出して合鍵を取ったのである。
それ以来、彼女はひどく落ち込んだりしたときなど、一人でこの秘密の場所にやってくるようになった。
造りかけで放置された、様々なオブジェと言うべき建造物を眺めながら、綺麗なタイルが敷かれるのを待つばかりの、曲線を描いた遊歩道を歩いていると、なんだか涙が出てきそうな気がするのだった。
とても寂しいところだし、学校でも家でも明るい娘だと思われている彼女ではあったが、何故かこういう荒涼とした、見捨てられたような感じのする場所とかが心にしみるのだった。誰にも言ったことはないが。
自分は、ほんとうはこういう場所にいるのがふさわしい人間なのではないか、という気がするのだ。
心の何かが決定的に欠けていて、そこに隙間風が吹いている、そんな気がするのだ。
それはちょうど、この一見華やかなアミューズメントパークが造られようとしていた場所のように、今さら誰一人として見向きもしないような他愛ない夢を──そこからしか始められない何かを、他の人間なら誰でも幼い頃に、とっくの昔に卒業してしまって忘れてしまったような夢を──それを、自分は一度として持てなかったのではないか……そんな風に思うのだ。
そこまではっきりと、この十七歳の少女が意識化しているわけではなく、ただぼんやりとそんな感覚を持っているだけだったが、その分そのせつなさはまるで解消されずに放ったらかしにされたままである。
彼女はとぼとぼと夕暮れの朱に染まったこの廃墟を歩く。
歩きながら、最近はそのことばかり考えていることを、やっぱり考えている。
従兄妹の
(仁にいさん……)
彼女が飛鳥井仁とはじめて出会ったのは五歳のときだった。今でもはっきりと思い出せる。
仁の父親が、彼の弟である琴絵の父に借金を申し込みに来たとき、仁も何故か一緒にいたのだ。このとき、彼はまだ小学生だったはずだ。
そのときは遠くから見ただけだった。
琴絵の父親は
それでも執拗にねばっていた兄に、彼の息子は静かに言ったのだ。
「おじさんの言うとおりだよ、父さん。なんの考えもなく、ただお金を欲しがっても誰もくれやしないよ」
その透き通ったボーイソプラノが祖父の趣味でけばけばしく飾られていた応接間に響いたとき、琴絵はなんだか、その少年が、自分を、不足はないが息苦しい生活からどこかに連れていってくれるような気がしたのだ。
父は驚いたが、その兄は息子の意見に「あ、ああ……そうだな」と納得し、さっきの、ただ兄弟だからいいだろうといった頼み方から、自分がやろうとしている商売の計画を説明し始めた。
……その辺から琴絵にはよくわからなくなったのだが、どうやら彼女の父は仁の父親に結局いくらか貸してやったらしい。琴絵が覚えているのは、その親子が帰るとき、父親よりも息子の方が遙かに立派に「お邪魔しました」と玄関で別れの言葉を言ったことであった。
すごく凜々しく見えたのだ。
初恋だった。
そして今度はいつ会えるのかと楽しみにしていたのだが、仁の父親はどうやらその借金して始めた商売に失敗してしまったらしい。それっきり、琴絵の家に来ることはなかった。時々彼女の父が兄のことを「あのごくつぶしが…!」などと罵っているのを聞いて、琴絵はすごく悲しくなったことを覚えている。
琴絵がふたたび仁と会うのは、それから四年後のことであった。
衣川家に、またあの親子がやってきたのだ。父親は立派な身なりをして、驚いたことに借金を返すという。しかも利息を計上した上で。
琴絵の父は「本来なら違約金ももらわなきゃならんのだが……」などとも言ったが、それでも金を返してもらえたことには喜んだようであった。
「しかし、一体どうやって稼いだんだ?」
と聞かれても、仁の父親はニヤリと笑うだけであった。
中学生になって、学生服を着ている息子は彼らの横で神妙な顔をしている。大人たちの会話に退屈しているという様子はなく、かといってよけいな好奇心を持っているというわけでもない。
馴染んでいた。それが陰からこっそりと見ている琴絵には、とても不思議に思えた。
「それより幸二、おまえ絵はいらないか?」
「絵?」
「一流の名画さ。いま俺、そういうものを扱う商売をしてるんだ」
「画商だって? 図工の成績が2だった兄さんが? 偽物つかまされてもわからないんじゃないのか?」
「まあ、その辺のことはこいつに任せているのさ」
と言って、息子の方を見る。
「こいつは天才だよ。もう絵の賞をいくつも獲っている」
「ほんとうか? しかし……」
「こいつの目利きは大したものなんだよ。どうでもいい安値で仕入れた物が、一年後にその画家が急に人気が出て十倍の値で売れたことがある」
誇らしげに言った。
誉められても、息子の方は相変わらず神妙な顔だ。
「ほお……? なんだ、将来はピカソのような画家にでもなりたいのか、仁は」
琴絵の父は、はじめて甥の方に注意を向けた。
「夢ですね」
少年は、決して偉ぶらずに、静かに言った。その態度はその場にいる誰よりもしっかりしている、と琴絵は思った。
その場の人間が何を考えているのか全部知っていて、それに合わせているような、そんな感じさえした。余裕とさえ感じさせないほどの余裕──