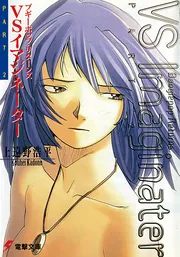ブギーポップ・リターンズ VSイマジネーターPart2
Ⅰ ①
市中から少し離れたその山はきれいに整地が入っており、傾斜にはあちこちに階段がついてさえいる。だが、その広々とした空間に人影はない。土がむき出しで、あちこちに冬を越えてきた茶色の雑草が茂っているくらいで、生物の影もない。もう少し経てばいろいろな草が生えて、逆にうっとうしいぐらいの景観になるのだろうが、今はまだ寂しいだけだ。組み立てられないまま放置された鉄骨や各種資材、そして建設途中で放り出されたままのタワーなどがむなしく聳えていたりする。
この山にアミューズメントパークが造られる計画が立てられてからすでに五年になり、山の整地がすんでからも三年になるが、本社の方でごたごたを起こした某アミューズメント産業は、結局この土地を銀行の担保に入れて、しかし銀行の方も競売にかけようにも買い手のいない中途半端な土地を持て余し、アミューズメントパークの計画を凍結状態にし、そのままどうにかなる日をあてもなくただ茫然と待っている。
土地は高い柵で囲まれており、夕暮れともなるとそれが地面に縞模様の長い影をつくっている。
──その上に、丸くて大きな影が一つ落ちたかと思うと、柵の内側にほとんど球体のようなシルエットの人影が降り立った。二メートル半もある柵を飛び越えたそいつの、白髪混じりの長髪が舞い上がって右耳のちぎれた痕が露になる。
スプーキーEである。その左手には、中身の詰まったコンビニのビニール袋を下げている。
「……ちっ」
かすかに舌打ちしながら、神経質そうに髪を戻す。
そして髪の上からバリバリと傷跡を掻きむしる。血がにじみ出し、髪の毛をべったりと汚すがスプーキーEは意にも介さず、爪を立てて掻き続ける。すでに耳を切断されてから一月近く経つのだが、こうやって掻いているせいで一向に傷がふさがらない。合成人間である彼は、傷の再生に関しては常人よりも遙かに早いのだが、それでも追いつかないほどしょっちゅう掻いている。
指先を小刻みに動かしながら、彼はアミューズメントパーク建設予定地の奥の方へと入っていく。
空に向かって螺旋を描くような、奇妙な形をしたタワーのところまで来た。
その入り口は固く閉められていて、鍵だけでなくチェーンが何重にも渡してある。
「…………」
スプーキーEはその厳重なロックには目もくれず、一歩小さく後ろに下がった。
そして柵を飛び越したときのようにジャンプして、タワー三階の、ガラスをはめ込まれていない素通しの窓から中に入った。
床の上は土埃や、風で飛んできたゴミなどが散乱している。それらを蹴散らかしながらスプーキーEは乱暴な足取りで進み、タワーの階段を上っていった。エレベーターはまだシャフトだけで中身が入れられていないのだ。もっとも電力が来ていないのだから付いていたとしても動かない。
最上階まで来た。ここだけは窓ガラスが填っている。どうやら上の方から付けていくはずだったらしい。
「…………」
スプーキーEはやっと耳の痕を掻くのをやめると、だだっ広いフロアーの真ん中に腰を下ろして、コンビニのビニール袋からおにぎりやらサンドイッチなどを取り出して、むしゃむしゃ食べ始めた。
ふと思いついたような動作で腰のベルトから携帯電話を一つ抜き取ると、異様に素早い手つきで十桁の数字を一秒かからず叩いた。
コールはほとんどなく、すぐに相手は受話器に出る。少女の声だ。
『──はい、
「指令七〇〇二五九」
スプーキーEは口の中でハムサンドをくちゃくちゃ噛みながら言った。
『了解。指令を受諾します。──態勢完了。内容をどうぞ』
声は急に機械的なものに変わった。
「これから市立図書館に行き、ハングル辞典とハンガリー語慣用句辞典の間に隠してあるキーをゲットしてこい」
『了解』
「キーは駅のコインロッカーのものだ。そこに入っている薬品を、おまえが勤めているバイト先のファーストフード店のドリンクに混入しろ。一錠につき、約三リットルを目安にしろ」
『了解』
「以上だ。指令七〇〇二五九伝達終了」
『了解。伝達終了。ただちに指示を実行に移します』
スプーキーEは電話を切る。
そしてベルトに戻すと、すぐに別の携帯電話を手に取り、またどこかへとキーを叩く。
『──誰だよ?』
今度は不機嫌そうな少年の声だった。それが、
「指令五四〇〇一二九」
とスプーキーEが囁くと、とたんに、
『了解』
とさっきの少女と同じような機械的な声に変わる。
「現在、おまえのチームのメンバーは何名だ?」
『七名です』
「足りんな。十二名に増やせ。今週中にだ」
『了解。方法は?』
「どうにでもしろ。脅してでも無理矢理にでも、とにかく人数を集めろ」
『了解』
「十二名になったら、六番街から八番街にかけて、すこし荒っぽく動け。そしてどんなヤツが刃向かってきたかを報告しろ」
『了解』
……ここでの〝動く〟という単語は、恐喝や窃盗といった暴行行為のことを意味している。
そして話している途中で、スプーキーEの腰の携帯電話の一つが振動で着信を告げた。
スプーキーEはあわてることなく、いまの少年との対話──指令を伝えるのを続けた。やがて、
「以上だ。指令五四〇〇一二九伝達終了」
『了解』
とそれを終えると、おもむろに着信電話に出る。
「──なんだ?」
『FS四五〇〇三六より定期報告』
その声はどうやら二十代後半あたりの成人女性らしい。やはりこれも表情というものがまるでない機械的な声だ。
「順調か?」
『仕込んだクリームのうち、七十パーセントが売れました。買った客の七割は再来店していますが、目立った変化は見られません』
「細かいデータをいつものところに送信しておけ。それと、仕込んだ客には第二レベルの投与を始めろ。効果があろうとなかろうとだ」
『了解』
……スプーキーEはこのように、誰もいない忘れられた場所でひとりコンビニのジャンクフードを囓りながら、街中に潜ませている洗脳処置をした〝端末〟たちに指示を出し続けている。電話をかけ続け、そして彼のところにも電話がかかり続けて終わるということがない。いったいどれくらいの数の相手がいるのか、ちょっと考えられないほどの量だ。それはさながら人気アーティストのライヴチケットの予約を受け付けるダフ屋、といった感じであった。
それらはまとめると〝薬物を投与する側〟とその結果の〝人々の反応を見る側〟の二つに大別できる。
だがその中には、そういうことは全然関係ないものも混じっている。
『……高速道路の高架下に〝出る〟そうです』
『……川沿いの道路を走っていくのを見たという者がいます』
『……ツイン・シティの屋上に、それらしい影を見たという噂が』
──そういうことを言う者たちが。
それらをスプーキーEはむっつりした顔で受ける。特に最後のヤツなどには「わかっている!」などと大声を張り上げる始末だった。
「──くそっ!」
電話のやりとりが一段落つくと、スプーキーEは忌々しげに呻いた。
「おのれ、ブギーポップめ……!」
ぎりぎりと歯軋りしていると、りきんだせいか耳の痕から血がぶしっ、と吹き出した。
ビニール袋に手を突っ込むが、もう何も残っておらず袋はむなしくがさがさと音を立てるだけだ。
「くそったれが!」
彼は袋を破り捨てた。
そのゴミを放り捨てると、乱暴な足音を響かせながらタワーの屋上へと上がっていく。
(ゆるせん、あいつは必ずこの俺の手でバラバラに引き裂いてくれる……!)
屋上には、彼があの〝敵〟と遭遇したときのような強い風が吹いていた。