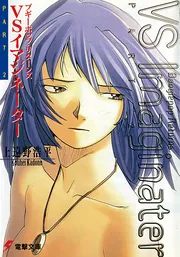Introduction
『人は誰かを呪うとき、心の中に死神を呼び寄せている。その死神は影となり、いずれ己の心を喰らい破る牙となって……』
──
「呪いに掛けられてる、末真さんはそんな風に感じたことない?」
「え? い、いやそれは……いいえ。そんなことはない、と思うけど」
「私はあるわ。それもしょっちゅうね。自分がなかなかうまくいかないのは、呪いのせいなんだろうなあ、って思ってる」
「水乃星さんが? かなり意外だけど」
「私みたいに、いつもニコニコ笑ってるような女の子が、そんな気味の悪いことを考えているのはイメージに合わない、かな?」
「そうじゃなくて……水乃星さんって、みんなの人気者だし。言ってはなんだけど、あなたがうまくいっていないんだったら、世の中のほとんどの人はどうなんだろ、って感じちゃうよね」
「ああ、それはそうでしょう。みんながみんな、どこかしら、なにかしらうまくいっていない。違うかしら?」
「まあ……それを言ったら」
「あなた、そういうこと考えるのが好きでしょ、末真博士。みんなの様子を観察して、どうしてだろうって分析するのが」
言われて、末真は苦笑しながら、
「……その呼ばれ方、好きじゃないんだけど──でも、否定はできないかもね」
「霧間誠一の本とか好きでしょう、あなたなら」
「……それも否定できないな。でも、この学校にわたし以外に霧間誠一を読んでる人がいるとは思わなかったわ。それこそ意外」
末真がそう言うと、透子は、うふふっ、と笑って、
「あなた、いつかそのことを不思議がることになるわ。ええ、きっと不思議がる──」
「? どういう意味?」
きょとんとする末真に、透子は視線を空に向けながら、
「呪いの話よ。それこそ意味がわからなくって、私は困っているって話。不思議なのよ、ほんとうに」
「なにか思い当たるふしでもあるの?」
「あなたは? その気配を感じたことはない? 自分を取り巻いている嫌な感触のことを。ちょっとなにか思い切ったことをしようかな、って考えても、すぐに駄目な理由をたくさん思いついちゃって、やっぱやめよう、ってなること、ない?」
「──あるけど。それが呪いなの?」
「じゃあ、なんなのかしら」
「いや、だからそれは世間体が悪くなるからとか、人に陰口たたかれるのを気にしてるだけで──いや、そうね」
末真はため息をついて、首を横に振って、
「なんでその人たちは、そんな悪口を言うのか、って説明にならないね。みんながそういうことを気にしてるから、息苦しくなる。で──その大本がなんなのか、わたしたちは全然わかっていない、と。それはもう、呪いに掛けられているのと同じじゃないか、って──そう言えなくもないね」
「さすが末真さん。理解が早いわ。みんなの心の中にある偏見とか諦めとか憎悪とか、いったいどこから来ているの? 最初にそれを始めた人なんて、もうこの世にはとっくにいないでしょうに。亡霊が決めたことに従って、その中でモノを考えて、優劣を競って、恋をしたり殺し合ったりしてる。これが呪いでなくて、なんなのかしら?」
「うーん──だとしたら、すっごく範囲が広くなっちゃうね、確かに。世界中ぜんぶが呪われてる、みたいになるね」
「いつのまにか、知らないうちにその呪いは完成しているのよ。私たちの心の中で。いつ、それをすり込まれたのかも覚えていない呪いに縛られて、馬鹿みたいに自分が上だ、あいつが下だってケンカし続けている。くだらないって思わない?」
「それはそうだけど、でも──その呪いって解けないのかな」
「私は難しいって思う。末真さんは? あなたには呪いの解き方がわかるかしら?」
「とんでもない難問だけど──それをあきらめちゃうのも、呪いなんでしょ」
「そう、その通り──さすが博士」
「だからやめてって──でも水乃星さんも、難しいって言うけど、無理だとは言わないんだね」
「うふふっ──」
二人がそうして話し合っていると、陰の方から一人の少女が近づいてきて、
「あ、あのう──その呪いの話って、私にはよくわからないんだけど……どうすれば意識できるようになるかな?」
と訊いてきた。これに透子は、
「ああ、
と素っ気なく突き放した。末真が眼を丸くして、
「い、いや水乃星さん。そんなことないでしょ。彼女だってちょっと話が気になっただけで──ごめんね、臼杵さん」
「────」
少女は顔を青ざめさせている。そこに透子はさらに、
「あなたはもう手遅れ──呪いは完成してしまっている。できることと言ったらせいぜい、死神に見つからないように気をつけるくらい……」
と宣告した。
……水乃星透子が学校の屋上から投身自殺をしたのは、この会話から二ヶ月後のことであり、その原因については遺書などが発見されなかったことから、ずっと謎のままである。一部ではそれを、呪いのせいだと囁く者もいる。
学校に巣くう死神〝ブギーポップ〟の呪いだと──。