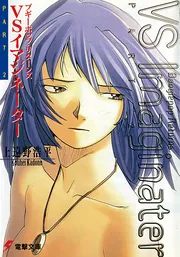死神は機嫌が悪い "Blue 'n' Boogie" ①
*
私の通う県立深陽学園は、呪われている──と、もっぱらの噂だ。
去年は生徒から飛び降り自殺が出たり、今年に入ってからも何人も行方不明になったりしていて、かなり洒落になっていない。だからって、そこに通っている生徒の私たちが、それを気に病んでいるかどうかと言えば、正直、そんなでもないわけで。
「梨杏、あんた
「ちょっといい気になってるよね」
「でしょ? やっぱそーだよね、あの娘、なんか周りが見えてないよねー」
「自慢の彼氏に夢中なんでしょ」
「その彼氏の評判が悪いってのに、ねー」
こんな風に友達と軽口を叩き合って、普通にやってることの方が多い。呪われてるかも、なんてびくびくしていたら何にもできないし。ただ──
「でもさ……ねえ、最近おかしいって思わない?」
「そうかな」
「昨日だって、一年のクラスで暴れる奴が出たっていうし」
「あー、なんか多いよね、最近。みんなストレス溜まってんじゃない?」
「それにしても多すぎるよ、子供のケンカとか呑気な感じじゃないよ。マスコミに言ったら大騒ぎになるんじゃない?」
このところ、うちの学校では暴力沙汰が目立つ。一年生が三年生を殴ったり、生徒がガラスを割ったり、先生同士が掴み合いしてたって目撃情報もある。しかし、校内が荒れてるってほどでもない。
「でも、その場だけでしょ。暴れ出した奴もすぐに注意されて、おとなしくなるし。停学処分になったのなんて、それこそ炎の魔女くらいでしょ」
「いや、霧間
「うちでわかりやすい不良なんて、あいつくらいでしょ。あいつって裏で何してるかわかったもんじゃないし」
「いや、あの人は不良っていうか……うーん。ごめん、なんか変な話しちゃったね」
「ううん、別に。でも気をつけなきゃね。変なトラブルに巻き込まれて怪我とかしたら馬鹿みたいだし」
「気をつけてればいいのかな……」
私たちが教室の隅で、そんな風にこそこそ話していたら、急に横から、
「いや、気をつけるだけじゃ駄目だね」
と男子の声が割って入ってきた。
え、と振り向くと、そこには悪い意味での有名人が立っていた。
(うわ、
私たちはきっと顔をしかめていたに違いない。しかし生成はそんなことにはお構いなしで、
「呪いには単なる根性論では対抗できない。気合いではどうにもならない。しっかりとした対策が必要だ」
急に真面目に、したり顔で訳のわからない説教をしてくる。私たちは困ってしまうが、生成は一人でうなずいて、
「まあ、それでも気をつけないよりはマシだから、君たちは他の奴らよりは意識が高いよ。でも忘れるなよ? 呪いはいつだって、すぐ近くに迫ってるってことを」
「はあ……」
「何かあったら、僕を頼ってくれていいからな。いつでも相談に乗るよ」
偉そうに言って、そして去って行った。
私たちは思わず、顔を見合わせてしまう。
「……あいつ、なんなの?」
「なんか勘違いしてるよね。家が金持ちだからって、調子乗ってるよね」
「陰じゃ〝お祓いさん〟って呼ばれてんだよね。なんでも呪いのせいにして、自分はそれを解消できるって言ってるって噂、本当だったんだね……さすがにビビったよ」
「うちの学校が呪われてるってのも、あいつが言いふらしてるだけじゃない? きっとそうだよ」
「うん……かもね。そんな気がしてきたよ」
「そういや知ってる? こないだ突然転校した
「えーっ、なにそれ?」
「いや、見た奴がいるんだって。二人でこそこそ話してたところを。で、百合原が学校に来なくなったと思ったら、転校しましたって事後報告でしょ。その一年も今、行方不明で。そっちは親が捜してるらしいけど。百合原の方は実家ごと引っ越しちゃって、うやむや。世間体が悪いんで逃げたんじゃないか、って話よ」
「えーっ……だって百合原って学年一位の優等生だったじゃない。それなのに」
「だからストレス溜まってたんでしょ。思い込みすぎると色々と面倒で……」
私が喋っている途中で、目の前の相手の顔が急に渋いものになった。ん、と思って、後ろを振り向くと、今度は風紀委員長が立っていた。
彼女はその小さな身体で、腰に手を当てて、こっちを睨みつけてくる。
「げ、
私は思わず声を上げた。
「南野さん──ちょっといい?」
彼女はくい、と顎をしゃくってみせた。
新刻敬は学校一背が低い。実際、街でしょっちゅう小学生に間違われるそうだ。しかしうちの高校で彼女に舐めた態度をとれる者はいないだろう。
「南野さん、ああいうの良くないよ」
新刻の声もまた子供みたいに可愛らしいのだが、そこに籠もっているドスの利き方がまた、半端ない。
「いや、別に深い意味はなくて」
彼女に連れ出されて、廊下の端っこで説教されながら、私は唇を尖らせていた。新刻は容赦なく、
「百合原さんや
責め立ててくる。私はちょっとイラついて、
「大したことじゃないでしょ。みんなやってるでしょ。それに、あんたにそういうことを告げ口してる奴だって、私の悪口を言ってるんだから、おあいこじゃないの?」
と反論した。すると新刻は眉をひそめて、
「そういう考え方って悲しくならない?」
と言った。私はさらにムカついて、
「なによ、そういうあんたは何なのよ。風紀委員長とか今時、馬鹿馬鹿しいって思わない? 管理なんてホントは教師が全部やってて、うちの高校ぐらいでしょ、風紀委員なんてあるのは。生徒の自主性に任せてますとかいうポーズだけじゃん、結局。それであんたみたいに真面目な奴が利用されてるだけでしょ。入試のときの役になんか立たないよ、その肩書きは。だって他の高校にないんだもの。比べようがないでしょ──」
と、一気に文句をまくし立ててやった。なんか本気で腹が立っていた。しかし新刻は言われても、特に怒りも泣きも驚きもせず、静かに、
「だから──そういうところよ」
と諭すように言う。
「南野さん、頭が良いから、周りの人間が馬鹿に見えて、その欠点を指摘したくなるんだろうけど、でもだからって、それを振りかざしても、その場では他人の上に立ったみたいに思うかも知れないけど、でも──」
「うるさいなあ。ほっといてよ。私が暴力沙汰を起こしてるわけでもないじゃんか」
「そう──それよ。それが問題なのよ。あなたは問題ないって思ってるけど、他の人がどう思うかわからないでしょ?」
「なにそれ? 私が襲われるっていうの?」
「その危険もあるってこと。無駄に敵を作るような真似はしない方がいい」
「あんたはどうなのよ。それ言ったらあんたの方がずっと危ないでしょ」
私が言い返しても、新刻は何も言い返さずに、
「…………」
と私の方を見つめてくるだけだ。
(なによ──覚悟はできてる、とかいうつもりなの、こいつ?)
私はちょっと気圧されて、口ごもってしまって、彼女の視線から目をそらし、何気なく窓の外を見た。
そこで……固まった。
(え──?)
校庭の隅っこに、黒っぽい塊が生えていた。筒のような影で、にゅうっ、と地面から伸びているように見える。
それはどうやら黒い帽子をかぶって、全身をマントで包んだ人間らしかった。妙に白い顔をしていて、唇には暗い色のルージュが引かれていて、そして──それは、
「……宮下
うちのクラスの同級生だった。そうとしか見えない。
「え?」
私の呟きを聞いて、新刻も校庭を見た。そして彼女は「うわ」と呻いて、慌てた様子で、
「ち、ちょっとごめん──」
と、いきなり話を切り上げて、階段を駆け下りてどこかに行ってしまった。
「────」
私は立ちすくんで、そして校庭に視線を戻したが、そこにはもうあの黒帽子の影はなかった。跡形もなく失せていた。