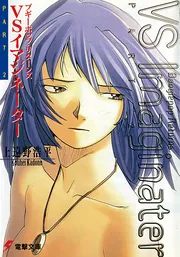死神は機嫌が悪い "Blue 'n' Boogie" ②
*
結局、午後の授業が始まっても宮下藤花は戻ってこなかった。
放課後になって、皆が帰り始めてからも、私はぼーっとしてしまって、席から立てなかった。
「──でさあ」
「──じゃない?」
「やだあ──」
同じように居残ってる女子たちは、なにやら楽しそうに噂話をしている。とりとめのない、他愛ない話らしかったが──その中でひとつの単語が耳に引っかかってきた。
「──だからさ、ブギーポップなんじゃないの?」
その名が聞こえてきた瞬間、私は思わず振り返っていた。
「──え?」
私が急に割って入っても、相手はいつも与太話をしている関係なので、別に反発もせず、すぐに、
「いや、そう思わない? 最近うちの学校が呪われてるとかさ、あれってブギーポップの仕業じゃないかって」
「ブギーポップ──」
私が茫然と呟く間も、他の女子たちは話を続ける。
「どーだろ、私はブギーポップって美少年であってほしいんだけど」
「そりゃあんたの好みだろ」
「でもさあ〝そのひとの一番美しいときに殺す〟って設定は、本人が美しくないと成立しないって」
「設定とかゆーなよ、白けるでしょ」
「決まり事は大事でしょ。それ無視したら社会が成り立たない!」
「社会! 大きく出るねー」
きゃはははは、と彼女たちは陽気にけらけらと笑う。話は脈略なく、あっちこっちに転がっていく。
そこに男子がふたり、教室を覗き込んできて、
「あのう──臼杵さん見なかった?」
と声を掛けてきた。とたんに女子たちはぴたりと黙り、二人を睨みつけて、
「知らねーよ。こっちは用はねーよ」
「上下コンビはお外で遊んでな」
と冷たく言い放った。すると二人は顔を見合わせて、
「上下……?」
と首をかしげると、女子たちは笑い出して、
「
「あはは、言えてる! 上下コンビだよ、あんたらは」
と囃したてた。二人は渋い顔になって、
「上下……」
とか唸りつつも、扉から顔を引っ込めて、廊下に去って行った。
女子たちも顔を寄せ合って、ひそひそ声で、
「いやあ、やばかったね」
「男子にブギーポップの話をしちゃいけない、ってのも、設定だからね」
「だから白けるって──でも、破ったらどうなるのかな」
「それこそ、呪われる──じゃないの?」
「うう、なんか本気で寒気がしてきたんだけど──」
決まり事──とはいうが、このブギーポップにまつわる話が、どこから高校生の女子たちに広まったのか、当然ながら私にはわからない。
ただ、そういう噂がある、という環境にいつの間にか入っていた。
それは死神の噂話だ。都市伝説、とも言えるだろうか。
人が、他の誰よりも真剣に生きて、誰よりも充実した瞬間に至って、誰よりも美しい存在になったときに、それはどこからともなく現れるのだという。
そして苦痛も自覚もないうちに、一瞬でその相手の生命を刈り取ってしまう死神──それがブギーポップ。
そして私の中で、どういうわけかそのイメージが、さっき見たあの宮下藤花の奇妙な格好と重なっていた。
(あれが、ブギーポップ──?)
なんでそんな風に思うのか。あれはただ単に変なコスプレをしていただけじゃないのか、それこそデザイナー志望とかいう彼氏と一緒にふざけてるだけじゃないのか……とも思うのだが、しかし──そんな気がして仕方がないのだった。
その日はいつも一緒に帰っている友達が早退してしまっていたので、一人で下校することになった。深陽学園は山の上に建っているので、帰り道は下り坂の道になる。大半の生徒はバスで駅まで行くのだが、私の場合は比較的近所に家があるので、そのまま徒歩で帰ることが多い。
(でも──呪いとか……本当にあるわけないけど……でも──)
さっきの奇妙な黒帽子を目撃したせいで、なんだか不安が心の底にこびりついている。あり得ないはずのことが、あるかも──という気にもなっている。
(呪いのせいだとして──死んじゃった人たちにはどんな責任があるんだろう……そうなっても無理ない、みたいな理由があるのかな……?)
そんなことを考えながら、坂道を下っていく。
風に乗って、何かが聞こえてきた。口笛のような音だった。どこかで聞いたことがある曲で──
(ええと、たしか大昔の曲で──なんつったっけ、なんか地名だったような──)
そうだ。〈ニュルンベルクのマイスタージンガー〉という曲だ。中学の時にやたらとこの曲が校内放送で流れていたことがあって、それで覚えている。なんで今、そんな曲の、それも口笛っぽいアレンジが聞こえてくるんだろう、とは思ったが、学校でなんかやってるんだろう、と大して気にもしなかった。
そうやって歩いていると、曲も聞こえなくなった。静かになった道を、ひとりで進んでいく。
大通りにつながる道まで、あと半分くらいの地点にさしかかった所で、車道の真ん中にかなり大きめの石が転がっているのが目に入った。
(あっ──)
石を踏んだらタイヤがパンクすることがある、という話を聞いたことがあったような──しかしほとんどの場合は、ただ弾き飛ばしてしまうだけだろう。
(うーん──でも……)
この道は事実上、学校へのアクセス専用のようなものなので、車はあまり通らない。バスもさっき通ってしまったから、当分は来ない。
(ええい──)
私は思いきって、車道に出て、その石を拾い上げた。なんだかやたらと尖ったところのある鋭い石で、やっぱり拾っておくべきだった、と変な安心をしたところで──それが見えた。
道路の脇に設置されているカーブミラー──そこに映っていた。
奇妙に歪んだ私の姿……その上に、一本の線が走っている。
真っ赤な線が、ミラーそのものを二つに割るように、大きく横切っている。
その赤い赤い筋が──私の首のところで、胴体から切り離すように、べったりと線が引かれている──
(……あれ?)
私は、動けなくなっていた。
そして、気がついたら手にしている石を、首筋に当てている。
そこはちょうど、鏡の中で赤い線が引かれている位置と一致している。
(え──)
私は、石を握っている手を離そうと思う……しかし、身体が反応しない。
腕が勝手に、石の鋭い切っ先を喉の柔らかい皮膚に押し当ててくる。
(ああ……?)
ぐぐぐっ、とその冷たくて硬い感触が首筋に食い込んできて、そして──熱いものが流れ出す。
血が……
(あああああっ……!)
私は叫びたかった。悲鳴を上げたかった。泣き喚いて感情を表に出したかった。しかし鏡の中の私は、人形のように無表情のまま、己の首を掻き切っていき──
(──え?)
──その背後に、黒い影が立った。それは黒い帽子に白い顔に黒いルージュで──そして、私の襟首を乱暴に掴んで、車道から歩道に引っ張り上げた。
石が、私の手から離れて、かんかんかん、とどこか遠くに転がっていく音が響いた。
どさっ、と私の身体は歩道の地面に放り出された。
「あ、ああ──?」
私は茫然としながら、私を引きずり倒した影を見上げる。
やはり──宮下藤花にしか見えない。しかし、そこに立っているのはどうしたって私のクラスメートではない。
「…………」
黒帽子は、私ではなく、あのカーブミラーの方に目を向けている。私も見たが、そこにはもう、あの赤い線はなくなっていて、普通に綺麗な鏡面が反射できらきら光っているだけだ。
「攻撃に指向性がない──無差別なのか」
そいつは苦虫を噛みつぶしたような口調で呟く。
「あ、あの……あんたは……」
私がおそるおそる呼びかけると、そいつはどこかふて腐れたような様子で、
「ぼくが誰なのか、君はもう知っているみたいだけど」
と言った。