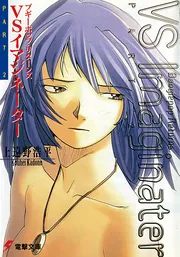死神は機嫌が悪い "Blue 'n' Boogie" ③
*
二重人格、というものがある。それぐらいは私だって知っている。
(しかし、あれは──なんか違う気がする……)
翌朝、宮下藤花は何事もなかったかのように学校に来て、私の斜め前の席に座った。
こっちの方はまったく見もしない。もともと仲良くないし、共通の友人も少ないので、通常通りだ。昨日のことなど、まったく意識にないとしか思えない。
(うーん……)
そう言えば、宮下藤花はいつも大きめのスポルディングのバッグを提げて登校しているが、もしかしてあの中に帽子だのマントだのを入れているのだろうか。別に校則違反の品でもなんでもないので、誰からも文句も言われず、不審にも思われていないが……そういうつもりで見ると、実に怪しい。
「…………」
私が後ろから睨んでいることにも気づかず、授業中の宮下藤花は相変わらずぼーっと気が入らない様子で時々、頭がかくん、かくん、と揺れて居眠りしてるのがバレバレだったりした。
(ううう、やっぱり違いすぎる……)
私は、昨日のことを想い出さずにはいられなかった──。
「も、もしかして、ブギーポップ……?」
私の問いかけに、黒帽子はとぼけているような、呆れているような、なんとも言いがたい左右非対称の顔になって、
「ほら、やっぱり知ってる」
と答えた。私は混乱しつつ、
「い、いやそれは、なんとなくそんな気がしただけで、でも……もしかして、昼休みのときに私が見たの、気づいていたの?」
「君や新刻さんとか、実に目ざといよね。そんなに気づかれたりはしないんだけど」
「いやいや、あんなにあからさまで、気づかないはずがないでしょうが」
「それがそうでもないんだ。人は日常で見慣れた物しか眼に入らないからね。異物は意識から排除されて、それっきり、ということの方が多いんだ」
黒帽子は、歩道にへたり込んでいる私に向かって手をさしのべてきた。私はその手を握り返して、立ち上がる。
がっちりと固定されて、まるで手すりに摑まっているみたいだった。普通の女の子の身体バランスとも思えない。
「……ええと、宮下藤花じゃないの?」
「さあね。別にどうでもいいんじゃないのかな、そんなことは」
「だって……だって絶対に違うでしょ。あんたと、あの……えと」
「クラスで、陰で笑われている間抜けな宮下藤花とは印象が違いすぎる、かな」
「い、いやその──それは」
「君が彼女のことをどう思っているか、それはぼくとは全然関係ないことだからね。どうでもいいよ」
「ええと──今、私を助けてくれたの?」
私がおずおずと切り出すと、黒帽子は素っ気なく、
「それはどうだろう。助けた、と言えるのかな」
「だって、変な風になっていたのを止めてくれて」
「君がどうして、あんな風になっていたのか、その理由をぼくは知らない。だからあれが、助けたことになるかどうかは、まだ確定していない」
「…………」
そう言われて、私の背筋がじわじわと寒くなってきて、ぶるるっ、と震えてしまう。そうだ、私はいったい、何をされたのだろう?
「……の、呪いなの?」
「それもわからない」
「ね、ねえ……あんたじゃないんでしょ、うちの学校の呪いって」
「呪いがなんなのか、そもそもぼくにはそれもわからないね」
「だから……いや、そもそも、あんたはどうして、そんな風になっているの?」
私の問いに、黒帽子はまた左右非対称の表情になって、
「ぼくは自動的だからね。自分でもその由来を認識できないのさ」
と言った。意味がわからない。私が眉をひそめたのを見て、さらに、
「ぼくには主体性はないんだ。ぼくが浮かび上がってくるときは、常に、危機が迫っているときなんだよ。今、この辺りには世界の危機が訪れている」
「せ、世界って……そんな大げさな」
「君にとっての世界と、全人類にとっての世界には差などない。世界は世界で、それはいつだって滅びかけている。崖っぷちにいるんだよ、誰だって」
淡々とした口調で、説得力などまるで考慮せずに、自分勝手な言葉を並べている。私は少しイラッときて、
「ね、ねえ──あんたの正体、つーか、その──とにかく、他人にはあんまり知らせない方がいいんでしょ?」
と言った。言いふらされたら困るだろう、という、後から思ったら実に底の浅い考えでつい、そう言ってしまった。だがこれに黒帽子は、
「別に、ぼくはそれについては何も言えることはないね」
あっさり投げやりに言う。私が絶句している中、さらに、
「そういうことは君たちの間の話で、ぼくはそれに関与できないんだし。それに君がどういう風にぼくと会ったのか、その説明についてもどうにもならないだろうしね」
そう告げられて、私は心臓を掴まれる気分になった。
(そうだ──私は……私は何をしていた……?)
傍から見たら、私のしていたことはただ、車道に出て行って、石を拾って、それで自分の喉を掻き切ろうとしていただけだ。監視カメラがあったとしたら、そこには私がただ情緒不安定で発作的な自殺を図ったとしか思えない映像が残されているだけだ。
「わ、私は……」
「君がどうするとか、それはぼくには関係ないんだ。ぼくはただ、今……迫っている世界の敵を排除するだけだ。自動的に」
黒帽子は私を見つめてくる。私はここで、やっと気がついた。
(そうか……こいつはただ、私を助けたのではなく……私自身が危険な存在なのかどうかを今、見極めようとしているのか……)
「わ、私は──違う、違うからね……!」
「だといいね」
黒帽子はそう言うと、山道を下り始めた。私は後をついて行く。
「ええと──あんたって、正義の味方なの?」
「それは炎の魔女だね」
「は? 霧間凪? なんであの不良が?」
「君も、今の状況に困っていて、助けて欲しいなら、ぼくではなく彼女を頼った方がいいね」
「意味わかんないんだけど──」
「それはそうだ。意味──真にそれを理解している者など、この世には存在しない。皆、その途上にいるだけで、到達した者はおそらく、誰もいない。仮にいたとして──」
黒帽子の、その縁で半分隠れている眼の奥がうっすら光ったように見えて、
「──それを誰にも伝えられず、死んでいる」
と言った。ここで私は、やっとこいつが死神と皆から噂されていることを思い出した。
「…………」
私は、その曖昧な表情から何かを読み取ろうとしてみた。しかし黒帽子の影に覆われて、その白い顔からはなんの感情も読み取れなかった。
ただ、ちょっと不機嫌そうに見えた。
「……あのさ、あの噂はなんなの? ブギーポップの都市伝説は」
「ぼくが広めたわけじゃないけどね」
「じ、じゃあ、その人が一番美しいときに殺すってのは、あれは嘘なのね?」
「さて、それはどうだろうね。美しいかどうか、ぼくにはそんな判断はできないから、嘘とも本当とも言えないだろうね」
「……人は殺すの?」
「世界の敵を滅ぼすのが、ぼくの存在理由だからね」
なんか答えをはぐらかされているというか、私に理解する力がないというか、とにかく空回りしている気がする。決定的な答えを得られない。
(……ううん、どう訊けばいいんだろう……でも)
ブギーポップの秘密はさておき、今の私にはさっきのことが何よりも切実な気がする。
「ね、ねえ──私は狙われているの? それとも巻き込まれただけ?」
「おそらく、どっちの考えも正しいだろう」
「どういうこと?」
「君個人は狙いではないかも知れないが、君はこの〝敵〟の標的には入っている可能性がある。さっきの攻撃が、この道を通る者を襲う罠だとしたら──」
私はぎょっとなる。この山道は、ほとんど通学路としか使用されていないのだから……。