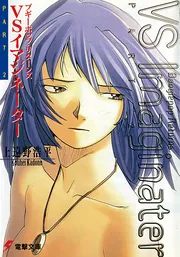死神は機嫌が悪い "Blue 'n' Boogie" ④
「じ、じゃあ──深陽学園の生徒をみんな呪っているっていうの?」
「断定はできないが、可能性は高いだろうね」
「だ、だったら──どうするの?」
「残念だけど、今はどうしようもない」
黒帽子はずっと、同じ調子で淡々と喋り続けている。それは冷静であるというよりも、なんだか他人事のように見えた。
私は不安がさらに大きくなってきて、
「で、でも何かしなきゃ──」
と相手にすがるように言ってしまう。言ってから焦りが湧く。甘えるな、とか怒鳴られそうな気がした。
しかしここで黒帽子は、
「いや、君はもうとっくに、色々とやっているんだよ」
と言った。私はきょとん、としてしまう。
「……は? なにが?」
「君はあれを呪いと呼んだが、そういうものを回避する努力を、君は日々積み重ねているのさ、すでに」
「……ねえ、何の話?」
「呪いとはなんなのか、それを定義するのは意味がない。なぜならおそらく、生命というものがすべて呪いだからだ。この世に生まれ出てきた、それ自体が呪いなのさ。生まれたからには、いつか死ななければならない──その苦痛を、ずっと味わい続けるのが生きるということだ。君たちは呪われるために生きているし、その苦痛を他に押しつけることで憂さ晴らしをしている。それはすなわち、自分以外の何かを呪っているということだ。呪いは循環しているし、それが途切れるときは世界が終わるときだ」
黒帽子の声はあくまで平静で、そこには乱れがない。そして、真剣みも薄い。異様なことを言っているのに、そこには押しつけがましい〝圧〟が薄い。そもそも何を言っているのか、いまいち理解できないし。
「せ、世界って──あんた、その敵がどうとか、さっき言ってたじゃない」
なんとか言い返してみる。これに黒帽子はうなずいて、
「そうだ。だからぼくは、ある意味で呪いの流れが終わらないように、続くように動いているとも言える」
「……は?」
「呪いは一つではない。さっき君を襲った呪いは、ぼくにとって敵だが、それは別の呪いの味方をしているということでもあるんだ」
「……呪いと呪いがぶつかり合って、戦っているっていうの? ううう、混乱する……」
私が思わず頭を抱えていると、黒帽子は、
「君は、いつも他人の悪口を言っているだろう。あれは呪いを掛けているんだ。世界は悪いもので満ちている汚いものだと定義しようとする試みであり、同時に、自分はその汚濁とは切り離された、純粋な存在であろうとする呪いだ。君だけではない。みんなそういうことを生活の中で繰り返しているんだよ」
やはり、落ち着いた口調で飄々と告げる。しかし──それを聞いて、私は、
「…………」
絶句してしまう。しかし黒帽子はそれを責めるでもなく、といって許すでもなく、あくまで他人事のように、
「ただ──今回のこれは、少し度が外れているようだ。裏にいるのはおそらく〝影を喰うもの〟だ」
──その後、気がついたら黒帽子はいつの間にかいなくなっていた。私はひとりで帰宅して、あれからずっと悶々としている。
(なんなのよ、まったくもう……)
斜め前の席で居眠りしている宮下藤花には、あの不思議な印象は全然なく、私だけが緊張しているのは馬鹿みたいだ。
そうしてへとへとになりながら、その日の授業は終わった。私はちょっと意を決して、いつも一緒に帰っている友達に、
「悪い、臼杵──先に帰っていて。私、当分一緒に帰れそうもないから」
と断った。
「えーっ、どうかしたの?」
「いや、ちょっと数学がやばくて──先生から図書室で自習しろって言われて」
すらすらと嘘をついた。相手の娘は首をかしげて、
「なんか梨杏、今日ずっとおかしくなかった? 宮下のことずっと睨みつけてたよね」
「い、いやそれは」
「あの娘となんかあったの? ケンカした?」
「そういうんじゃないから──とにかくごめん」
「いいけど──でも、気をつけなさいよ。図書室に遅くまで一人でいると、お化けとか出るってよ。自殺した優等生が後ろにいるような気がする、とか」
笑いながら言われた。冗談だとわかっているのだが、私は少し顔を引きつらせてしまった。
「は、ははは──そうね……」
「でもさ──宮下って、やっぱりなんか怪しいのかな」
「え?」
「今日の梨杏じゃないけど──時々、変な方を見てることあるよね、あの娘」
「そ、そんなことないんじゃないかな。別に、たいした意味ないと思うよ、ははは」
「そうかね──そうかもね」
「そうそう、ははは。じ、じゃあ悪いけど……」
「うん、わかった」
*
(…………)
去って行く南野梨杏の背中を見つめながら、その少女──
(もしかして、あれ効いたのかな? そして──宮下藤花、か……)
*
……そしてまた、私が一人で山道を下っていくと、問題のカーブミラーの所にさしかかった。
「うう……」
なるべくそっちを見ないように進んでいく。足下だけを見て、おっかなびっくり歩んでいると、
「いや、もう攻撃はないと思うよ」
と横から声を掛けられて、びくっ、と顔を上げる。
そこにはやはり、昨日と同じように黒帽子がいた。唐突に現れるのも同じだった。
「あ、ああ──その」
「ぼくに会いたかったのかな、君は」
「え、えと、そういうわけでも──あるかな」
私はもじもじしながら、顔を上げた。そこにはやっぱり、あの左右非対称の表情があった。
「で、でも──どうしてもう大丈夫なの?」
「大丈夫ではないだろう。単に、この前の攻撃が一回限りだろう、ということだ。別のアプローチで来る危険はある」
「よくわかんないけど──まあいいか。だったらなんで、あんたはまたウロウロしてるの」
「次の気配が現れるまでは、少しでも可能性の高いところにいた方がいい。攻撃の主体は以前はここを狙った。その事実だけが今、唯一の手掛かりなのだから。というか」
喋りながら、黒帽子は歩き出す。
「君が訊きたいのは、そういうことじゃないんじゃないかな」
私も後を追いかけながら、
「う、うん──そうだね。えと、どうにも気になってて。あのさ、あんた昨日、変なこと言ってたよね。私も〝毎日、呪いを掛けている〟って」
「気にすることでもないだろう?」
「いやいや、気になるって。なんか気味悪いし」
「自分を気味悪がっているのかい」
「だから、そうじゃなくて──私、そんなことしてないつもりなんだけど」
「つもりは関係ないんだよ。君がそのつもりでも、周囲のすべてがそうしているのだから、君もそうせざるを得ないという話だからね」
「周囲、って──」
「君の周りの人たちは、君に色々と期待したり、失望したりしているだろう。それがそのまま呪いなんだよ。君という存在を外部から規定しようとする攻撃だ。先生に叱られたりとか、友達に気にくわないことをされたりとか全部、君が呪いを掛けられていることになるし、それに対して君が〝クヨクヨしてもしょうがない〟と自分に言い聞かせるとき、君は自分で自分に呪いを掛けているんだよ。願掛けとかおまじないとか自己暗示とか色々言い換えても、それが呪いであることには変わりない」
「……ううう。そういうものなの……かな……で、でもそれを言ったら、あんたはどうなの? 自動的とかなんとか言ってるけど、あんたってみんなの無意識が生んだ悪霊みたいなもので、それが宮下藤花に取り憑いているとか、そういうものなんじゃないの、ひょっとして」
「かもね。でも、それはぼくには関係ないからね」