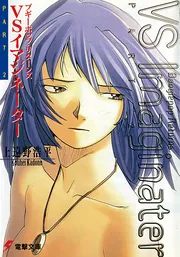死神は機嫌が悪い "Blue 'n' Boogie" ⑤
「なんでそんな風に割り切れるのよ?」
「それは話が逆だよ。ぼくには何もできない。だから関係しようがない、ということだからね。君だって他のあらゆる人間と無縁になれば、呪いを掛けられる危険は減るけど?」
「んな無茶な──できっこないでしょ」
「なら呪いも受け入れるしかないね」
「うーん……」
「まあ、今のぼくの言葉も、かなりの比率で君への呪いになってしまっているとは思うが」
「あーっ、そうよ! なによ、偉そうに上からあれこれ言ってたけど、あんただって私に呪い掛けてんじゃん!」
「上からではないけどね」
「あんた、無駄に余裕ぶっこいてるようにしか見えないのよ。そこがなんかイラつくわあ……」
「不思議な感情だね、それは」
「あんたに言われたくないわ、ったく」
──と、そんな風に私は、ブギーポップと話をするのが日々の習慣になってしまった。あれ以来、学園の危機とやらはいっこうに現れず、私が下校すると奴はいつもその辺をウロウロしているのだった。そして適当な話をしては、いつの間にかいなくなっている。翌日になると宮下藤花はふつうに来ているし、この変な習慣が私は、妙に癖になってきてしまっていた。学校で話せないことを、奴には平気で喋ってしまう。
「……いや、私だって最初から他の人の悪口を言ってたわけじゃなかったのよ? ただ、ちょっと話題が途切れちゃって、気まずい感じになったとき、どうでもいいような先生の悪口言ったら、それがみんなに変にウケちゃって。それから、なんとなく毒舌を期待されるようになっちゃって──」
「別に、ぼくに弁解しなくてもいいだろう」
「新刻に言われなくたって、わかってんのよ──言い過ぎるとマズいってのは。だからかなり気ぃ遣って、ギリギリのとこで抑えるようにしてんのよ。そうよ、宮下藤花の話だって、あいつの悪口って言うよりも、有名人の彼氏の方を責めてんだからね?」
「ぼくに言われても、なんとも言いようがないね。まあ、
「イカレてんのよ。成績も悪くないのに進学しないでデザイナーになるとか、なんのために深陽学園に進学したんだって話でしょうが──県下有数の進学校よ、ここは。青春したきゃ部活とか盛んなトコに行きゃよかったのよ」
「もしかして、羨ましいのかな」
そう言われて、他の奴が相手だったら、何を馬鹿な、って笑うところだけど、今は、
「うん、そうよ──すっごく羨ましい。格好いいって思う。でも私にはそんなの無理だし、そんな奴と仲良くなれる気もしないし」
と素直に認めてしまう。
「なんてのかな。憧れるってわけじゃないんだよね。正直、馬鹿じゃないのってのも本音。でも、どっかですごいなあって気持ちもあるの。どうして宮下藤花が、そんな男を好きになったのかってのも理解不能だけど、でもその理由を知りたいとも思う──難しいね」
「そうかな。とても単純だと思うけど」
「まあねえ、ガキっぽい反発でしかないんだろうねえ。我ながらめんどくせー性格だと思うよ。あはは」
「いや、そうじゃなくて、君はただ単に〝いいひと〟なんだよ。そう思うけどね」
「──は? なんのこと?」
「君はあの危なっかしい二人のことが心配なんだよ。でもそんなこと言ったら変な顔されるし、自分には忠告する資格がないとも思っている。だからせめて当てこすりでも言って、彼らに少しでも慎重な行動と判断を求めているのさ」
「……いや、その宮下藤花の顔で、そんなん言われても困るんだけど……ていうか、ぜんぜん的外れよ、それ。心配? なんで? 私が?」
「君の、数々の悪口っていうのも、ほとんどはそれなんじゃないかな」
「いやいやいや、待って待って。なんか変なこと言い出してるね、あんた。いくらあんたが適当で無意味なこと言ってるのが面白いからって、それはなんか笑えないよ」
「ぼくは最初から、まったく笑わないけどね」
黒帽子は相変わらず、淡々とした口調で、ふざけているのか真面目なのか、その区別をつけることはできない。
「そもそも、君がぼくと出会ったとき──君はどうして、車道に転がっている尖った石を拾っていたんだい?」
「そ、それは……」
「車が踏んで、パンクでもしたら危ない──と、そう思ったんじゃないのかな。だから反射的に動いていた。君はそういう人なんだよ。誰も見ていないところで、誰にも感謝されないのに、誰かのために行動する──そして、あの攻撃が悪質なのは」
黒帽子の陰で、その半ば隠れた眼に昏い炎が灯ったような気がした。
「そういう対象に狙いをつけているところだ。この〝敵〟は──人間という存在を嘲笑っている。〝未来〟そのものを呪っているのかも知れない──」
その横顔は、とても不機嫌そうに見えて、私はすこし絶句してしまった。目をそらして、うつむいて、しばらく無言で歩いた後で、
「う、うーん──でもさ……」
と私が振り向くと、そこにはもう黒帽子の姿はなかった。いつものように、どこへともなく消えてしまっていた。
「…………」
私はひとり、とぼとぼと山道を下っていく。そして大きな通りに出る寸前のところで、一人の男と遭遇した。
男は、歩道の真ん中に立って、山の上の学校の方を見上げている。サラリーマンのようなスーツ姿だが、なんだかその気配には、あまり穏当な印象がない。半端に伸ばした長髪に、整っているのかどうか曖昧な髭面という見た目は、勤め人か無職かわからないギリギリのラインだった。
私が立ち停まると、男はこっちの方を向いて、
「なあ、そこの君──この深陽学園の生徒だろう? 訊きたいことがあるんだが」
と言ってきた。私が返事をしないでいると、男は懐からなにやら取り出して、私の前にかざして見せた。ドラマなんかで知ってる身分証だった。
「怪しい者ではない。警察関係者だ。なんならこの辺りの管轄署に連絡を取って照会してくれてもいい」
静かな口調で告げてきた。男は眉間に皺を寄せているが、睨みつけてくるという感じでもなく、なんだかちょっと困ったような顔をしている。やっぱり、警官にはとても見えない。ではなんだ、と決めることも難しい、奇妙な男だった。
「は、はあ──ええと」
私は身分証の名前が読めずに、それを見つめてしまった。すると男は慣れた調子で、
「名前はギノルタ、と読むんだよ。ギノルタ・エージ……
となぜか繰り返して自己紹介した。私が、はあ、と生返事をすると、その鬼乗汰氏はまた学校の方を見上げて、
「最近、この学校では奇妙なことが連続して起きているらしいね。君はそういうのに遭遇したことがあるかな?」
と質問してきた。私が口ごもっていると、鬼乗汰は、
「去年だったかな、ここで水乃星透子という少女が飛び降り自殺しただろう。あの辺りからなにか始まっているんじゃないのかな。心当たりはないかな?」
「い、いや……別に」
「この学校に、生成亮って生徒がいるはずだが。彼のことは知っているか?」
「え? 生成?」
「そうだ。この地域の有力者の息子で、色々と優遇されている立場だと思うが……彼、最近おかしなことを言い出したりしていないか? 呪いがどうの、とか」
「…………」
意外な名前が出てきて、私はたじろいでいた。
(な、なにアイツ──なんであの〝お祓いさん〟のことを警察がマークしてんのよ?)
あんなのはただのおふざけの遊びでしかないと思っていたのに、突然、深刻な話に変わってきた。
(い、いや──違う……そうだ、ブギーポップの言うとおりなんだ……)