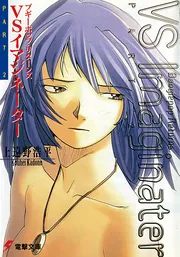死神は機嫌が悪い "Blue 'n' Boogie" ⑥
〝君にとっての世界と、全人類にとっての世界には差などない。世界は世界で、それはいつだって滅びかけている……〟
そんな大げさな、と思うことに意味なんかない。どんなことでも、それはいつだって世界とつながっているのだろう──馬鹿な同級生と自分と、それだけでは話は終わらず、世界そのもののあり方と地続きでつながっているのだ、と──私はこのとき、実感していた。
「ええと──これって正式な尋問なんですか」
私は鬼乗汰に、気がついたらそう問い返していた。無駄な反感を招くような挑発的な言い方をしていた。しかし鬼乗汰はこれに、
「もちろん違う。公式に資料として採用されるものではないから、君もそんなに深刻に考えなくてもいい」
と受け身の言い方をしてきた。その丁寧さに、私はますます、
(やばい、これってマジだ……)
という緊張感が増してきた。そこでできるだけ自然な調子で、
「いや、生成ってやたらに呪いを解いてやるって言いふらしてるんですけど、その相手はだいたい女の子なんですよねー」
と軽く言った。鬼乗汰はうなずいて、
「なるほど、ナンパのようなものだと? 君も言われたことが?」
「ええ。友達と二人のときに。でもすぐに〝うるせー、あっち行け〟って言っちゃいました」
「それで、彼は怒った?」
「いいえ。そんなに真剣じゃないのかも」
「ふうむ……反応を識別しているのか──」
「え?」
「いや、こっちの話。それと……まあ、こっちは本当にどうでもいいんだが、彼はもしかして、なんとかの〝機構〟に自分は属している、みたいなことを言っていないか?」
「…………」
「もちろん彼の親は金持ちなんだが、それだけではなく、世界で特別な立場にあるんだという、妙な自慢をしていないかな?」
「……ええと、わかりません。そこまで話をしたことないんで」
「そうか──いや、呼びとめてすまなかったね。ありがとう。もういいよ」
「はあ──」
私が横を通り過ぎても、鬼乗汰はまだ立ったままで、学校の方を見上げ続けている。なにかを監視しているのか、それとも──
(……ブギーポップを待っているの?)
私は冷汗を背中に感じながら、だんだん早足になりつつ坂道を駆け下りていった。
*
翌日、ブギーポップに鬼乗汰のことを相談しようと思ったのだが、しかし肝心の宮下藤花が登校してこない。
(な、何やってんのよもう──なんで今日に限って休むのよ?)
彼女が来なかったら、当然ブギーポップもいないわけで、私はイライラしていた。
しかし、昼休みになって意表を突かれる事態が起きた。
教室に三年生の男子がひとり、やって来て、
「あのう──宮下さんは来てますか?」
と声を掛けてきたのだ。
そのときクラスにいた全員が、思わず彼の方を注目した。皆、その人のことを知っていた。
そう──彼は竹田
「…………」
皆が黙っているので、私が仕方なく、
「宮下さんは、休んでるみたいですけど」
「朝から来てないんですか?」
「はい……」
「そうですか──失礼しました」
竹田啓司はものすごく不安そうな顔をしながら、クラスから去って行った。
「なあに、あれ?」
私の横にいた臼杵がひそひそと囁いてきた。
「なんか揉めてんのかね、あの二人。彼女なのに直に連絡取れないのかな」
「そ、そうね──」
教室中でひそひそ話が広がる。皆、あの二人の話をしているのだろう。私はなんだかいたたまれない気持ちになってきた。ついこないだまで、自分が率先してそういう話をしていたのに──。
だがここで、そんな空気をさらに一変させる事態がまた起きた。
今度は二年生の女子生徒が来て、扉をばん、と勢いよく開きながら、
「おい──宮下藤花はいるか!」
と怒鳴ったのだ。
皆が絶句し、今度は私も返事ができない。いつもは陰で彼女のことを笑っている者たちは、本人を前にしたらひたすら威圧されて、縮こまることしかできない。
その女子は、噂では中学の頃に留年して、歳は皆よりひとつ上らしい。しかしその迫力は、そんな一歳差のレベルで語れるものではない。
校内一の不良にして、炎の魔女とも呼ばれるその女──霧間凪は、誰も答えないことには特に反応せずに、教室内を一瞥して、そして宮下藤花がいないことを確認すると、
「ちっ──」
かすかに舌打ちして、そして扉を閉める。皆がほっ、としかけたところで、また扉が開いて、霧間凪が皆をじろっ、と睨みつけながら、
「おい──つまらない〝呪い〟なんか気にしてる奴がいるなら、そんなのは意味がないからな。……いいな!」
とドスの利いた声で言うと、彼女は身を引いて、今度こそ扉が完全に閉められて、そして足音が遠ざかっていく。
「…………」
「…………」
皆はしばらく絶句したままで、なかなか元に戻れなかった。
少しずつ誰かが咳払いしたり、ごとん、と椅子を引いたりして、音がし始めて、なんとか普通の空気に戻っていく。
(で、でも……いったいどういうことなの……?)
私は困惑し、混乱し、そして……焦っていた。
身体の奥がすごく冷たくて、そのくせじりじりと炎で焼かれているような気分になっていた。
宮下藤花に何かあったのだろうか? それはつまり──
(ブギーポップが──)
その身になにか決定的な事態が起こっているのだろうか? 今の二人は、それであんなに焦っていたのか?
それを考えると、私自身も焦りが湧いてきてどうしようもなくなるのだった。
そして──視線を落とした私は、隣の席で臼杵がなにげなく記しているラクガキを見て、ぎょっとなった。
「う、臼杵──それは──その赤い〝線〟は──」
思わず声に出してしまって、彼女に怪訝そうな目で見られる。
「え? なに?」
彼女はルーズリーフ用紙に、アンダーライン用の蛍光ペンで線を引いていたのだ。
その赤い線が、私があのときに見た、カーブミラーの中に見えた赤い線のように感じられて、それで──
「い、いや……なんでもない」
……弱々しく打ち消す。どうでもいいような物まで怖くなってしまっている。明らかに私は今──ひどく動揺している。
「このペンがどうかした? 貸してほしいの?」
「ううん、そうじゃなくて──なんでもないから……」
私がおどおどしていると、臼杵は、
「そういやぁ、さ──さっき、炎の魔女が変なこと言ってたよね。〝呪いを気にするな〟とか──あれって、どういう意味だろうね?」
「い、いや、それは──」
「この学校の呪いって、そんなに皆に気にされてんのかな。あんな不良までムキになるくらいに、存在感あんのかね」
「ど、どうだろう──」
私は気もそぞろで、彼女が言っていることの半分も耳に入っていない。生返事をしているだけだ。
臼杵はそんな私にかまわず、なおもルーズリーフ用紙に赤い線を引きながら、
「思うんだけど、さ──呪いってのは、外から掛けられるものじゃなくて、怖がっている本人の心の中にあるんじゃないかな。そう、怖いと思うから怖い、ってヤツよ。でもさ、それって逆に言うと」
赤い線は、いつのまにかぐるぐると螺旋を描いている。いくつもの渦巻き模様が、彼女の指先から形成されている。
「どんなに強いヤツでも、どんなに偉いヤツでも、どんなに周囲に守られているヤツであっても──世界中の誰でも、怖いと思ったら、それでおしまいなのかも知れない。そこには実体はいらない──影絵だけでやる芝居みたいなもので、充分──この〝シャドゥプレイ〟だけで、呪いは成立する──そう、相手がどんなに恐ろしい死神だろうと炎の魔女だろうと、統和機構だろうと──」
臼杵はまだぶつぶつ何か言っているが、私は完全に聞き流して、
「あ、あのさ臼杵──私ちょっと急に用事を思い出して、行かなきゃならなくって」
焦りながら言うと、彼女はにっこりと微笑んで、
「うん、わかった──じゃあね、ばいばい」
と小さく手を振ってきた。私は、
「う、うん──それじゃ」
と、せかせかとうなずくや否や、教室から飛び出して行った。
まだ遠くへは行っていないはずだ──私は階段を駆け上がり、三年生のいるフロアへ向かった。
竹田啓司と、話をしなければ──。