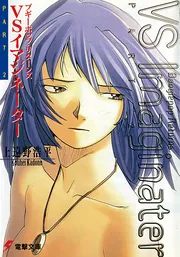ブギーポップ・ナイトメア 悪夢と踊るな子供たち
1,愚を欺き、悪に迷い…… ①
「ところで、世界の頂点に立つってどんな気分なんですか?」
「……誰よりも愚かで、害悪だと……思い知らされる感じだな……君もそうだろう……」
──とある対話の断片より
玖良々三兄妹──とは言うが、実際のところ彼らには血のつながりもなければ義理の関係もない。共通するのは、同じ〝欠落〟と──紫色をした瞳。
*
ぴゅうっ、と口笛がその広い室内に響くと、玖良々
「やめなよ──
と文句を言った。彼女はその顔立ちだけならまだ幼さの残る少女にしか見えない。
言われた少年は、ちょい、と片眉を上げて、
「悪い悪い。でも無意識でね。嫌な予感がすると、つい吹いちゃうんだよね」
と無邪気な調子で言う隣で、もう一人の少年が、
「まあ、ふつうは口笛を吹くっていうのは〝やったね〟とか〝よかった〟みたいなときだから、印象としては真逆なんだけど──でもさ、舌を出して、あっかんべえ、とかやるのは、相手を挑発する意味になるけど、でも土地によっては、相手を祝福するジェスチャーになる文化もあるらしいから、その辺は一括りにはできないんじゃないかな。少なくとも、あなた方の話を聞いて〝ざまみろ〟と思ったわけじゃないってことを、納得してもらいたいね」
と悟りすました表情で静かに告げた。少女もうなずいて、
「そうそう──
と言う。その声もさほど大きくないのに、しかし広い室内に充分すぎるほどに響く。
とても広い──ここは都心でも最高級のホテルの、さらに最上階で最高値のスイートルームだった。
壁のほとんどはガラス張りで、外が一望できるようになっているが、今はそのすべてが遮光カーテンで覆われていて、いくつかの間接照明だけで全体は薄暗い。しかしそれでも、その豪奢な内装は隠しようもない。
玖良々三兄妹は、この部屋を半年以上も占拠している。しかし宿泊代は一切払っていない。自分たちは誰がその負担をしているのかさえ知らないし、興味を持とうともしない。
「は、はあ……」
彼らの前に座っている男は、憔悴しきった顔をしている。その隣の女は、疲れ切って焦点の合わない目を宙にさまよわせている。二人ともよれよれになった服を着ているが、それは特注で誂えさせた仕立てのいいものであるはずだった。だが着の身着のままで一週間も経てばどんな立派な服でもみすぼらしくなるのは当然だった。
「ええと……それで、いくらだっけ。あなた方の今の負債総額って」
と南砂が遠慮のない口調で訊くと、男は震える声で、
「じ、十億ほどです──株も下がり続けているので、毎日のように膨らんでいっています……」
と漏らした。横の女が、あああ、と呻いた。そこでまた西風が、ぴゅうっ、と口笛を鳴らした。
「いやあ、すごいねえ。ツイてないねえ」
「実感湧かないだろうねえ。いつのまにそんなことになってしまったのか、未だに理解できていないんじゃないかな」
北斗の問いかけに、男は力なくうなずく。
「ほんとに……なにがいけなかったのか……」
弱々しくそう呟くと、三兄妹はそろって、
「いや、それは話が逆」
と言った。そして南砂が、
「いけないことをしたから、しくじったから損をした──そんな風に思うこと自体が、そもそも間違っている。世界というのは、最初からうまくいかないもので、成功するってことは、不自然であり、そもそもどうかしている──あたりまえのことが起きたに過ぎない。だからあなたたちが気に病む必要なんて、全然ないって」
と穏やかな口調で言った。そこに圧はない。やや茫然としている二人に、彼女は、
「ただ──ひとつだけ悪いとするなら、それはあなたたちが〝未来〟を信じすぎてしまったということだけ」
と続けた。相手の反応を待たずに、さらに、
「自分たちには素晴らしい将来が待っているはずだ、とか考えちゃってたんじゃない? これだけ努力したのだから、その見返りがあるに違いない、ないと腹が立つ──そんな風に感じて生きてきたんでしょう、これぐらいの対価を払えば、それにふさわしい成果は必ず伴うはずだ、って──そう信じて、これまでやってきた──でもね、その結果が今。努力してきたことは全部、裏目。賭けは負け。クジは外れ。他の者たちの強欲に食い尽くされて消費されるだけの存在になっている。それもこれも、あなたたちが〝未来〟に縛り付けられていたから」
彼女がそこまで言ったところで、今度は北斗が、
「なあ、そんな〝未来〟なんていらないだろう? 君たちはそれをこれまで素晴らしいものだと思ってきたかも知れないが、実際のところ、人間にとってほとんどの未来は、害にしかならないんだよ。事故に遭う未来、病気になる未来、才能が涸れる未来、仕事がなくなる未来、友だちに裏切られる未来──そういう未来なんかいらない、そうは思わないかい? 百の未来のうち、君たちにとって都合のいい未来はひとつかふたつで、それが重なることさえ滅多にないんだ。いいことがひとつあれば、九十九の悪いことが待っている。それが未来を受け入れるってことだ。現に今の君たちは、十億という返しようがない負債を抱え込んで、破滅する未来しか残っていないわけだけど──それを後生大事に抱え込んで、これからの人生を送るつもりかい?」
「そ、それは──」
「なあ、いらないだろう──そんな〝未来〟なんて」
北斗は言葉を繰り返す。それからうっすらと微笑んで、
「君たちは、ここに何をしに来たのかな? 僕らの話を誰から聞いたのか知らないけれど──どんな話を聞いてきた?」
と質問してきた。二人は小刻みに震え出す。
薄暗い室内の中でも、三兄妹のその肌の白さは明確に見て取れる。それは病的なほどで、しかし彼らの物腰には弱々しさなど微塵もない。いや、むしろ妖しいまでの不敵さ、強靱ささえ感じられる──。
「……え、えと……」
おどおどしている二人に、西風がにっこりと笑いながら、
「吸血鬼みたい、とか思っている?」
と言った。二人の顔が強張るのと、部屋のカーテンが一斉に開いていくのは同時だった。いつのまにか南砂がリモコンを手にしていて、その〝開〟のスイッチを押していたのだった。
まぶしいまでの陽光が、燦々と室内を照らし出して、三兄妹の身体を包み込む。その白い肌がまるで陶器のような反射で、きらきらと光って見える。
そして、その輝きを逆に吸い込んでしまうような深い深い紫色の瞳が六つ、二人のことをじっ、と見つめてくる。
その美しさに……二人は状況を一瞬忘れて、うっとりとしてしまう。
「ああ……」
「この通り、別に僕らは太陽の下に出られない魔物でもないし、君たちの生命そのものを吸い取るつもりもない。ただ──君の要らない〝未来〟を引き取るだけだ。それが僕ら〈サンタ・クララの生存者〉と取引するということ──」
三兄妹はあくまでも穏やかに微笑んでいる。
その噂は、ごく一部の間でだけ伝えられている。
どうしようもなくなって、どこにも救いがないときが来たら──玖良々三兄妹のところに行けばいい、と。
ただし彼らと会うにはとてつもなくハードルが高い。人づての人づてで、次は誰某に会え、どこそこに行け、とさんざん振り回されたあげく、それでもめげずに追い続けていると、あるとき──突然に本人たちが出てくる。