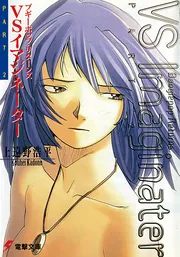ブギーポップ・ナイトメア 悪夢と踊るな子供たち
1,愚を欺き、悪に迷い…… ⑤
*
統和機構がいつから存在しているのか、誰も知らない。それはいつのまにかこの世に存在していた。あるいは人類がこの地上に出現したときには、その萌芽はすでに生まれていたのかも知れない。
その組織とも言えず、集団とも言えず、国も人種も越えて明確なビジョンもないぼんやりした〝仕組み〟──システムとしか言い様がない存在の目的はただひとつ、
『進化しすぎた人間を排除する』
その一点のみである。現行人類の安定のために、新しい可能性に目覚めた者たちを始末してきたのだ。
そのために〝合成人間〟と称する疑似進化を遂げた者たちさえ創りだし、世界中に〝殺し屋〟として派遣している。世界を裏から監視し、陰から支配している存在──しかし、その全体を把握している者は誰もおらず、トップに君臨しているという〝
その苛烈な虐殺活動のなかで、数少ない例外として計画されたのが〈サンタ・クララの子供たち〉と呼ばれる施設だった。
きっかけは情報分析部門の長であるジッタリン・フィジティンという男が、害がないにもかかわらず処分されている児童が多すぎるのではないかというデータを下に、それまでは危険な存在として扱われていた可能性がある者を、充分に管理すれば強力な味方として活用できるのではないか、と提案したことに始まる。
そうして、周囲から〝なんか不思議だな〟と思われるような天涯孤独の子供たちが集められた。
そしてその中心には、玖良々東梨という紫色の瞳をした少年がいた。彼はみんなに向かって、
「僕たちはみな、兄妹になろう。今までのことなんて関係ない。これから新しい家族になるんだ」
と提案した。彼は子供たちの中でもひときわ奇妙で変わっていて、そして魅力的だった。統和機構の大人たちとも対等以上に話し、管理者たちも彼のアドバイスに従い、彼の指示で動いていた。
子供たちも東梨になつき、憧れ、彼と一緒に家族になると誓った。みんな新しい名前を名乗り、一致団結した家族となった。その中には、西風、南砂、北斗の三人も含まれていた。生まれも育ちも、ここに来た過程もバラバラな彼らだったが、まるでずっとずっと昔から肉親であったかのように、打ち解けて深い絆で結ばれた。
そして──子供たちは玖良々東梨から〝あること〟を教えられていった。
それは〝未来〟を操ることができる力だった。
「僕らはみんな、世界から疎んじられてきた。だから自分たちの可能性を──〝未来〟を自分たちで制御しなきゃならない。他の人たちが無造作に扱っている可能性を──〝未来〟を僕らは繊細に取り扱わなきゃならないんだからね」
彼に心酔していた子供たちは、みんな言われた通りにした。自分たちが何をしているのかよくわかっていない内から、色々と変化が生じていった。
そんな中で──東梨は奇妙な話を皆に伝えた。
「なあみんな、ブギーポップって知っているかい?」
誰も知らなかった。彼によると、それは都市伝説の中で囁かれる死神で、その人が人生の中でもっとも輝いているとき、その美しさが頂点に達したとき、それ以上醜くなる前に、殺してくれる存在なのだという──。
「女の子の間でだけ語られる存在らしいんだけど、まあ、僕らはみな、世間一般でいう性別からは自由な存在だから、別にかまわないだろう──僕だって、とある女の子から教えてもらったしね」
「その人は?」
「ここにはいない。でもいつか、僕らも彼女と一緒に世界を変えられたらいいな、と思っているよ。それよりも、今はブギーポップの話だ」
「なんか怖いね。そんなのがウロウロしているのかな」
「馬鹿だな。そんなのデマに決まっているじゃん」
「でも、それ言ったら私たちだって、世間の人たちからは信じられていないようなものじゃない?」
「だから、いつか認めてもらえるように頑張るんだろ?」
皆がわいわいと喋っているのを楽しそうに見つめていた東梨は、やがてぽつりと呟いた。
「でも──僕はブギーポップがほんとうにいるなら、そいつに殺されたいって思うよ」
え、と皆が彼の方を見ると、うなずいて、
「なんていうか──保証されたいって感じだね。自分は人生を可能性の限界ギリギリまで追究した、もっとも美しく輝くことができたんだ、ってね──死神はそれを認めてくれるんじゃないかな」
どこか遠い目をして、東梨はうっとりとした表情を浮かべていた。西風たちはそんな彼を見たことがなかったので、少し驚いた。
だが結局、玖良々東梨はブギーポップに会うことはできなかった。彼らの下に来たのは死神ではなく──最強の暴力そのものの化身フォルテッシモだったからだ。〈サンタ・クララの子供たち〉はその圧倒的なパワーに踏みにじられ、何もできないうちに壊滅した。
どうして西風たち三人だけが生き延びられたのか──自分たちでも憶えていない。思い出せない。
目が覚めたときには、彼らは柊に保護された病院のベッドの上だった。
それからずっと──三人は柊の言う通りに生きている。
東梨に分け与えられた〈サンタ・クララ〉の能力をちまちまと使うことで、莫大な資産を形成しているらしいが、管理も何もかも、彼らに〝処置〟されて支配下に置かれた者たちに投げっぱなしなので、どうなっているのかはわからない。せっかく〝未来〟を制御する力を持っていても、彼ら自身はもう、どういう〝未来〟を夢見たらいいのかわからない。
そういうビジョンは、東梨と一緒に消えてしまった。
柊は、彼らに決して無理強いしない。頼みを断っても、きっと何も問題はないのだろう。東梨のように「こうしよう」という提案をしてくれるわけではない。しかし三人にとっては唯一の〝みちびき〟なのだった。
「なあ、柊さんが一緒に統和機構に逆らおう、って言ったらどうする?」
教えてもらった土地に来て、初めて見る街を前に、北斗がぽつりと呟いた。
目の前の大通りでは人々が次々と行き交っているが、彼らの方を見る者は例によって誰もいない。
「そんなの考えるまでもないでしょ。私たちに他の選択肢、ある?」
南砂は当然、という顔である。しかし西風は、
「どうかな──確かにその方が楽なんだろうけど──」
と煮え切らない表情である。
「でもそうなったら、僕らはまたフォルテッシモと戦わなきゃならなくなるんじゃないか。そして──今度はきっと、助からないよ」
「────」
「…………」
二人も黙り込む。彼らにはどうしようもない恐怖が刻まれている。自分たちの夢を家族ごと
「……で、でも、それでも、今度は私たちだけが取り残されることにはならないじゃんか」
南砂が震える声でそう言うが、しかし弱々しさは隠せない。
「……そうよ、そのときは私があんたたちを守るよ。盾になってかばうから」
「──いや、そのときはみんな一緒だ。それは否定しないよな、西風」
北斗に言われても、彼は苦笑したように微笑むだけで、何も言わない。
三人が空気の重たい沈黙に包まれていると、街の人通りの中から一人近づいてきて、
「見つけました──問題の二人です。織機綺と谷口正樹です」
と三人に教えた。既に能力によって支配した手下の一員である。
「よし──では、作戦開始と行こうか」
北斗が歩き出すと、西風もそれに続く。
まだ動揺から脱しきっていなかった南砂だけが、はっ、と我に返って、あわてて二人の後を追おうとして──そこで、
……ざわっ──
という悪寒が背筋を走り抜けた。何かを感じた。
視線が──自分に向いている。
誰かがこちらを見ている、その生々しい圧迫が来る。
はっ、となって感触がした方を見る。しかし、そこにはただ無関心な雑踏があるだけで、特に怪しい人影などはない。
(しかし──今のは……)
その気配には何かが絡みついているような気がした。
その紫色のイメージは、それは……
(…………)
一瞬、立ち尽くしていた彼女に、北斗が、
「おい南砂、何している──早く来い」
と呼びかけてきたので、彼女は戸惑いつつも小走りで駆けていく。
だが今のは、その紫色の視線は忘れようのない感触だった。
死んだはずの、玖良々東梨の気配に酷似していたのだった。