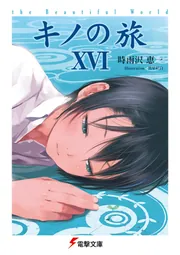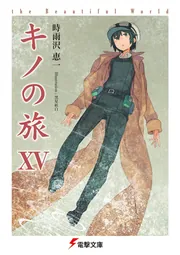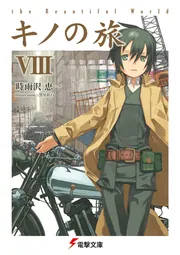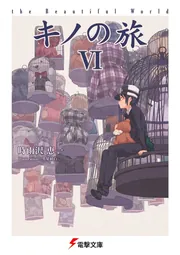第一話 「人の痛みが分かる国」④
「そうだね……、簡単に言ってしまうと、ここは人の痛みが分かる国なんだよ。だから、顔を合わせないのさ……。いいや……、合わせられないんだ」
「人の痛みが分かる、ですか?」
「何、それ?」
男は少しだけお茶を飲んだ。
「君達も、昔親から言われたことはないかい? 人の痛みが分かる人間になりなさいって。そうしたら相手のいやがること、相手を傷つけることをしなくなる。もしくはこう思ったことはないかい? 他人の考えが分かれば、それはきっと便利で素晴らしいことだって……」
「ある! あるよ! ここに来る時もキノは、まったく……」
男の問いかけに、エルメスが飛びつくように答えた。キノに発言の機会を与えない素早さだった。
「悪かったよ、エルメス」
キノが淡々とした口調で、エルメスの発言にかぶさるように言った。
「この国の人間も、真剣にそう思った。昔からこの国では機械が仕事をほとんどやってしまい、人間は楽に生活できた。食べ物も豊富で、とても豊かで安全な国だった。そうすると人々は、暇を持て余してしまい、頭脳を使ういろいろなことに挑戦するようになった。新しい公式を発見したり、ひたすら科学的追求をしたり、文学や音楽を創ったりね。そしてある時、人間の脳を研究していた医者グループが、ある画期的な発見をしてしまった……。その発見とは、人間の脳の使っていないところを上手く開発すれば、人間同士の思いを直接伝え合うことができる、というものだった」
「思いを直接伝える?」
キノが怪訝そうな顔で聞いた。エルメスも、
「どういうこと?」
男は話を続けた。
「たとえば僕が、頭の中で『今日は』と思う。そうすると近くにいる人にその挨拶が伝わる。こんな単純なことじゃなくても、僕が何か悲しくなった時、近くにいる人にその悲しみが直に伝わる。その人は僕の悲しみが理解できて、僕に優しくしたり、解決方法を一緒に考えたりできる。または言葉のできない赤ちゃんの痛みや気持ちよさを、その母親が感じることができる。俗っぽい言い方をすれば、テレパシーってやつだ」
「なるほど」
「はーん」
キノとエルメスが同時に相づちを打った。
「国中の人が、それは素晴らしい発見だと褒め称えた。それによって人間はお互いに心の底を伝え合うことができる。そしてもっとお互いを分かり合える。自分達は今までの、ノイズだらけの、しかもきちんと伝わっているか絶対に確認し得ない言語によるコミュニケーションを、古くさい方法にすることができるんだ! ……みんなそう信じた。そして全ての人間にその能力を与えようと、簡単に脳を開発できる方法を探り、薬が完成した。それはもう、あっという間にね。それから、全ての国民がそれを飲んだ」
「全員が?」
エルメスがすかさず聞いた。
「全員がさ。みんながみんなと同じ高みに立ちたかったんだ。進化したかったんだよ。取り残されたくなかったんだ。そして、確かにある意味僕達は進化した……」
「それで、どうなりました?」
キノが思わず身を乗り出した。男は少しだけ悲しげな表情をして、淡々と話し始めた。
「ここから先は、僕個人の体験を語ろう……。僕は薬を飲んだ。飲んだ次の日の朝、目が覚めると『分かる? 分かる?』と頭に何か飛び込んできた。部屋には誰もいない。驚いたよ、本当に離れたところにいる人間からメッセージが届いたんだ。それは、もちろん『分かる?』って言葉で頭に伝わった訳じゃない。僕自身が『分かる?』と思っているような感じがしたんだ。とっさに『分かるよ!』と思ったら、『私にも分かるわ! 凄い!』と感じが返ってきた。『玄関にいるの』と伝わったので、あわてて外に出てみると、僕のその時の恋人が立っていた。テレパシー能力の開花は成功したんだ。僕と彼女は嬉しくて嬉しくて、何度もお互いを思い合って、『愛してる』を伝え合った。今思い出すと笑っちゃうけれどね」
男はそこで一旦話すのを止めて、ふーっと息を吐いた。
「僕達は世界で一番幸せだと思った……。その時はね。そのまま一緒に暮らし始めて、それから数日が過ぎた。そして……ある時、僕は彼女がハーブに水をやっていて、そしてあげすぎてしまったのを目撃した。そして思った。『あれ? この間注意したのに。何度言ったら分かるんだろうなあ?』ってね。それと同時に『違うよー』って穏やかに言おうとしたんだ。でも、それを言う前に、彼女は僕を睨んでいた。そして頭の中に直接返答が届いた。『なによ! 何度言ったらって? 私のことバカだと思ってるのかしら!』」
「…………」
「そう、彼女に伝わってしまったんだ。伝えたくないことがね。彼女のいきなりの返事に僕はとまどって、『一体なんなんだ? なんでそんなことで、こんなに怒られなきゃならないんだ?』と思ってしまった。すると、『そんなこと? そんなことですって? 私にとってはとても重要なことが、やっぱりあなたにとってはそんなことなのね!』そう返事が来た」
男の顔に、今度はほんの少し笑みが浮かんだ。それは、自嘲するような笑い方だった。
「その後は、ひたすらテレパシーでケンカさ。実はね、彼女は僕に対して、学歴面、そして頭脳面での劣等感を常に持っていたんだ。僕は長年つき合っていて、そのことにまったく気がついていなかったのさ……。当然、彼女が僕はそれに気づいてるんだろうと思ってることも、気づいてなかった。彼女は、『あんたみたいなエリートぶった冷血人間と、一緒になんていられないわ!』と捨て思いを残して、出て行ってしまった。僕はボーゼンと取り残されて突っ立っていた……。とんでもない笑い話さ。お互いの心の内をストレートに伝え合うことができたから、もう取り返しのつかないほど仲が悪くなってしまった。でも僕らは笑い話ですんでまだよかったんだ……。同じ頃に、とある場所では一人の人間が事故で死にかけた。その人間が今際のきわに思っていることが、あわてて駆けつけた人達に伝わって、彼らを発狂させてしまった。別のところでは、今まで手を組んでいた二人の政治家が、じつは互いに相手をいつか裏切ってやろうと思っていたのがばれて、議会で殺し合いを始めた。決着がつかないで、そしてお互いに痛くなって止めたけどね。学校では、みんなが答えを教え合うのでテストが成り立たなくなっていた。ああ、そういえば若い女性に近づいただけで、婦女暴行未遂と猥褻物陳列で訴えられた奴もいたな」
「…………」
「まあ、そんなようなことがあちらこちらで起こったんだろうな。一週間ほどは、国中パニック状態だった」
「それから、どうなりました?」