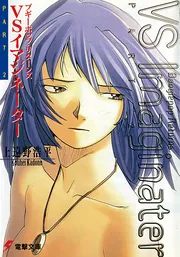crack1.最強の先は弱くなるだけ ①
「堕落したけりゃすればいいさ。自ら進んで落ちぶれるってのは、それはそれで立派な選択だと思うよ。後で後悔するのも含めて」
――霧間
周囲からは平凡な優等生だと思われているこの少年には、誰にも言っていない秘密の習慣がある。
一日に一度、携帯端末の電源を切って、人っ子ひとりいない無人の廃墟をさまようのだ。その三十分ほどの間、彼は自分が「まだ大丈夫」だと感じる。
今日は調整がうまくいかず、電源を落とす直前に着信が来てしまった。
ため息と共に出ると、通話口からいつもの、
〝臣井、あんた課題提出が遅れてるって?
と少女の声が響いてくる。
「予定通りだよ。先に数学の方をやっただけだ。美術課題は少し遅れても大目に見てくれるから」
と答えると、咲奈は、
〝ダメだよそんなんじゃ。ちゃんとしないと。せっかく臣井、絵がうまいんだから。美大にだって行けるかも、って先生も言ってたし〟
と注意してきた。拓未は舌打ちしたくなる気持ちをぐっと抑えつつ、
「行くわけないだろ、親が許すはずないんだから。理系の国立大って今から言われてるのは、如月だって知ってるだろ」
〝それは……〟
「話はわかったよ。明日には出すから。じゃ」
と彼から通信を切った。いつもならこういう連絡等は、事前か事後に来るように彼の方からあちこち根回ししておくのだが、今日は少し詰めが甘かった。如月咲奈に対しては、学校で一声掛けておけば、そこで済んでいた話だったろう。彼女は少し放っておくと、色々なことを勝手に、深刻な方に思い詰めがちなので、その前に片付けておくべきだった。あるいは美術教師に彼の方から先に課題は明日出します、と言っておけばよかった。
(なかなか面倒くさい……)
しかしそれでも、彼は誰からも切り離されてさまよう時間を作らずにはいられない。この前、どうにもスケジュールが取れなくてやむなく学校から塾に直行したことがあったが、そのときは最悪だった。集中力が切れて、やたらとイライラして、マニュアル通りの授業しかできない講師に向かって無駄に反抗的な態度をつい取ってしまって、後のフォローが大変だった。
(精神の安定のためには、この時間が絶対に必要だ……)
その場所は、彼の通っている中学校と学習塾の間にある再開発地域だ。去年からずっと封鎖されていて、しかし工事はいっこうに始まっていない。かつてそこにあった建物は半分壊されているが、しかしそのままの物も多く、様々な計画が頓挫しているのだろうと推察される。通りひとつ分くらいの規模がまるまる外界から遮断されている。
(まあ、来年ぐらいにはもう、さすがに工事が始まっちゃうんだろうから、今だけなんだろうな……)
それに定期的に管理の人がやって来ているから、見捨てられた土地というわけでもない。ただ拓未にとっては、自分がふらふらとさまよう三十分の間だけ、無人であってくれれば充分だった。他の場所だと、いくら人がいないと思っても、ふいに道の角から通行人が現れてビビることを避けられないが、ここではその心配はない。
厳重に鍵が掛けられて、柵で覆われている場所には、彼しか知らない抜け穴がある。柵の一部のナットを締め忘れていて、押すと小柄な彼がギリギリ通り抜けられる隙間ができるのだ。これを偶然発見してから、彼の秘密の冒険が始まったのである。
(陽が沈みきる前にしかいられないしな……)
当然、区域内には照明が一切ない。一度だけ雨の日にも入ってみたことがあったが、完全に真っ暗で何も見えなかった。そのときは一箇所にただ立ち尽くしていた。それも悪くなかった。
薄い柵一枚で囲われているだけなのに、その場所は静まりかえっている。外の騒音は聞こえるけれども、どこか決定的に、遠い。
(ああ……安らぐ)
拓未は無人の街をふらふらと歩き出した。
世の中に自分しかいない、文明が滅びた世界をさまよっているような気分になる。もうこれ以上、何もしなくていいんだ、という感覚に浸れる。
ここにいる間だけは、自由だ――そういう錯覚がある。そんなことがないのは理解している。でも目に入ってくるのは半壊した風景であり、道を行くのは自分だけであり、そして外部からの連絡もない。
(ここでは僕は、無敵だ――誰にも邪魔されない最強の存在だ――)
彼は子供っぽい陶酔に浸りながら、あちこちアスファルトが剥がされている路面を踏みながら、いつものお気に入り散歩コースを進んでいく。悲しいかな、本人は意識していないが、それは安全なルートを丁寧に分析して、ほどほどの安全性が保証された道筋になっていた。無意識のうちに、無難なやり方を選択してしまっている。
そして陶酔しつつも、心の一方では冷静に時間を計っていて、この場所にいるのは必ず三十分以内であり、携帯端末の電源を切る時間を決して半時間以上にはしないのも、身に
(今、僕は自由だ――でも)
ふいに、馬鹿なことをしているなー、という自覚が芽生えそうになり、それを即座に打ち消す。白けてしまったらおしまいだ。せっかくの気晴らしをひとつ減らしてしまうことになる――その不安に駆られそうになった、そのときだった。
――どおん、
と、頭上から音がした。ぎくっ、として上を見上げると、半分解体されているマンションらしき建物から、
(
そんな風なものが降ってきたように見えた。ぶるるっ、と背筋が震えた。
世界が滅びる前兆のような――そんな気がした。
*
――数分前。
その問題の解体中であるマンションの一室では、二人の男女が
その内の一人、女の方は、手脚を針金で縛り上げられて、椅子の上に固定されていた。顔中に切り傷が刻まれていて、しかしその手当ては一切されていない。
拷問されている。
もう一人の男の方は、妙にさっぱりした顔をしている。手にはナイフを持ち、それにはあからさまな返り血がべったりと付いているにもかかわらず、その表情には重みや
彼は縛り上げられた女に、穏やかな調子で、
「なあ〈サーチ・ショート〉――君は我々、合成人間について、どう思っていたんだ?」
「…………」
「我々は統和機構によって改造されて、常人にはない特殊な能力を獲得した。それは自然に発生してしまう、人類を滅ぼしかねない進化しすぎた危険な新人類MPLSに対抗するためだが……だが、いつだって〝その不安〟がつきまとっている」
「…………」
「そう、我々が強くなっていくと、いずれは危険なMPLSと同類になってしまって、統和機構に始末されるのではないか、と――そう思ってしまう」
「…………」
「ああ、ああ――君自身はそうでもないな。君の能力はどこまで行っても、他の者をサポートする役にしか立たないからな。だが……君の相棒は、そうは行かないよな」
「…………」