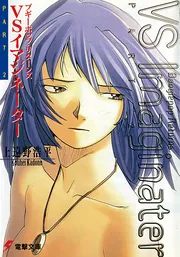crack1.最強の先は弱くなるだけ ③
(こいつも、だな――せっかく大きな任務を任されたというのに、こんな横やりが入って、ぜんぶ台無しだ。みんなツイていない――私だってこの最強さんのご機嫌を損ねたら、どうなるかわかったもんじゃないし――)
と彼女が心の中でぼやいていると、フォルテッシモがサーチから視線を外して、空を見上げて、
「来たな――」
と
「ううう……」
サーチが
ふう、とカチューシャはため息をついて、羽衣石に、
「なあ、ポエット――さっさとこいつにトドメを刺してやれ。フォルテッシモが弟の死体を持ってくる前に、楽にしてやれよ」
と言うと、彼女も壁の穴から外へと飛び降りていった。
「…………」
その場には、また二人だけが残された。
「うぐぐ……」
激情に燃え続けているサーチに、羽衣石頼我は振り返った。
その表情が――変わっていた。
乱入者たちが来てからの動揺は、
(…………?)
サーチが眉をひそめると、羽衣石は手にしていた特殊徹甲弾入りの拳銃を顔の前にかざして、ひょい、と傾けて――そして、放り出した。
床を滑っていって、それは――サーチの足下へと到達した。
縛られている手を伸ばせば、指先が届きそうなところに――。
「え……?」
サーチが驚いた顔を上げると、羽衣石ことポエトリー・アナトミーはあくまでも生気のない表情のまま、
「…………」
と沈黙している……。
*
(な、なんだ……?)
臣井拓未は、無人のはずの街でいきなり始まった衝撃の連鎖に、ひどく戸惑っていた。
学校と塾の間の、ほんのささいな息抜きのはずだった廃墟の散策は、謎の破壊音と振動が辺り中から響いてくる、さながら戦場の中に迷い込んでしまったかのようで……いいや、これは――
(さながら、とかじゃなくて――ほんとうに……?)
拓未は、ぱらぱら……と頭上から
人間だった。
それが遠投されるボールのように宙を舞っていて、そして建物に
そして、姿が消えた。それは拓未の眼にはもはやその動きが捉えられなかっただけで、実際はそいつ――戦闘用合成人間ミラー・ショートは地面を蹴って跳躍していたのだった。
そのまま反対側の建物の壁を蹴って、物陰に飛び込んで――姿を消した。
しーん……と静寂が周辺に落ちる。
「な、ななな……なんだよ、今の……」
拓未が
「…………」
空を見上げると、そこには一人の男が立っていた。
空に……立っていた。
宙に浮いている、という感じではなく、空に見えない床があって、そこに立っているように見える。
人間が空中に、落ちることなく居続けている――あり得ない光景が、平然とそこにあった。その男――フォルテッシモは下を向いて、拓未の方を見た。
「…………」
特になんの感情もない、平然とした眼をしている。拓未は
「…………」
「…………」
二人とも、何も言わない。フォルテッシモが何を考えているのか、当然、拓未にはわからないが、それよりも拓未は、
(なんで……僕は今、この人と見つめ合ってんだ?)
と、自分の思考さえよくわからなくなっていた。混乱しているのかも知れないが、それにしては妙な平静さがあった。
(なんか――この人って……)
相手の眼を見ていると、奇妙な納得がある。何をしているのか、本能的に察せられるような感覚が……なんなら、共感がある。
何をしに、ここに来たのか――それが理解できるような不思議な感覚があった。どこかつまらなそうな顔をしている男と、拓未はどこか似ているような――。
「ふん――」
フォルテッシモが拓未を見ていたのは、ほんの一瞬だった。彼はすぐに視線を上げて、そしてどこへともなく、また飛んでいってしまった。
拓未はぼんやりと、空を見上げていたが、急に力が抜けて、へたへた、とその場に座り込んでしまった。
そして――その指先に生暖かいものが触れる。
手をかざすと、そこは真っ赤に染まっていた。
血だった。
さっき頭上を通過していったミラー・ショートから飛び散った負傷の出血だった。彼はすでに全身ずたずたで
「う……」
拓未はがたがたと震えだした。やっと自分が置かれている事態を認識し始めていた。
(こ、ここは……安全な廃墟なんかじゃない……おそらく、最初から――)
こういうことに利用するために、意図的に放置されていたのだ。ここは見捨てられた場所なんかではない、ここは――
(危険なものを抹殺する〝処分場〟だ……!)
拓未は立ち上がろうとして、転んで、なんとか身を起こす。奥歯がかちかちと鳴っていた。これまでの甘えた考えが逆に牙を
(に、逃げないと……!)
走り出そうとするが、足がもつれてうまく動けない……。
*
空高く上昇したフォルテッシモの胸元から、彼にだけ聞こえる声が響いてきた。
〝おいおい、今のガキ――放っておいていいのか? 巻き添えで死んじまうんじゃないのか〟
それは彼の首に掛けられた、エジプト十字架のペンダントから発せられている。
「別に――どうでもいい」
フォルテッシモは素っ気なく呟くと、声は、けらけらと笑って、
〝いやいや、おまえは気にしてる――だからオレの声が聞こえる気がしてるんだから。このオレ〈エンブリオ〉は受け手の精神に反応して
「――――」
〝あの敵が人質に取ろうとか思うヤツだったらどうする? 色々と面倒だし、あの付いてきてるカチューシャとかいう娘も、目撃者は消せ、とか言ってくるかもな〟
その声に、フォルテッシモは、ふん、と鼻を鳴らして、
「どうするのか決めるのは、連中じゃない――この俺だ」
と言うと、ふたたび戦場へと降下していく。
*
そして、その敵の方には、そんなことを考える余裕さえなかった。
(く、くそっ……なんてヤツだ――!)
ミラー・ショートは戦慄の極みにあった。
フォルテッシモが、あまりにも強すぎる。
既にサーチから敵の性質を示す波動は受け取っている。彼はそれを打ち消す衝撃波を相手に打ち込めばいいだけのはずだったが――それができない。
(あまりにも隙がない。接近することさえできない。あいつは背中に眼でも付いているのか?)
彼ら双子が統和機構から危険視されたのは、敵の能力を模倣し、自分でも使えるようになるのではと疑われたためだったが、実際にはそんなことはできない。相手の肉体を、その内部波動を
(それを、やるしかないのかも知れない――サーチが分析して、俺に伝えてくれたフォルテッシモの固有波動を、俺自身の身体に起こして、ヤツの能力を我が身で再現させる――それしか道はないのでは――)