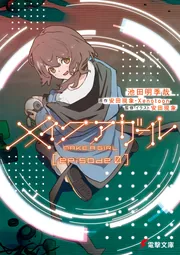第二章 ENCOUNTERING ①
僕はニンジャにでもなった気分で、できるだけそっと、そのガラスの扉を開けた。
城北大学は歴史ある大学である。いかにもな古びた大講堂のようなものも写真で見たことがある。てっきりそういったところで最初のオリエンテーションは行われると思い込んでいたのだが、どうやらそうではないらしかった。
その建物は、ほとんど全面がガラス張りの建築物だった。四角い格子にガラスが嵌め込まれたもので壁が構成されていて、それが荷重を支えているように見える。実際にはどこか別の場所で全体を支えているのだと思うが、未来的な印象を与える場所であることは確かだった。
後から気づいたのだが、これはどうやら大学院棟であるらしい。
先進的な研究をするのにふさわしい、未来的なデザインの建築物、というわけだ。
僕の後ろからは、そろそろとモンスターのぬいぐるみを抱えたままのソナタが入ってくる。
壇上では年老いた教授がなにかを話していた。
僕たちは壇上に注意が向いているのをいいことに、ひっそりと席につこうとする。
こちらに目線を向ける者はいない。
ひとりを除いては。
「初! お前、結局間に合わなかったのかよ!」
ひそひそ声でそう語りかける庄一に、僕は同じく絞った声で返す。
「いろいろあったんだ」
「いろいろってなんだよ!」
「いろいろは……いろいろだよ」
そこに小さく手をあげて、ソナタがおずおずと割り込んでくる。
「す、すみません、わたしのせいで……」
庄一はきょとんとした顔で、彼女の顔を見つめる。
「だ、誰?」
「えっと、さっきこの子が刺さってて」
どう説明したものかわからず、僕は簡潔にそう告げる。
「刺さっ――まあいいか。俺は高峰庄一。よろしく」
「あの、はじめまして。深森ソナタ、です。よろしくお願いします」
できるだけ小さな声で話そうとはしていたが、それでもうるさかったらしい。前に座っていた生徒に注意され、僕たちは気まずい顔で黙り込む。
まあ、せっかく最小限の遅刻でなんとかなったのだ、教授が話していることにちゃんと集中しようと、改めて耳を傾ける。
「――ということで、みなさんには次世代を担う人材であることが求められているわけですね。そう言われてもね、責任取れないよと困るかもしれないですけども、少なくともスポンサーである政府としてはそう考えているわけです。
老教授は、湖上、と自分のことを名前で呼んだ。話し声が聞こえていたのか、こちらにちらりとだけ目をやったが、そのまま話を続けている。
その老教授のことを、僕はよく知っていた。
応募する学生目線でいえば、湖上教授から直接指導を受けられるというのが、この〈次世代高校生プログラム〉の重要なセールスポイントのひとつだった。今、日本でもっとも優れたロボット研究者は、と聞かれたら、真っ先に名前が挙がるだろう。
僕は改めて、湖上教授を見つめる。髪のなくなった頭には、講堂の照明が薄く反射している。それまでの業績を背負っているかのように下がる瞼と頬は、さすがに年季を感じさせる。しかし洒落たスーツに身を包み、背筋をまっすぐ伸ばして朗々と話すその知的な姿は、御年85歳の高齢とはとても思えなかった。
「さて、肝心のコンペティションの内容ですが。みなさんはなにもわからないままここに連れてこられているはずです。内容は意図的に伏せてきました。サプライズというやつです」
隣でソナタが息を呑んだのがわかった。庄一は、そう来なくちゃという顔でニヤニヤ笑っている。こいつの図太さは呆れるばかりだが、メンタルの強さという意味では長所でもある。
「先ほども申し上げましたけれどもね、本プログラムではみなさんに次世代のロボット工学分野を牽引していっていただきたいと、そう考えているわけですね。そこで湖上が必要だと思うものはふたつあります」
教授は細かな皺と血管が目立つ手を胸の前にあげて、まず親指を立てる。
「ひとつは競争です。研究者なんて一斉に迷路に放たれたネズミみたいなもんですからね。まあ、湖上はここに立っているわけですから、一応は運良くチーズに辿り着いた側のネズミです。大きな年寄りネズミですね」
そう言って、げっ歯類のように前歯をむき出しにして見せた。
講堂はくすくすという控えめな笑い声に包まれる。
僕はとても笑う気にはなれなかった。
その意味では、僕は一度もチーズに辿り着いたことがないネズミなのだから。
「いや、笑い事ではありませんよ? 1位の特典はご存知でしょう。パイは限られているわけですから。まあ、ルールはシンプルです。次世代のロボットを構想し、そのデモを作り、発表すること。それだけです。プレゼン一発、デモ・オア・ダイ。……この言葉もずいぶん古くなってしまいましたがね」
なんだそんなことか、あるいは、そりゃそうだろう、という空気が、講堂を支配する。
ロボット工学分野なのだ、ロボットを作るに決まっている。サプライズというほどでもない。
僕もこのときは、安堵に近い感情を抱いていた。
雲行きが怪しくなったのは、湖上教授が親指に続いて、人差し指を立ててからである。
「さて、それはそれとしてですね。本当に競争に勝つためには、ひとりで戦うのはいいこととは言えません。大事なのは、チームを作る力、そしてそれを走らせる力です」
そう言って、湖上教授は手をくるりと回し、中指、薬指、小指を立てる奇妙なジェスチャーを示した。
「なので、コンペティションは3人1組のチームで参加してもらいます」
生徒たちは、静まり返った。
まさか個人戦ではないとは。
3人。
その数字に、僕の頭は、望むと望まざるとにかかわらず、フル回転する。
次に湖上教授がなにを言うか、僕はすでに推論していた。
チームを作る力。チームを走らせる力。それを試すということは、つまり――
「もちろん、特典は1位となったチームの全員に与えられます。デモのプレゼンテーションも必ず全員で参加してもらいますからね。……おっと、みなさんの疑問、わかりますよ。どうやってチームを組むのか? いいチームを組みたいですよね。ですが、それもまた実力です。ですので――」
嫌な予感は、僕の脳から電気のように足を伝って、床を走り、湖上教授の口から発せられる。
「――今からみなさんに、3人組を作ってもらいます」
やっぱり、か。
悲鳴に近いざわめきが学生たちから上がる。
「すでに結果通知ページから、履修システムにアクセスできるようになっているはずです。チームができたらシステム上で登録しておいてください。さて、今日はここでおしまい――ん?」
湖上教授が話を止めたのは、壇上に教職員と思しき誰かが上がってきたことに気づいたからである。そのまま湖上教授は、その人の耳打ちを受け、何度か小さく頷く。
「ふむ……間に合わなかった人がひとりいるようです。まあ、おそらく来ないんじゃないかなと個人的には思いますけどね。そういうわけで、ひとつだけ2人のチームができます」
欠席1名。ひとつだけ2人のチームができる。
それはあまりにも、重大な情報だった。
湖上教授は、目を細める。
「それでは若きネズミのみなさん、がんばってくださいね」