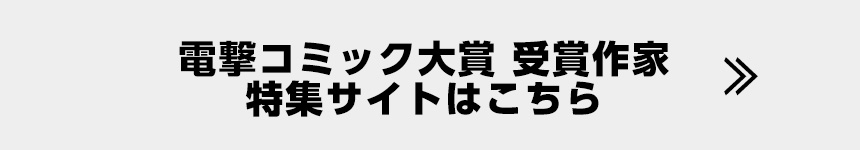ひきこもりの弟だった 特別書き下ろし番外編
◆
目が覚めると夕方で。
まだ胃の中に食パンが残っているような気がする。
しばらく布団の中でぼうっとしていた。
隣の部屋は、しんとしている。
俺は部屋を出た。
まだ誰も帰っていない。
居間のテレビを点ける。
空っぽの居間に、バラエティの笑いが弾ける。
チャンネルを変える。
ニュース番組。桜の開花予想と、中学生の自殺。
チャンネルを変える。
通販。どんな汚れもきれいに落す洗剤。
チャンネルを変える。
母さんが、仕事から帰ってきた。
「おかえり」
「ただいま。もう夕飯にしましょう」
「……啓太は?」
「今日で最後のバイトだって」
そうだった。昨日言っていた。
ファミレスのバイトがある日は、啓太はそこで食べてきてしまう。
母さんがスーパーの袋から取り出したコロッケをレンジで温め、春雨サラダの蓋を開ける。
俺は炊飯器を開け、朝用意した三人分の米を二つの茶碗によそった。大分余った。
ソースを垂らしたコロッケを端から削るように、少しずつ食べ進めていく。
「……そんなに食欲ないなら、病院に行く?」
どっちの病院を言っているのだろう。
普通の病院だろうか。精神病院だろうか。
「行かない」
どちらにしても、行きたくない。
部屋に戻る。
少し迷って、窓を開ける。
冬と春の入り混じった風が、部屋を充たす。
月が出ている。
静かな夜道に、靴音が響く。
見ると、同い年か少し上くらいの、スーツを着たサラリーマンだった。
俺は窓を閉め、パソコンの前に座った。
動画サイトで、好きなバンドのライブを見る。
音が空回りして、俺の中まで届いてこない。
イヤホンを外す。
妙にじっとり、のろのろと時間が進む。
啓太が、帰ってきた。
隣でがさがさ物音が聞こえる。
この音を聞くのも、今夜で最後だ。
そう思うと、上から押されたみたいに、ぐっと胸が歪んだ。
……正直、啓太が出て行ってくれることにほっとしている。
啓太と接していると、すごく疲れる。
自分一人で育ってきたような顔をして。
見限った相手のことは人間扱いしない。
自分勝手で傲慢な、すごく嫌な奴だと思う。
何様だよ。
何をしても、何をやっても、無視、無視、無視、無視、無視。
俺がお前に何かしたか。
どうして人に対してそういう態度が取れる。
お前みたいな奴がいるから、世の中が、生き辛くなってるんだ。
午前零時。
啓太が寝た。母さんも寝た。
静かな夜。
静寂の音がする。
音が、内側で糸を引いて、どんどん膨れて、頭の中が、ひっちゃかめっちゃかになる。
啓太が、寝返りを打つ微かな音がした。
白く光る、パソコンの画面。
はっとする。
何かをしたいと思う。
でも、何をしていいかわからない。
じりじりと時間が進む。
夜が白む。
……また、朝がくる。
啓太がごそごそと起き出して、部屋を出る。
トントン、とドアが叩かれる。
「弘樹、朝ごはん食べないの?」
母さんの声。
「……ヒロくん?」
「もう少ししたら、食べに行く」
午前八時。
啓太が部屋に戻って来る。
午前九時。
ごそごそと、啓太の部屋で音がする。
午前十時。
じりじりと、時間が進む。
午前十一時。
ぎぃ、と啓太が部屋を出る音がした。
ずん、と心臓が強く収縮した。
どうする。
立ち上がり、ドアの前に立ち尽くす。
ドアノブに掛けた手が、動かない。
「ヒロくーん、ヒロくーん、啓太の旅立ちよ! 一緒に見送りましょう!」
母さんが呼んでいる。
母さん、お願いだ。
もう一声。
もう一声で、俺は動ける。
俺は啓太のことなんてどうでもよくて、けれど、母さんがしつこいから仕方なく――。
そういう、大義が欲しい。
「いや、いいって」
心底嫌そうな、啓太の声がした。
それが、それこそナイフみたいに冷たく胸に刺さった。
俺は音を立てないように、ドアを細く開けた。
母さんが車を準備する、というようなことを言って、先に玄関を出たところだった。
お別れが解っているのだろうか。トムが、ひんひんと鼻を鳴らしながら啓太にすり寄る。
啓太が静かにトムを撫でている。
玄関までの数メートルの距離が、信じられない程遠く感じる。
啓太は知ってはいないだろう。
お前、知らないだろう。
覚えていないだろう。
お前のハイハイを初めて見たのは俺なんだ。母さんじゃない。俺なんだ。あの時、啓太は俺に向かって懸命に這ってきたんだ。それでな、お前は笑ってた。あと、歯が生えてきた時も、俺が一番に見つけた。あとな、字を教えたのも俺だ。
お前の初めてに、いつも一番に気付いたのは全部、俺だ。母さんじゃない。俺だ。
なあ、啓太。知らないだろう。お前の成長を一番近くで見てきたのは、俺なんだ。
だから、どんなに嫌がられても。俺はお前の兄貴だから。だから、やっぱり、お前がこの家を出て行くのなら、俺が見送る責任があるんだ。
なんとか部屋を出る。そして、
「うわぁ、もしかして愛犬との感動のお別れの最中かな?」
自分の口から出てきた言葉に愕然とする。
啓太がこちらを見た。
俺はニヤッと笑った。
違うんだ。
こんなことを言いたいんじゃなくて。
やめろよ。その、ゴミを見るような目。
だって、他にどうしたらいいんだよ。
――お前、俺のこと嫌いだろう。
どんな風に接したって、お前は嫌そうにするじゃないか。お前、俺のこと、全否定しているだろう。
でも、お前にだけは、弱さは見せられないから。お前の前で傷付いた顔なんて絶対にできないから。笑うしかないんだ。
お前が俺をどんなに軽蔑しても、へらへら笑っているしかないんだ。
啓太は無言で靴を履き、背筋を伸ばすと、仕上げでもするように無言でトムの頭をポンポン、と叩いて床から荷物の詰まった大きな鞄を持ち上げた。
その後ろ姿を見て、啓太の背が随分と高くなったことに気付いた。
啓太が玄関のドアノブに手を掛ける。
行ってしまう。本当に行ってしまう。
そのことが、急激に実感となって胸に迫って来た。
嘘だ。嘘みたいだ。
俺の、弟が。あんなに小さかった、毎日顔を突き合わせていた啓太が。遠くに。この家を出て行ってしまう。
俺を必要としなくなった弟が。
小さい頃のお前は、泣き虫だった。俺がいないとダメだったんだ。四六時中俺の後をくっついてきていたのに。
「啓太」
無視。
もう、ゴミを見るような目すらも向けてくれない。
俺は誰よりも、お前のことを理解していたはずだった。
でも、お前はどんどん変わっていくから。
今はもう、どうやってお前に接したらいいのか解らないんだ。
ずっと解ってた。お前が俺を嫌っていることも、俺を避けていることも。
だから余計、どうしていいか解らなかった。
ぎい、とドアが開く。
本当に行ってしまう。
「がんばれ」
振り返った啓太は、きょとん、としていた。
遅れて、俺の耳に自分の言葉が届いた。
一瞬、全てが溶け去って、俺たちは兄弟として見つめ合った。
啓太の顔には確かに昔の面影があった。
だから、言えた。
「啓太、がんばれ」
お前が出て行く先が、どういう場所かはわからないけれど。
がんばれ。
「ああ」
啓太は短く頷くと、ドアを開け、今度こそ行ってしまった。
車の音が聞こえなくなるまで見送る。
……言えた。
俺はその場で、しゃがみ込んだ。
少し休んで、ふらふらと部屋に戻る。
いつもならもうとっくに眠っている時間だ。
身体がしんどい。
クタクタの布団に入る。
昼間なのに、静寂の音がする。
隣の部屋、啓太の部屋からはもう、なんの音もしない。
と、思ったら、トン、と音がした。
忘れ物でも取りに来たのか?
布団を跳ね上げ、ドアを開ける。
そこにいたのは、トムだった。
トムが啓太の部屋をひっかいている。その尻尾が、くたりと萎れている。
「そうか、トム。お前、寂しいのか」
クン、とトムが鼻を鳴らした。
「ずっと、啓太と一緒にいたもんな」
俺はトムをぎゅっと抱きしめた。
「……置いていかれちゃったな」
トムが、ぺろ、と俺の頬を舐めた。