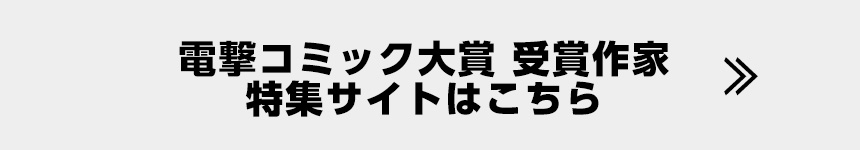キネマ探偵カレイドミステリー
事の顛末を知らせに、俺は四度目の正直で嗄井戸の家へ向かった。当初の目的は何処へやら、である。こんなことになってしまった俺を、高畑教授はどう思っているんだろうか? そちらの方にも報告に行かなくてはいけないが、まずはこっちからだろう。
インターホンに対する反応が早かった。がちゃりと開いた扉と覗く白い頭に安心する。嗄井戸の方も訪問され慣れてきたということだろうか。
「……奈緒崎くん」
「嗄井戸。入っていいか」
「……構わないよ」
ぎこちなくなりながらも、俺は嗄井戸の部屋の中に入った。図書館のようなワンルームは、以前より更に綺麗になっているように見えた。
「片付いてるな」
「お金を払って掃除に来てもらってるから、定期的に綺麗になるようになっているんだ」
「お前の家、お手伝いさんまでいるのか……バブリーだな」
会話しながら俺は素早く嗄井戸の頬の具合を確認した。随分腫れが引いている。この分だと、その内すぐに元通りになりそうだった。それにいくらかほっとする。
リビングのスクリーンでは珍しく映画が掛かっておらず、白いのっぺりとした画面がこの部屋をもっと寂しくさせていた。
ここも寂しい部屋だ。常川さんの家に行ったときと同じ感想を抱いた。物が大量にあるからわからなかったが、この部屋はなんだかとても寂しい。ここに、嗄井戸はいつも一人でいたのだ。
「それで、何しに来たんだい?」
ソファーに座りながら淡々と尋ねてくる嗄井戸に、俺は常川さんの事件の顛末を話した。常川さんは結局自首をして、所有していたフィルムは全て、東京国立近代美術館にある、フィルムセンターに寄贈されることになったこと。あと、パラダイス座は他の人の手に渡り、少しの休業を経てまた営業再開する予定だということを告げた。
この話を聞いた嗄井戸はここ最近で一番嬉しそうな顔をしていたので、それだけで何となく、俺はこの事件が解決されてよかったと思うのだった。人一人の死を隠蔽したまま営業される映画館なんて、あんまり幸せじゃなさそうだし。
「そうか……パラダイス座がね。それは嬉しいニュースだ。わざわざ報せに来てくれてありがとう」
「だって、お前の手柄だろ。今回は」
そう言うと、嗄井戸は笑うときのような、あるいは泣く手前のような、奇妙な顔を見せた。折角の美形が歪む。あんなに映画の登場人物然としていたのに。
それがなんだか、とても好ましかった。
「……あと、謝りに来た」
「謝りに? 何で」
「お前の顔、殴ったから。いや、これについては本当に申し訳ないと思ってる。……何か、お前が家族のことまで言ってくるのに苛ついて……本当に、悪い」
俺の謝罪に、嗄井戸は何も言わなかった。
何も言わずに、ただただ驚いていた。大きな目が星を散らす。嗄井戸は、今初めて自分が怪我をしていることに気が付いたかのように、頬に手を遣った。
「何か言えよ」
「……いや、意外だった。まさか謝られるとは」
「謝罪の気持ちもあるし、感謝の気持ちもある。常川さんの事件が解決したのはお前のお陰だからな」
「いや……それほどでも……」
嗄井戸は首を傾げながら、ほんの少しだけ眉を寄せた。どうやら、真っ当に照れているらしい。もしかすると、嗄井戸は思いがけず素直な人間なのかもしれない。
「……提案なんだけど」
ややあって、嗄井戸がそう呟く。
「どうした?」
「『ニュー・シネマ・パラダイス』、観ない?」
そうして俺と嗄井戸は、件の『ニュー・シネマ・パラダイス』を見た。これがまあ、恐ろしいほどよかった。ラストシーンでは、ぼろぼろ泣いてしまった。詳しく内容を書くのは野暮である。だから、ただただ俺は、アルフレードとトトに素晴らしい体験を貰ったということだけ言っておこうと思う。
嗄井戸は俺の泣きっぷりに引いていたんじゃないだろうか。勝手にティッシュを使いまくってからそう思ったのだが、驚いたことに嗄井戸の奴も泣いていた。
「映画で泣ける奴は良い奴だと思う。善じゃなくて良だけれど」
「それって、自分が良い奴だって主張してる?」
嗄井戸は答えなかった。柔らかな髪を揺らしながら、エンドロールを眺め続けている。
「俺達仲良くなれるんだろうか?」
「もう一本見てから決めようじゃないか」
嗄井戸がそう言って立ち上がった。そこでようやく俺は、この男が柄にもなく浮かれているのを知った。
了