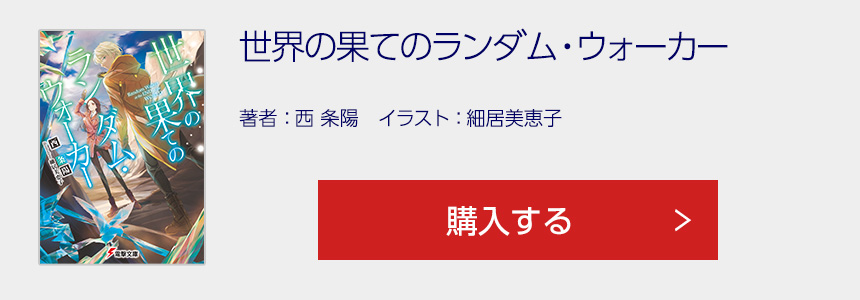世界の果てのランダム・ウォーカー
◇
空中都市セントラルの首都にある官庁街。
中央調査局のオフィスの一室で、ヨキは報告書の作成に追われていた。
現地調査があれば、デスクワークもある。ヨキは眠気と戦いながら、お堅い行政文書の形式にのっとって、報告書を作成していた。肩も凝るし、目も疲れる。しかし上司をみれば、優雅にお茶を飲んでいるのであった。
「ちょっと先輩、遊んでないでダブルチェックしてくださいよ」
ヨキは報告書を送信する。しかし、シュカは端末を操作しているものの、いっこうに確認済にならない。ゲームでもしているのかもしれない。ヨキはあきれながら、シュカの席にゆき、後ろから画面をのぞきこむ。
「いつの間に撮ったんですか」
画面には、ユヒテル山脈を旅していたときの画像が表示されていた。アリスの前でカメラ付きの端末を出すことはできない。それにもかかわらず、いつのまにかシュカはたくさんの画像を撮っていたようだ。
「こっそりとね。ま、旅の思い出だよ」
次々に画像をスライドしていく。
「不思議に思うことが多くなると、知の贈り物が授けられる」
シュカが脈絡なくいう。アリスの横顔が映し出されたときのことだ。「なんですか、その言葉?」とヨキが聞くと、シェリオロールの先住民の格言だという。
「セントラルとシェリオロールの技術力の差は、積み重ねた時間の差でしかない。知的好奇心さえあれば、いつかはたどり着くんだ。アリスのような娘がいれば、地上もそのうちセントラルに追いつくよ」
「かもしれませんね。ところで先輩、そのカテゴリーは?」
シュカは思い出に浸りながらも、手際よく画像を分類していた。フォルダが二つある。フォルダAとフォルダB。石化した動物の画像をそのフォルダに収納している。山で石像になっていた動物の画像をAに、湖で石像になっていた動物の画像をBに入れていく。
「なにか違いでもあるんですか?」
「よく考えてみなよ」
シュカの顔つきは真剣だ。
「湖で石化するには、長時間、あの強アルカリ水に浸からなきゃいけない。死んだ動物や湖に落ちて溺れた動物ならそうなるのもわかる。けれど、生きて元気な動物だったら、足をつけた時点ですぐに湖から離れるよ」
「たしかにそうですね」
「湖で死んだ動物が石灰化するのならわかる。けれど、山のあちこちで石化していた動物はどう説明すればいいのかな。石化の原因が湖なのだとしたら、そこから遠く離れることはできないはず。しかも、山のあちこちにあった石像は、今にも動き出しそうな姿勢をしていた。生きたまま湖に落ちた? 説明がつかないよ。そういうやつがカテゴリーA。どうみても湖で石化したと思われるやつがカテゴリーB」
シュカが、あるスライドにきたところで手を止め、画面を凝視する。
赤い湖のわきに、ヨキが立っている画像だ。特に不審な点はないようにみえる。しかしシュカのまなざしは鋭い。
「そもそも、なんで僕のアップを撮ってるんですか」
「疲れた顔が面白かったからだよ」
「部下をいたわりましょうよ」
シュカがその画像の、ヨキの背後をどんどん拡大していく。ヨキの顔はすぐに画面の外に追いやられる。何の変哲もない平地がアップになり、鮮明に表示されていく。小さな点がある。最初は汚れのようにしかみえない。しかしそれが拡大されるにつれ、形をあらわしてゆく。
人だ。人がいる。
赤ん坊を抱いた女の人が立っていた。あの山小屋にいた女性だ。
どうしてここにいるのだろう。まさか、ついてきたのだろうか。けれど、なんのために?
ヨキはその状況に狂気を、そして背筋に冷たいものを感じる。
シュカはなおも拡大をやめない。女の人をみたかったわけではないらしい。彼女の胸元をさらに拡大する。布に包まれた赤ん坊に焦点が定まる。ヨキが山小屋にいたときはいつも眠っていた赤ん坊。しかし画像のなかでは起きていて、目を開いている。
赤ん坊の瞳は暗黒で、画面越しにこちらを睨みつけていた。
ヨキは頭をかく。
「もしかして、僕たち危なかったんですかね?」
シュカは薄く笑う。
「かもね」