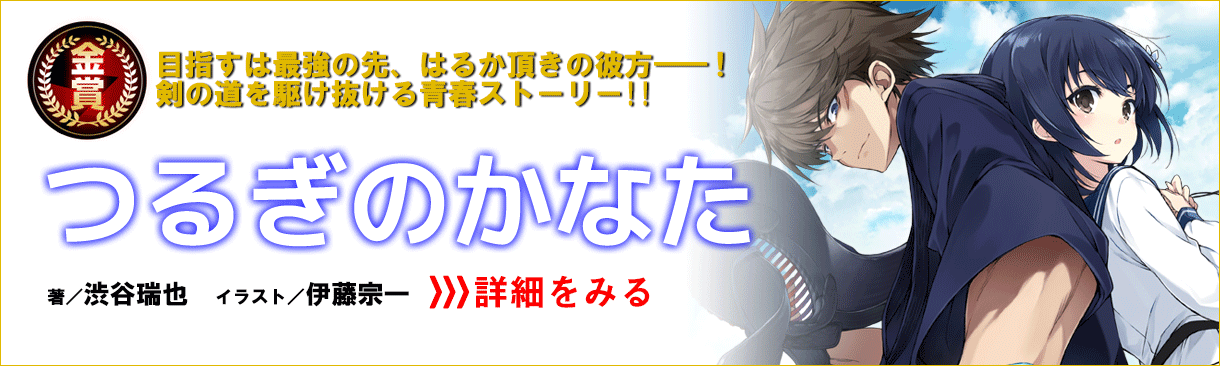二合目 吹雪、快晴、冬模様
吹雪が、剣を構える。
宝石のような瞳の中で火花が散った。その火種はやがて防具を纏った全身に灼熱となって行き渡り、ついには烈火の叫びとなって空気を裂く。
「ヤぁああああ―――――――――――ッ!!」
対峙する者は声を失う。死にたくないと後ずさる。しかし覚悟を決めた雪の剣姫に、慈悲などありはしなかった。
「めェんッ!!!」
氷を叩き割るような重い一刀が、相手の自信ごと真っ二つ。疾風のごとく相手の隣を抜き去って、吹雪は次を問うため振り返る。足りない。足りない。……早くしろ!
「ふ、吹雪、ストップ! 竹刀が、壊れています!」
諫められ、自らの手に握る刀を見る。確かに打突部位が砕けていた。
水を差されて苛立ちは加速するが、これでは仕方が無い。主将の言葉に従い、吹雪は納刀の動作を行った。
すぐに自分の竹刀袋のもとに駆ける。近くに居た同期の部員がぎょっとしていた。
「あんた、それ……。壊した、の?」
「うん。折れちゃうとは思わなかった。……由季さんが、打たれすぎるせい」
物足りない。つまらない。報われない。つい、戦うことをやめたくなる。
しかし、自分にはできない。早く戦場(あそこ)に戻らなければ。立ち止まっている暇など、自分にはないから。
「……吹雪ってさ~。そんなに強くなって、将来何になりたいの~?」
「何度も言った。……そんなもの、もう、ない」
新しい刀を手に取って、目の前にかざす。凍った自分の目が映ったような気がした。
「夢は、捨てたの」
溶けない氷のような言葉。吹雪に春は、まだ遠い。
× × ×
「春、だなあ。……はーあ」
乾快晴は、剣道場の床に行儀悪く背中を預けた。顧問がいないので大の字に寝転がる。
私立秋水大付属高校はスポーツ名門校で、当然剣道場もいい木を使っている。床がひんやりとして気持ちが良かった。道場の窓から吹いた春風が、快晴の頬をなぜる。
屋外の部活は、きっと外気が気持ちいい時期なのだろう。妬ましくて仕方なかった。
快晴は昼寝でもするように、綺麗な二重瞼を閉じる。最近伸びてきた前髪がどこか鬱陶しい。切る暇がないほど練習漬けなのだ。おかげで、せっかくの春なのに散歩もできていない。
「楽しくないなあ。剣道……」
春夏秋冬、快晴の剣道に対する気持ちはいつもそれだけだ。
「うるっせーぞこの馬鹿! 散々遊んどいて何言ってやがる!」
副主将、橋倉崇仁にキックされる。胴垂れを外して胴着姿だったので、もろにボディに入ってしまった。
「……痛い。パワハラですよ、橋倉先輩」
「おめーが言うな! ところ構わずパワーぶん回しやがって。ちっとは気ぃ遣えねーのか、この殺戮マシンが。俺っちにいらねー仕事増やすなよ。誰があいつらのケアすると思ってんだ? 瀧本のハゲも影下のクソガキも、糸切れた人形みてーになっちまってる。
おめーさあ、仲間の自信潰してどうする気なんだよ」
焦げ茶の髪の毛をがしがし掻いて、橋倉は顔を苛立ちに歪ませる。西欧の血が半分混じった顔立ちは端整で、どんな顔をしても人を惹きつける華々しさがある。練習場所は別だが、女子剣道部にも彼のファンは多いらしい。実力の方も折り紙付きだ。
「どうするって、どうもしないですけど……。気を遣うって、何を?」
「あんまり舐めプみてーなことして人間ぶっ壊すなって言ってんだよ、剣道星人」
「……うーん」
快晴は身体を起こし、腕を組んで考えてみる。首を傾げた。
「そんなの、弱い方が悪くないですか?」
「……はいはい、ピポパポ。また星から電波受信かよ。やってらんねー」
肩をすくめて笑われた。心外だ。だが、好意的な笑顔だと思う。少しは反省すべきなのだろうか。……でも、何を?
悩んでいると、またしても橋倉に笑われた。
「露骨すぎんだよ、おめーは。もっとバレねーようにやれ。さすがに決め技全部逆胴だけってのはやり過ぎだ。プライド砕け散るどころの話じゃねーぞ」
逆胴。その技の名を聞いて、快晴の目は輝き出す。
「一番、好きな技なんです。カッコいいじゃないですか。残心とか含めても、一番」
快晴が、汗に濡れた手拭いを右手に持って技を振った。
高い頂点から、右に向かって弧を描く。そして命中したら、胴体を裂くように手元に引くのだ。確実に殺し切るために。
「まーだからこそ、喰らった側は一生忘れねーんだけどな。俺っちも胴技は一番好きだぞ。一番強え、技だからな。……そういや、吹雪ちゃんも抜き胴得意じゃなかったか?」
「嫌な名前を出しますね。萎えるからほんとにやめてくださいよ……」
また快晴の顔が露骨に曇る。けれどそれ以上に、橋倉がキレていた。
「おめー贅沢すぎんだよ! 俺っちのゴリラみたいな姉貴と交換しろってか紹介してくれ!」
「別にあんなの、好きに持ってってくださいよ。こっちからお願いしたいくらいだ。……何が剣姫だ。かぐや姫みたいにわがままばっか言って」
お姫様の望みはひとつ。自分の敗北。だから色んな者と対戦した。
『竜の巣穴』と呼ばれた石動から来た者も、それから『鬼が棲む山』と呼ばれた御剣から来た者も。けれど今の六大道場には、望みを叶える者はどこにもいなかった。
「橋倉先輩も、挑戦しますか。愚妹の課題に」
「お? まじか? 俺っちは結構ハイスペックだぞー? クリアしちまっていいのか?」
「是非。『僕より強い人』だそうなので」
自分はもう、諦めた。だから挑んで来ないで欲しい。
そういう言外の意を置いて、快晴は道場を出ようとする。しかし途中で一つ、思い出した。
「そういえば先輩。……バレなきゃやっていいんですか? さっきの縛り」
「ん? いいさ。だってんなもん、喰らっちまう方がわりーだろ。実際俺っちに当たったか?」
快晴はむっとする。今日、唯一入れられなかった男を睨んだ。
「逆胴だけは二度と貰わねー、べろべろばー。……あとよ、おめーコレ試合で一発も打ってねーだろ。実用化もできてねーもんが当たるかよ。あんま、先輩舐めんな」
本当は打たないんじゃない。今までずっと、打ちたくなかっただけだ。
だが、それを今さら言っても負け惜しみになってしまう。……だから。
「じゃあ今度、橋倉さんに打ちますよ。逆胴」
「はーん? やれるもんならやってみな。じゃあ、なんか賭けっか?」
「そうですね。……もし入れられたら、どうしよっかなあ。そのときは」
きっと未練も、断ち切れているだろうから。
「辞めようかな、剣道。……それじゃ、次の練習があるので。お疲れ様でした」
快晴は礼をし、道場を出る。そして部室へ帰る道中で唸って考えた。
さっき怒られた理由以上に分からない、永遠の謎について。
「みんな、熱烈だなあ……。あんな妹のどこがいいんだ?」
× × ×
「へっくし!」
誰かが噂をしている。絶対お兄だ。死ねばいい。
練習での不完全燃焼も相まって、乾吹雪はぶすっと顔を燻らせる。
一年前に名顧問を迎え、一気に強豪校に名を連ねた私立お嬢様校こと、桐桜学院の稽古でも彼女は満足しなかった。剣道場で正座をした吹雪が、雑に右手だけで胴垂れを外す。練習のためにポニーにしていた髪も、同様に解いた。
烏の濡れ羽色という言葉がまさにピッタリな、彼女の瑞々しい黒髪が道場に躍る。名前のように真っ白で綺麗な肌とのコントラストも相まり、道場に残る誰もが目を留めてしまった。控えめな胸に、切なさを喚起されるほど綺麗なうなじ。それから、整いすぎな小顔。同性である桐桜部員の誰から見ても犯罪級に可愛くて、ついお近づきになりたくなる。……が。
「足りない。こんなの、全然話にならない。……舐めてるの?」
全身から迸る殺気が、誰にもそれを許さない。鋭い視線に捉えられたら最後、問答無用で斬られてしまいそうだ。吹雪に話しかけようとしていた新入生たちが、蜘蛛の子を散らすように逃げていく。
けれど同級生の三刀愛莉は、そんな殺気なんて一切気にしない。構わず吹雪の背後に忍び寄って、すぱこーんと頭を叩いた。
「……痛い。何するの、愛莉」
「馬鹿はあんただっつ~の。この万年欲求不満~。何が足りひんね~ん」
たまに出るエセ関西弁は中学の友人の影響だが、とても下手だ。上手いのは剣道と人の彼氏を盗ることだけ。武道に似つかないギャル感のある愛莉が、泥棒猫のように吹雪の隣に滑り込む。
「藍原先生との地稽古、凄かったじゃ~ん。相手はあの御剣の『殺人姫』だよ~? もう満足しときなってば」
「良くない。だってあの人、上段じゃなかった。本気じゃないのに勝っても意味ない」
「え~? ぜ~たく言うなよお姫サマ~。中段でもあの人、十分クレイジーじゃん」
「やだ。……絶対やだ! わたし相手に本気じゃないとか、絶っ対ゆるさない!」
この子、わがまま。
けれどこれほどの可愛さと強さがあれば、まあ許されてもいいのかな。
愛莉は一瞬納得しかけるが、それはそれとして、どうしても許せないことがひとつある。
「じゃあちょっとは男相手にも本気になってあげなよ~。あんた、この前ま~た他所のガッコの男子に告られてたじゃん? しかもイケメン。……え~っと。これで何人目だっけ?
へ~い、林檎~」
「ははっ、呼ばれて飛び出て! 林檎氏サーバの吹雪DBに全てお任せ!」
吹雪のお話と聞いて、少し離れたところで防具を片付けていた大貫林檎がしゅばばっと駆けてきた。
身長が高く、折れそうなほど細く痩せている彼女には、どことなくインドアの気風がある。
「告白された回数二十五回、うち男性十九、女性六、キー重複を除くと男性十五の女性三。ついでに桐桜学院(女子校)抱かれたいランキング二年連続第一位! いじょう!」
「よっ、さすが林檎氏。今度漫画貸してよね~。……じゃなくて。話逸れちゃった。この前の男、どうしたん? 吹雪、フリーだろ? 顔ジャニ系だったし、あれはいけるっしょ!」
「いらない。斬った」
冷然とした顔で一刀両断。隣で林檎が両手を合わせて南無南無していた。
「……ねえ林檎~。あたしこいつ嫌いなんだけど。見捨ててイイ?」
「ま、待って! 林檎社がクレーム対応するのでどうか他社にだけはっ!」
「ふん。別に、見捨てていい。勝手にしたらいい。……恋愛で剣道強くなるわけない。時間がもったいない。顔なんて面つけたら一緒。弱い男とかありえない。
最低でも、わたしより強くて。……それから」
その先に続く言葉が何なのか、桐桜部員ならみんなが知っている。それこそが乾吹雪を手に入れるための、単純明快にして難攻不落の無理難題だ。愛莉は諦めたように肩を落とす。
もう知らん。営業終了だ。
「林檎、二人で帰ろ~。サイゼで化学の課題やろ~よ」
「ウォルター氏の課題か、あれは中々鬼畜。でも理系ならこの林檎氏にまかせてほしい!」
「……………え? か、だい?」
吹雪がその名の如くフリーズしている。でも知らん。授業中に寝ている奴が悪いのだ。
「行くよ林檎。あたしたち友達だよな~?」
背の高い林檎とバランス悪く肩を組み、道場から去ろうとする。が、進めない。
振り返ると、宝石のような瞳を潤ませているチワワが袴を引っ張っていた。
「……ま、待って。見捨てないで。ひ、ひとりじゃ、死んじゃう……」
「……はっ。これが『剣姫』とか呼ばれてるの、マジ受けるよね~」
「大丈夫! 殿様商売アップルサポートが吹雪の高校生活を終身保障!」
愛莉は吹雪の頭を雑に撫でながら、ため息をつく。こうやって自分たちが甘やかすから、ますます剣道以外何もできなくなっていくのだ。マジ魔性の女。ああ、誰か早急に貰ってよ。
もうこの子一人じゃ生きてけないよ。なのにどんどん捻れていくよ。一体誰のせいなんだ?
「……快晴く~ん。吹雪が売れ残ったら、絶対キミのせいだかんな~?」
× × ×
「ただいまー……」
夜更け。快晴は電気の点いていない玄関に、ポケットから取り出した鍵で入る。腕時計が示す時刻は、もうすぐ零時だ。
学校の練習の後、六大道場である錬心舘に練習に行く。そうすると帰宅する頃にはこんな時間になっている。けれど今更そのことに、何の感慨も湧かない。あとは風呂に入って寝るだけだ。そして朝起きると、学校の朝練に行って、深夜ここに帰ってくるまでを繰り返す。
辛いが、仕方ない。玄関で防具を下ろして、光が漏れる居間への扉を開いた。
「おかえりなさい、快晴。お風呂湧いてるわよ。それとも先にご飯、食べちゃう?」
「じゃあ、お風呂で。……はあ。疲れた」
「いつもお疲れ様ね。……ねえ、辞めないの? 剣道。母さん、いっつも心配。そんなに生き急がなくたっていいと思う。色んな楽しいことが、他にもたくさんあるんだし」
全くその通りだ。快晴は苦笑する。
できることならそうしたい。でも、自分にはその資格が無いのだ。
「じゃあ、吹雪が許せばそうしようかな。言っといてよ」
「バカねえ。辞める気ないなら最初からそう言いなさい。……あと、直接こっちにも」
母がテレビを見ながら、ソファで寝転がっている物体を指差した。口開いてよだれが出ている、完全なアホ面で寝ている愚妹だった。着てるのは上のTシャツだけで、下は下着のみ。ついでにテーブルには食べかけのお菓子が放ったらかしだ。
快晴に頭痛が襲いかかる。
「霊長類としてクオリティが低すぎる……。これが本当に人気あるの? ありえないよ……」
「今日は難しい勉強の課題やって疲れたんだって。ころんと寝ちゃった。日曜に練習試合もあるみたいだし、稽古も気合入ってるんじゃないかしら。母さん、なんだか起こせなくって」
深い溜め息をついて、妹が散らかしたモノを片付ける。そして、ソファの前で腰を落とした。
「……萌えないゴミだなあ。今すぐ捨ててやりたいよ」
「こらこら。そんなでも、お嫁さんに行くときはきっと快晴泣いちゃうわよー?」
「旦那に同情してるんだよ、それは」
本当にどうしようもない奴だ。快晴は、仕方なく吹雪をお姫様抱っこする。
「上に捨ててくる」
抱えたまま階段を上る。途中、吹雪が身じろぎしだした。どうやら寝言を言いそうだ。こういうところだけ見れば、まだ昔みたいに可愛い――。
「……むぃ……。おにぃ、しね……」
「階段から転がしてやろうかこいつ……」
吹雪ルームを開いて、ベッドに安置する。間違っても運んできたことは内緒だ。勝手に部屋に入るなとかでどうせキレる。兄はただ、黙って見守るだけだ。
「お嫁さんに行くときか。……取り越し苦労だけどね」
後ろ手で静かにドアを閉めて、天井を見上げる。そして目を、ぐっと瞑って自嘲した。
「……早く、泣かせてくれよ。吹雪」
× × ×
「あー、そろそろ結婚したーい。どうして男できないんだろー? 見る目ないよねー、男って」
見る目あるからそうなってんだろと吹雪は思うが、暴虐顧問相手にはスルーが安定だ。
「先生。そういえば今日、どうして藤宮高校で稽古なんですか? 突然すぎて聞けなかった」
「んー? 先生の私情でーす」
時は過ぎて、今日は日曜日のお昼前。藤宮高校への出稽古当日だ。
現地集合ではなく、桐桜学院に一旦集合してから出発となった。吹雪は自分の防具と竹刀を担いで藍原瞳に付いていき、車に積み込むことにする。
後ろから、適当なことばかり言う顧問を睨んだ。身長は自分と同じくらいだから多分百六十程度。ゆるふわな天然パーマの髪は肩くらいの長さで、風に揺れると花みたいな香りがした。
「なにー、乾さん? 先生に何か恨みでもあるー? 視線、痛いよー」
時々漫画みたいなことを言ってどきりとさせる彼女が振り返る。目尻が下がった蠱惑的な顔つきは、人を堕落させる魔女のような印象を抱かせる。それに、限界突破級の胸。
吹雪は我が身を振り返って、無いものは無いと悲しみの唇を噛む。
「……むしろ、何で恨まれてないと思ってるんですか? あの稽古、人道に反する罪」
「あはー。それは、あんたたちがヘタクソなのが悪いんじゃーん。先生は、キレーにできたら五回で終わらせてあげるーって毎回言ってんのにー♪」
「婚期を逃せ。地獄に落ちろ」
桐桜名物、無限かかり稽古。最初は「五セット綺麗にやれたら終わりねー♪」とかだけ言って、いざ始まったらそんな数字は蜃気楼のように消えてなくなる。
『はーい乾さんがサボったからゼロからやりなおーし♪』
『大貫さーん、何で倒れてんのー? そっかー、また最初からやりたいんだー』
『三刀さーん、声忘れてるよー。取りに帰んなきゃー。はーい、みんなで最初からー♪』
まさに鬼畜の所業。慣れてくると、五セットと言われた時点で「おっ、今日は五十セットくらいかな?」などと悟ってみんな笑い出す。
武道という名の免罪符。関わったものは全員地獄行き。それが剣道。
「うるせー。まー、キレイな花にはトゲがあるって言うしー。しゃーないよねー?」
「可愛くて彼氏できない女には何かある。先生は、その典型」
「乾さんが言うー? それ」
「わたしは作れないんじゃなくて作らないだけ」
童貞の強がりみたいなことを言い出した吹雪に藍原は笑う。ポケットからキーを取り出し、トランクを開いた。そこで、吹雪が首を傾げる。
「先生、これ、なんですか? 一個ずつ多い。先生の?」
やけにボロボロの竹刀ケースと防具袋が、いつも見る藍原愛用のモノの隣に鎮座していた。御剣と書いてあるから道場の関係なのだろうが、使っているところを見たことがなかった。
「んーん。……それは、ゆーしゃ装備だからねー。先生には、着けられないかな」
聞いたことのない藍原の声音に振り返ると、吹雪はぎょっとした。まるで彼女が、怯えている少女のように見えて。
「どの面下げて、また起きろって言うのかな。……あたし、何もできなかったのにね」
緩くて生徒に人気の先生。厳しくて無慈悲でみんな大嫌いな『殺人姫』。
そのどれにも今の藍原は当てはまらなくて、吹雪は言葉を失ってしまう。
「……そんな顔しないでよー、乾さん。先生だって、ふつーの二十四歳なんだよ。まだまだ子供だし迷うんだってば」
「え。……よ、よく分からないけど。二十四歳は、大人では?」
「あは。先生もそう思ってた。乾さんくらいの頃はねー」
謎の防具を前に彼女は腕を組んでいる。どうやら、何かを迷っているようだった。
「……ねえ、乾さん。聞きたいことがあるの。顧問命令だよ」
「何ですか?」
「先生のこと、好き?」
「世界で二番目に憎い。大っ嫌い。わたしの楽しいJKライフ、返してほしい」
即答する。あんな稽古を付けてくる奴のことを、好きになれるはずがない。
「でも。……楽しいだけで終わるより、ずっといいから。そこだけは、感謝してます」
「うん。……うん。よし。乾さんなら、そう言ってくれると思ってたぞー♪」
藍原が、いつもの調子に戻る。防具を完全に積み込みトランクを閉じ、吹雪の方を向く。
彼女がぱぁん! と両手で自分の頬を打った。
「よし、行くよ。乗んな」
「はい、先生」
この人になら、まあ付いていってもいい。そう思える顔だった。
藍原がエンジンのキーを回す。火が点いたようなその音と共に、彼女が言った。
「ぶつかってきてくれてありがとうね、乾さん。……だから、次もお願い。ぶつかってあげて。そしたらきっとね。……きっと、待ってるから」
「……わたしに、何が待ってるの?」
何でも知っている大人に、正解を問う。
「なーいしょ。妬けちゃうから、教えてあげなーい♪」
返ってきた答えは、満開の桜のように咲き誇る、明るい子どもの笑みだった。
< 前へ|・・・|2|3|4|5|6|7|8|・・・|次へ >