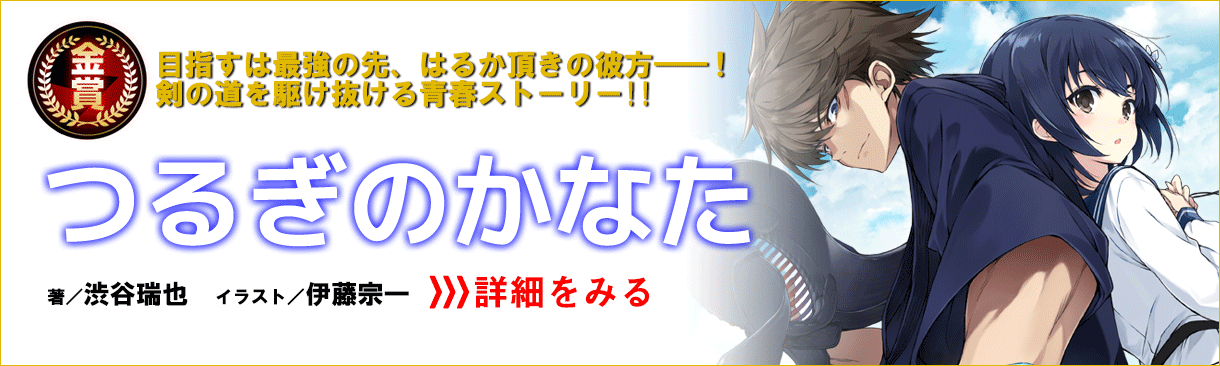一合目:だいじなもの
「じゃあそろそろ学校行くな、かーさん。今日は仕事、どんな感じ?」
「七時……、いや待て。やはり定時にオフィスから出るぞ!」
「え、ええ? かーさん、昨日も定時だったじゃん。無理しなくていいんだぞ」
早朝の玄関。悠はカバンを背負い、ドアノブを握りながら、真新しい靴の爪先をとんとん鳴らした。うん、履き心地がいい。早く都会を歩いてみたい。
悠が笑って頷き振り返ると、同じ顔をした母がいる。しっかりと、首を横へと振っていた。
「無理なんかしていない。今日は、息子と一緒に夕ご飯を食べたいんだ」
「……うん、わかった。晩ご飯、楽しみにしてる。それじゃ、行ってき――」
いつもの癖で返事を待たずに家を出ようとする。が、後ろから肩を叩かれた。
「待て、悠。……忘れ物だ。作ってみた」
小柄で凛とした母が、照れ臭そうな顔で右手を突き出している。その手には、乱雑な風呂敷包みのお弁当箱があった。
悠が目を丸くする。それから同じ照れ臭そうな笑顔を作って、大事そうに、両手で母の愛を受け取った。
「いってらっしゃい、悠。頑張ろう、お互い」
「うん、かーさんも。……じゃあ、行ってきます!」
意を決して、扉を開く。
水上家の、新しい朝が始まった。
× × ×
県立藤宮高校二年E組の一年間もまた、この朝から始まる。新学期一発目のホームルームはクラス全員の自己紹介だ。ひとり、またひとりと個性に富んだ挨拶をしていく。
城崎俊介は、普段朝方は閉じている目を大きく見開き、その様子を見守っていた。きょろきょろとクラスを見渡してみる。
「……んー? あんなやつ、うちの学年にいたっけか?」
ワックスを付けた髪を触りながら記憶の中を探してみたが、心当たりは見つからなかった。ちょうど、自己紹介の順番が奴に回る。城崎はクラスメイトに交じって拍手を送った。
教室の一番奥の窓際席で、その男が立ち上がる。
「えっと、みつ……、じゃない。水上悠です。よろしくおねがいします」
背筋がぴしっと伸びた、綺麗な立ち姿。
まず何よりそれが、城崎の印象に残った。整った顔立ちや優しそうな笑顔、若干アシンメトリーに伸びた茶色っぽい前髪がその次に目立つ。穏やかな雰囲気は、昼寝中の猫のようだ。
驚いたのは、身長がそれほど高くないことだった。
平均ちょい上の自分より微妙に低いくらい。なのに、なぜかその姿が大きく見えた。
「実は俺、三月からこっちに越してきたばっかの転校生です。なんで、東京のことが全然わかりません。色々教えてくれたら嬉しいです。趣味はランニングと散歩、落語鑑賞……かな。あと、特技はストップウォッチ止めです。五分までなら、絶対誤差一秒以内にできます」
「はは、まーじで? ムダにすげーけど、それって何に使うんだよ」
城崎はリアクションを取ってやる。いいヤツそうだから、早くコイツが馴染めたらいい。
そう思っての軽いアシストを、転校生はしっかりと受け取ってくれたらしい。片目を瞑ってから、温和そうにへにゃへにゃ笑っていた。
「ほんとにな。……で、最後に苦手なことか。苦手なことは、友達を作ることです。頑張るので、どうか仲良くして下さい。よろしくお願いします」
こいつと友達になってみたい。
理屈じゃなく城崎はそう思い、チャイムと共に席を立って話しかけていた。
「よー、転校生。オレ、城崎俊介なー。チャラいんで下で呼んでくれると嬉しいぞ」
「お! さっきはアイスブレークありがとな。助かった……、俊介。俺、水上悠な」
ちゃんと呼んでくれて、結構嬉しい。そう思っていると、城崎の隣めがけて元気な突風が吹いた。エネルギーの正体はすぐに分かった。だって、喋る前から既に雰囲気がやかましい。
「おはようテンコーセーくん! うちも混ぜて! うちもちっひとかちっひーって呼んでー!
二宮千紘、二宮千紘やで! 清き一票よろしくおねがい!」
ベリーショートに黄色のヘアピン、明るくうるさい関西弁。全人類は大体友達の千紘の圧を、悠はさらっと笑顔で迎えた。
「よろしくちっひ。関西弁かわいいな」
「せやろ! でも惜しい! それはな、関西弁じゃなくてうちが可愛いんやで!」
「うん、そうな。ちっひ可愛い。元気だし。俺は好きだぞ」
照れずに、そう捌かれる。千紘ロボは動作を停止し、簡単にオーバーヒートした。
爽やかな雰囲気でチャラさがないから、嫌な感じが全くしない。
「……ぼけ殺しやめてや。照れるやんか……」
さっきまでのやかましさはどこへやら。千紘の蚊の鳴くような声に、城崎は笑った。
「やるなー悠。ちっひー、防御クソザコなんだよな。一目で分かったカンジ?」
「いや、なんとなく。でもそういう勘はいい方だと思うよ。……ちっひかわいい。かわいい!」
「や、やめてや! どつくぞ! じゃあうちはテンコーセーくんのこと、ゆーくんって呼ぶからなっ! ほら女子から下の名前やで、照れるやろー?」
「二人のときは呼び捨てでいいからな、『千紘』」
「いやぎゃぁああっ! やめて! お願いやめてっ」
気が合いそうだな、と城崎は笑う。定番の、あの質問をしてみたくなる。
「なー、悠。向こうでは部活、どんなの入ってたんだ?」
「……あー。中学では一年ぐらいやってたけど、張り合いが無くてやめちゃった。以降ずっと帰宅部。俺は中々やるぞ。全国大会も優勝した」
「めっちゃ覇気なさそうな大会やなソレ……。でも、そうなんや! ゆーくん帰宅部かぁ!」
千紘の目がきらんと光る。城崎がそのアイコンタクトを受け取った。
了解。このチャンスは逃せない。悠が少し目を逸らしてたのが気になるが、今は些細な問題だ。細かいことはいいからとりあえず押しまくろう。
「悠、さっき勘がいいって言ってたよな! オレ、何部だと思うよ?」
「んー……。よしわかった、軽音部!」
「あー、ゆーくん惜しい! あともうちょいやったのに!」
千紘のわざとらしい言葉に合わせるように、城崎も大げさに頷く。じゃあ何部なのって突っ込まれたらこっちの負けだ。勢い。とにかくそれのみだ。
「なあ悠、オレたちの部活見にこねえ? 実は、ちっひーと一緒んとこ入ってんだよ。それで、春だから見学に人連れてくるノルマとかあってさー。協力してくれるとすげー助かる」
「転校したばっかやからヒマやろ? お願い! 来るだけ! 先っちょだけやから! もしほんまに来てくれたら、今度の日曜、きのっちとつきっきりで東京とか案内するから!」
「……お? それ惹かれんなあ。見に行くだけでいい? それだけで東京案内してくれんの?」
食いついた。城崎の目が光る。この感じならあと一押しだ!
「するする! ヨユーでする! 東京なんか電車ですぐだから遠くもない。エンリョすんな!」
「……じゃあ、いいぞ! 交渉成立だな。最近ずっと暇だし、部活に入んのもいいかもな」
はい、言質取った。もう逃げられないざまあみろ。千紘と城崎の顔が邪悪に歪む。
「そういえば、二人って何部なんだ? 聞くの忘れてた」
一手遅い。どんくさい。でも、鍛えたら――きっと強くなれるよ転校生!
「「剣道部!」」
× × ×
「何が惜しいだよ。最初と最後の文字しか合ってなかったじゃん……」
その夜。悠は食卓で愚痴をこぼしながら、夕食のハンバーグを食べていた。大きさは不揃いで、焦げてるモノもあれば生焼けのモノもある。宣言通り定時退勤の母親製だ。
「ん? どうした悠、何か言ったか?」
「いや、何も。……あ、こら、携帯見ながら洗い物禁止。また仕事か?」
「ち、違う、これは仕事じゃない。そう、プライベートなやり取りだ」
プライベート? 座右の銘はワークワークバランス、水上綾華にそんなもんあったっけ?
そう思ったけれど、悠は言えない。
今日もやっぱり、この時間帯に母がいることに対して違和感を感じてしまっていた。というか何を話せばいいんだろう。無言を埋めるように、意識的に話す。
「こっち、人多いよなー。電車とかやばすぎるんだけど。俺、近々チャリ通にしようかな?」
「何キロあると思っているんだ……、と言いたいが。息子には杞憂か。しかし別の問題もあるぞ。都会は信号が多いんだ。直線距離で考えると、すぐに遅刻するぞ。通行人も多いし」
「多すぎると何でも嫌になるよな。そういうわけで、ちょっとは反省しろよなかーさん」
悠は椅子の背もたれに体重を預けて、広々ゆったりのはずのリビングを指差した。
圧倒的に、狭い。モノが多すぎるのだ。
「持って来すぎだ! 段ボール地獄かよ! もっと捨てても良かったのに」
「だ、だって、もったいないじゃないか。『だいじなもの』は捨てられないんだぞ?」
「有休とエリクサーを最後まで余らせるやつのセリフだな……」
部屋のあちこちに、吐いて捨てるほどの段ボール。悠は目を細めて、その中でも一番いらなさそうで重そうな箱を指さした。荷造りした記憶がない。
「アレとか。絶対捨てたほうが良いだろ。誰も使わ――」
「それを捨てるだなんてとんでもない!」
急に語気が強くなって、悠は驚く。そんなに抵抗しなくてもいいのに。
まったくしょうがないなと息を吐き、悠は大きな音を鳴らして両手を合わせた。
「よし、ごちそうさま! じゃあ水上家の掃除鬼こと俺が、今からちょっと本気出してやる。かーさんは食器片付けてて。……よし! 最初の犠牲者はお前だ! くたばれ!」
謎の段ボールの隣を指差す。その箱には『雑誌』と書いてあった。悠の目がきらんと光る。
「ま、待て息子。それも、もったいな――」
「シャラップかーさん! 俺、かーさんが雑誌とか読んでるの見たことないぞ! いらない何も! 捨てちまおう! 水上家の人間に足りないのは、断捨離なんだ!」
悠は乱暴にガムテープを破って中身の雑誌を取り出し、近くにあった紐で素早く括る。それからサンダルを履いて、部屋から出た。向かった先はマンション常設のゴミ捨て場だ。重い鉄門扉を開くと、乱雑にそれらを投げ捨てる。
勢いで、紐の縛りから一冊外れてしまった。表紙がこちらを見つめてきて、悠はぎょっとする。
「こんなもんまで持ってきてたのか……。いつ買ったんだか」
ゴミ捨て場の中で、ふうと息を吐く。同時に、今日のクラスでのことがまた頭によぎった。
「……どうしようかな、部活」
腕を組み目を瞑り考える。複雑に曇った顔をして。
奇しくもその表情は、打ち捨てられた雑誌の表紙を彩るその男とそっくりだった。