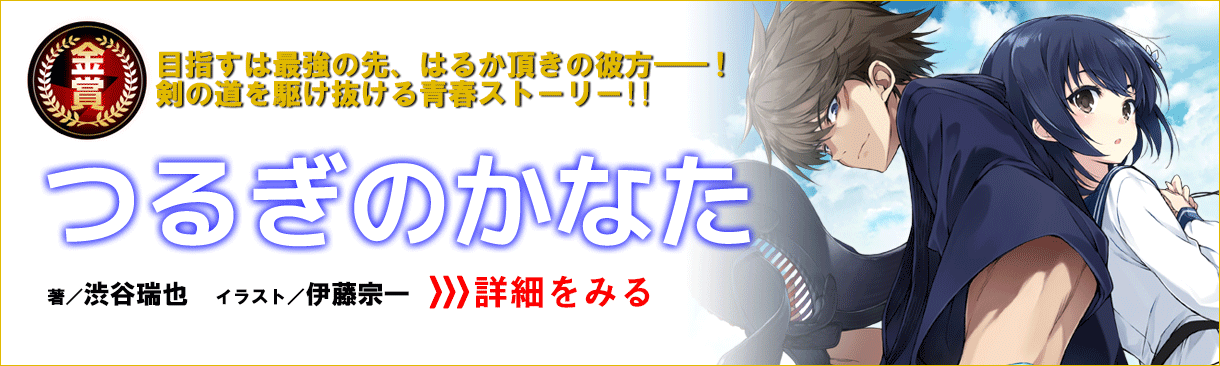× × ×
彼が、何か藍原と話している。けれど、吹雪はその内容を聞こうとは思わなかった。
藍原のお気に入りかなんだか知らないが、とっとと今すぐ死ぬがいい。そう思っていたら。
「なあ。ひょっとして、前にどこかで会ったことある?」
急に話しかけられた。首を傾げて、垂れネームを確認する。……が、なかった。
「名前、どうしたの。ないよ」
「ああ、これ? ……捨てたんだ」
「……よく、分からないけれど」
答えは一つ。男だろうが女だろうが、顔が良かろうが悪かろうが関係ない。
「覚えてないし、覚える気もない。他に、言うことはある?」
凍て付け。恐れろ。邪魔するやつは全員殺す。
そういう思いで睨んでやったのに、笑い返されたことがとても癪に障った。
「……お手柔らかに」
名の知らぬ彼が、対岸に帰っていく。その背に向かって、面の中で独り呟いた。
「できない。わたし、手が硬いから」
試合終了のブザーが鳴る。それは幾度となく聞いてきた、氷の戦場が自分を呼ぶ合図だ。
瞳が、すっと凍っていく。……早く審判。「前へ」と言って。
時間が勿体ない。こんなところで立ち止まる暇は、自分にはないのだ。
「前へ」
だって、わたしが目指すのは――。
× × ×
「ねえねえー、藤宮の綺麗な一年ちゃん。お名前何て言うのー? 隣、座っていーいー?」
「あ、はいっ。藤宮高校一年の、深瀬史織です」
史織ちゃんねー、と頷いて、藍原は史織の隣に座った。
綺麗だ。大人の自分でも妬けるくらい。悠を強奪されたら、ちょっといじめる。
でもこの子からは血の匂いがしないから、可愛い弟分が惹かれることはないだろう。
「史織ちゃん、初心者でしょー? 剣道、やったことないよねー?」
「はい。だから、水上先輩に色々教えて貰っていて……」
「だよねー。……あのさー。悠坊、乾のこと何か言ってた?」
「あっ、はい。ぼけーっとして、上手い、綺麗だ、頭一つ抜けてるって言ってました」
「そっかー。……綺麗、かあ。だよねー」
頬杖をついて苦笑する。
かつて、同じことを言われ続けた女としては微妙だった。
「とうとう悠坊は、一回も『強い』って言わなかったねー」
「……それ、何か違うんですか? 綺麗でもいいじゃないですか」
「んーん。嫌だよ。すっごい傷つく。……ブスって言われるより、泣きたくなる」
藍原は、ポケットから携帯を取り出す。使う機能は動画。共犯者とは、そういう約束だ。
今更になってしまったホームビデオに、彼の姿が映し出される。
「綺麗な『だけ』だって言われてるの。頭百個も千個も抜けてる奴からしたらねー」
ああ、始まる。泣きそう。でも我慢。
だって自分は大人で、無理矢理起こした悪者なんだから。
「……ごめんね、史織ちゃん。先に謝っとくね。……もう、戻れないと思うからさ」
「えっ?」
「ちゃーんと、責任取って貰うんだよー」
「始め」の声が道場に響く。開いた道場の窓から、春風と呼ぶには生やさしい烈風が吹いた。
「おはよう、『剣鬼』。……起こして、ごめんね」
史織の隣に置かれた『剣道ジャーナル』のページがめくれて、彼の名を呼ぶ。
――第六十八回蒼天旗六大道場大会。十八歳以下、男子個人の部。
優勝:御剣 悠 14歳(御剣舘)
× × ×
何が起きているのか、全く分からなかった。
「止めっ!」
並の男子では吹雪の相手にならないことも、誰に対しても一歩も引くことがないことも。桐桜部員なら誰でも知っていることだ。
だからこそ、夢幻のように信じられない。右斜め下、吹雪の方向に伸びる赤旗が。
「反則、一回!」
下がった足が、線を割った。引くを知らないあの無双の剣姫が、自分から。
「始めっ!」
震える、吹雪の唇。それは恐怖か、寒さのせいか。
どちらも違う。それは間違いなく、歓喜の震えだった。
「っしゃぁ―――――――ァアアア!!」
立てかけたホワイトボードが揺れるほどの、彼女の高い咆哮。曲線的に剣先を変化させ、吹雪は敵の喉元に揺さぶりをかけた。一瞬刺突かと見紛うくらい、速さと重みに満ちている。
かかれ、動け引け、どっちに避ける! 吹雪の踏み込みが床を揺らした。
悠は動かない。動く必要もないと目を細めた。
迫られた三択が全て虚であることを分かりきり、ただ前へと竹刀を伸ばす。
同じタイミングで、曲線から生じた吹雪の本命――出がしら面が躍り出る。しかし、確かに本命だったはずの吹雪の一刀は、そのとき既に意味を失っていた。ぱしりと面金に当たった音がするだけで、打突がそれ以上続かない。吹雪の身体が動きを止めた。止まるしかないのだ。
悠の竹刀が、寸分違わず彼女の喉元に付けられているから。
自分の勢いがそのまま喉元に返ってくる。呼吸が止まる――だけど!
下唇を強く噛んだまま、吹雪は細胞のひらめきで引き面――と見せかけた引き小手!
連続打ちを警戒し、面を守りにいくと手首が落ちる二段策だ。
が、判断が光る吹雪の一撃を、悠は埃でも落とすように無感動に払った。「ッしゃあっ」
たった今吹雪は引き技を放ったばかり。従って間合いは十分に離れている。なのに彼から繰り出された追い面は、距離を無視した伸びで彼女に襲い掛かった。だめだ、やられる――!
ばこん、と鈍い音がした。吹雪の、肩口から。
それは防御が間に合わないと判断した彼女が、咄嗟に首をひねって回避したことを意味する。
悠は瞠目し、ほうっと息を吐いた。鍔迫り合いになった彼女の目の前で。
あれ避けるのか、という感心もある。けれどそれ以上に、彼女の歪な笑顔が語っていた。
もっと。もっと。もっと――たまらない!
道場に沈黙が満ちる。けれどこの場にいる全員は、心の中でたった一つの言葉を叫んでいた。
何より誰より問いたい彼女が、心の中で畏れと共に、つるぎのかなたへ問いかけた。
あなたは一体、何者なの――?
右足親指の爪先に痺れが走る。その触覚が脊髄に届くより前、吹雪は既に跳んでいた。
引っかかった気がした。勝利へのか細く見えない糸が。正しさの保証などどこにもないが、数多の戦場を駆け抜けてきた自分の身体を吹雪は信じた。
行ける。一秒を、凝縮しろ――!
面打ち。全く同じ軌道のものが悠から返ってくる。相打ちになるがそれだけでは終わらない。連続技にすぐに繋げた。間合いゼロから放つ引き技だ。憎き兄の姿をイメージして、竹刀で左に弧を描く。人生最上位に入るほど力強く打てた珠玉の引き胴が、がつんと激しい音を二つ鳴らした。……二つ。まったく同じ音が、吹雪の胴にも鳴っている。
意味の理解を後回しにして、吹雪はさらに小手面を放った。
面、引き胴、小手面。僅か一秒間に放った四連撃には、吹雪の全てがこもっている。
その一本も、決まることはなかった。まるで鏡を相手取るように、同じ技で打ち消されて。
「ィやァアアア!!」「っ」
剣の余勢で弾丸となり、吹雪は体当たりを仕掛ける。悠は足と下腹に力を込めバランスを取ったが、そこで小さなハプニングが起きた。勢い余った吹雪が、悠の袴を踏んづけてしまう。
二人は、絡まるように激しく転倒していった。「止め!」
「っ、てて……」
咄嗟にかばえることができて良かった。そういう競技だが、もう人を傷物にしたくない。
「大丈夫か?」
面越しに見ても分かる。整っていて綺麗な顔だ。こんなに苛烈でも絵になるくらい。
「そういうのいらない! ちゃんと本気でやってくれないと死んでやるから!」
剣姫は一人で立ち、背を向けて颯爽と開始線へ戻る。その姿を見て、悠の唇は弧を描いた。
『そういうのいらねぇんだよじじい! ちゃんと本気でやれっ!』
「……だよな。俺も、そうだった」
遅れてゆっくりと立ち上がる。ついでに、椅子に座っている藍原の方を見た。
笑顔とピースサイン。無言で悠は頷き、そして心の中で吹雪に頭を下げた。ごめんな、と。
上手いのも分かる。綺麗なのも分かる。けれどこの程度じゃ、眠たすぎて話にならない。
夢は終わり。帰ろう。一人きりの場所へ。
竹刀を下げて、世界の中心に歩いて行く。目を瞑って、深く息を吸った。
もう誰も寄せつけないよう、縁ごと全て断ち切るのなら。
やっぱり、最後に選ぶのはあの技がいい。
× × ×
鼓動がうるさい。頬があつい。どくんどくんと脈打って、竹刀の先にも血が通ったみたい。
溶けて、死んでしまいそうだ。
この人は一体何者なんだろう。垂れに名前がないことが、焦れて惜しくてたまらない。
吹雪は先刻の四本を思い出す。鏡を見るようだったのは、選んだ技が偶然同じだったからじゃない。見てから、向こうが同じ技で打ち消してきたのだ。それはつまり、相手の方が格段に速くて余裕があるということ。吹雪は己が高みにあるからこそ、一つの結論にたどり着いた。
手を抜かれている。
気付けば、熱に浮かされた身体は勝手に言葉を紡いでいた。
屈辱だ。けれどそれ以上に見てみたくなった。鏡の後ろに隠れている、彼の本当の姿を。
世界の中心で、吹雪は再び剣を構えた。五感が鋭くなっていく。
剣の重さ。息を吸う音。彼の鋭くなっていく両眼。それから……匂い?
「始めっ!」
諦めたはずの春が、そこにあった。
「我ァあああッ殺ャ―――――――――アアアッ!!」
声が違う。吹雪が唾を飲む。
金属走る面金の向こうで、紅く焔のように激しい瞳と目が合った。
竹刀を握った手が熱い。心の中が燃えている。跳びたい。もっと自由になりたい。自分の全てを引き出して、この人にぶつかってみたい――!
歓喜の震えは竹刀に伝達する。中心を寄越せとゆさぶってみたが、悠は微塵も揺らがない。
「っ!」心臓が下がれと命じている。
重心のブレを一切感じさせない鮮やかな足運びで、悠は一気に間合いを詰めてきた。
疾い。怖い。でも引くな!
この試合初めて、悠の竹刀は中心を離れて始動した。その剣は蛇のように生きている。竹刀が曲がっているのかと見紛う変則的な動きで、吹雪を殺りにかかっていく。吐き出しそうな程のプレッシャー。――どこなの、どれを狙ってるの!?
全てを狙っているようにも思えるし、そうでないようにも思える。吹雪の刹那の逡巡を待たず、悠の竹刀は中心に回帰し、ついに前へと襲いかかった。
速すぎて常人なら動くこともできない。けれど吹雪は、咄嗟に最高の防御方法を取った。
右小手と面を相手から隠し、竹刀を握る左手を右腰へ。面、小手、胴。全ての打突箇所を同時に隠す裏避けだ。咄嗟に出すのは最も難しい。……そのはず、だった。
時間が止まる。スローモーションになった世界の中で、吹雪は確かに目にしたのだ。
禍々しく牙を剥いた、鬼の表情を。
止まった世界の中で悠は動き出す。中心からの最短距離で、面へ向かうはずだった竹刀が頂点で右へと弧を描く。
美しい軌道だった。
まるで時の隙間を縫うようなその一刀は、裏避け唯一の隙に向かって吸い込まれていく。
その技は引き技以外で唯一後ろに残心を取る特殊技で、最も旗が上がりにくい。打突箇所には本来大小二本の刀が差してあり、生半可な一撃では刀が通らないとみなされるからだ。
正確無比かつ極限の一刀を、相手の左胴へ。
そのまま返す刀を手元に引いて、相手の胴体を刀ごと真っ二つにたたっ斬る。入ればギャラリーが一斉に沸き立つその技の名は。
「どォ――――オオおぉおっしャぁあああッ――――ッ!!」
逆胴。吹雪の左腰に、雷が落ちる。
ずっと見ていた鏡が壊れる音がする。刀は空間を引き裂いて、本当の姿を導き出した。
天井しかないはずの剣道場。
なのに吹雪はつるぎのかなたに、そのとき悠かな空を見た。
「ど……胴あり!」
道場がどよめく。吹雪もただ呆然とするばかりだ。なのに悠は当然とばかりに、上がっている三本の白旗を一顧だにせず開始線に戻っていった。我に返った吹雪も、急いで戻る。
「始め!」
ああ、終わらないで――。
そんな吹雪の心の叫びを無視するように、悠がいきなり大きく三歩下がった。
何のつもりだと瞠目する。すると魔法のように、ちょうど時計のブザーが鳴った。
「止め! ……勝負あり」
両陣営から拍手が起こる。それは試合終了時に行う形式的なものだが、道場にいる誰もが心からのものを贈っていることに疑いはなかった。
藍原が、動画の停止ボタンを押す。官能のため息をついた。試合前のことを思い出して。
『一本勝ちにしといてねー。四分たっぷり、試合しようよ』
『ん? いいけど、なんで?』
『昔いっぱい教えたろー。デートの時間は、長いほうがいいの』
『……分かった。じゃあ残り二十秒になったら、可愛い顔でピースでもしてくんない?』
『んー? いいけど、調整ー?』
『それもあるけど。ちょっとした剣への復讐』
武道は、ガッツポーズ厳禁。もちろん、ピースサインも許されない。
『平和に行こう。今日の迷惑料はそれでいいよ。姉ちゃんと喧嘩したくない』
「……もー。どんだけ姉ちゃんをダメにしたら気が済むんだよー」
そんな呟きをよそにして、悠は騒がしくなった道場で面を外した。視界が広い。空気がおいしい。けれどどこか窮屈な感じだけは、いつになっても消えないままだった。
深呼吸すると、少し落ち着く。すぐに黒瀬に返さねばと思い、竹刀を見た。
「げっ!」
試合前はなんともなかった打突部位が、もはや修復不可能レベルでささくれていた。
謝りにいかなくては、と立ち上がる。すると。
「待て」
大きな男が、目の前に立ちはだかっている。
その男は年上。どけ、と言えるはずもない。
「逢引の誘いがある。乗ってくれ。もはや主審の近さでは物足りないんだ」
「……押しの強すぎる男は嫌われますよ、江坂部長」
バカだなあ、と思う。わざわざこっちに来てまで、また同じことをしている自分に。
「悪いな。今度の相手だけは、どうやら誰にも譲れんらしい。……賭けをしてくれ、水上悠。一本勝負だ。俺が負けたら好きにしてくれ。お前の願いを、俺ができる範囲なら何でも叶えてやる。金銭でも、人の斡旋でも、時間でも。お前が望むものを何でもやろう。……だが」
「部長が勝ったら?」
「剣道部に入ってくれ。頼む」
悠は、言葉が出ない。年上の男が、こんなに大きな男が、臆面もなく頭を下げているのだ。
自分のような出来損ないに、誠心誠意。
「どうして、そこまでして……」
「この部は俺の全てだ。だから勝つために、お前が欲しい」
あまりにも、真っ直ぐな言葉。悠は目を見ることができずに顔を逸らした。
そして手放せなかった左手の剣を、全ての憎しみをぶつけるように、強く強く握りしめる。
「……後悔しますよ。きっと」
断れなかった。……断ち切れなかった。自分の刀が、きっと錆び落ちていたせいだ。
そのことを憎む自分があまりにも自分で、悲しいと感じた一日だった。
< 前へ|・・・|5|6|7|8|9|10|11|・・・|次へ >