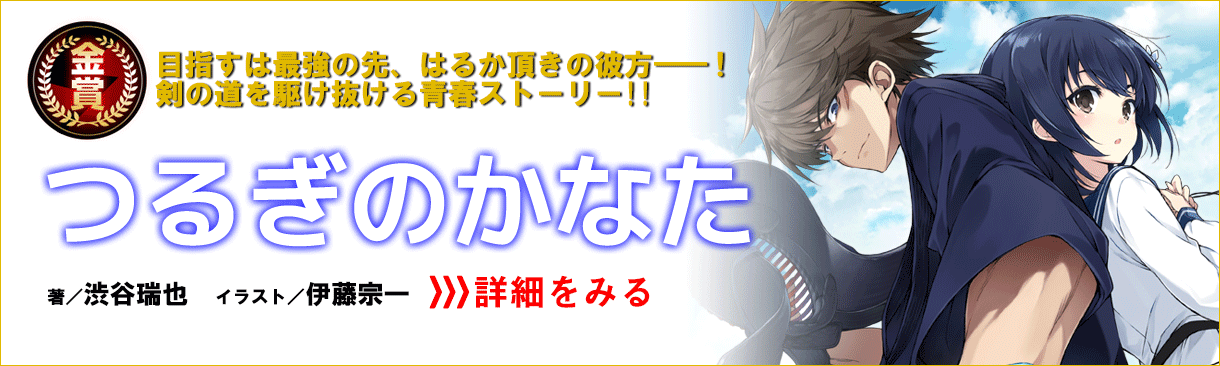四合目:水上、部活入ったってよ
鬼が、哭いている。
高く、遠く、無人の凍土で鳴る鎮魂の鐘のように、その声は万人の耳を悲哀で包んだ。
地鳴りと共に、激烈な一刀が再び誰かの胴体に迸る。「胴あり!」
振り返らない。鬼は喜色を失った。背中だけがただ遠く、歩いた場所から氷になっていく。
その後姿に、誰も追いすがることができない。なのに、なおも彼は闘争を続ける。応えてくれる誰かを探すよう、言葉を失くした鬼は代わりに剣で問いかける。
何処だ。いったい何処にいる。今更勝ち逃げなど許さない。この剣、どこに向ければいい!
「面あり」「小手あり」「突きあり」「胴あり――勝負あり!」
要らない。こんなものは要らない。河原で価値のない石を積み上げても、地獄では価値ある何かに変わらない。分かっている。けれど代わりを求めるには、人はあまりに脆すぎて。
ああ、鬼になんてなりたくなかった――。
人を辞めた彼の呟きに、照らせなかった太陽は、ただ柵の向こうから唇を噛んで見守るのみ。
悲しい剣だった。
悲しくて、獰猛で、破滅的で。だからこそ、儚く美しかった。
『……やめてよ』
けれど。
『やめてくれ。みんな拍手をやめてくれっ! この声が聴こえないのか!?』
どうして僕はあそこじゃなくて、こんなところに立っているのだろう。
『僕に泣くなと言ったのは、君だったんじゃないのか!』
どうして僕は、こんなにも弱い。
言葉は鬼に届かない。最後の一刀が弾ける音が、全てを飲み込み消えていく。床に散らばった竹の破片が目に映る。どうやら壊れてしまったらしい。しかし砕けた獲物はそのままに、鬼は次を問うためそのまま構えた。誰だ。次は誰だ。あと何人斬ればいい。
どこまで行けば俺は、もう一度奴に会える――?
生涯焦がれ続けた、つるぎのかなた。
そこにいたはずの誰かは、地獄を探してもいなかった。
× × ×
「快晴。……快晴。起きなさい。ご飯できてるわよ」
「……ああ。ごめん母さん。すぐ起きる」
「朝練ないとはいえ、珍しいわね。自分で起きてこないなんて」
自室で快晴は目を覚ます。背中を触ってみると、寝汗がぐっしょりだ。目覚ましの音にも気づかないほど眠りが深かったらしい。蒼天旗の夢を見るのは久しぶりだった。
窓の外を見ると、激しい雨。湿度が関係したのだろうか。
「今日はいつもと逆ねえ。吹雪なんて母さんより先に起きてたのよ。朝練ないのに」
「……道理で雨だと思った」
雨でも中止にならないなんて剣道って本当に嫌だなあと思いつつ、快晴は持ち前の寝覚めの良さでパパっと制服に着替え、階段を下りる。
「あれ、父さん。もう出るの?」
「おお、雨だと電車止まるからな。出るよ。……なあ快晴。吹雪がヘンだ」
玄関で革靴を履きながら、父は怪訝な顔をしている。
「ヘンって、何が? バカはいつも通りでしょ」
「それは知ってる! 違うんだ! な、何か、嫁入り前みたいな感じなんだよ!」
「……何言ってんの。眠いの父さん? 心配しなくても誰も引き取らないよ、あんなの」
そうかなあ、と納得してない父を玄関先まで見送り、快晴はリビングの食卓につく。誰にでもなくおはようと声をかけ、まずは夢のせいでカラカラになった喉を潤した。
「……おはよう、お兄ちゃん」
「げっほ!」
もはや幻となった敬称。しかも熱に浮かされたような声で返ってきて、快晴はむせた。
「きも。きたな。お兄、最低」
「お前が気持ち悪いこと言うからだろ!」
「……何も言ってない。いいからお兄も、早く食べたら? ……遅刻するよ」
誰だ、こいつ。快晴は言葉を失う。
いつもなら朝は必ず無言だし、兄に気遣いなんて絶対しない生意気の塊なのだ。
「お前、何かあったのか? 熱があるんじゃないのか?」
「ある、かも……。ねえお兄。水上って名前、知ってる? みずのうえで、水上」
「水上? 僕の高校で?」
「違う。剣道で」
快晴は腕を組んで数秒考えるが、誰も思い浮かばなかった。
「いや、知らないな。県内でも全国でも蒼天旗でも、そんな名前の奴は見たことない」
「そう。やっぱりお兄は無能すぎ。……ごちそうさま。もういい」
「あら! 吹雪、残してるじゃない!」
「なんだか、昨日から胸がいっぱい……」
母と快晴に衝撃が走った。いつもは日本昔ばなし盛りのご飯を三杯食べるのに?
「母さん、こいつ吹雪じゃない。誰かに斬られて入れ替わった? ……今日、雪かな」
「……あら。もしかして母さん、お赤飯とか買うべき?」
妙に浮かれている母も謎だし、ご飯そっちのけでソファに座り、スマホで動画を見始めた妹も謎。快晴にとって、女性というものはときに火星人よりも未知だ。
「昨日帰ってきてから、ずーっと部屋で動画見てニヤニヤしてるのよ。貰ったとかで。母さん知らないんだけど、昨日って何かイベントでもあったの?」
「いや、普通に出稽古って聞いたけど……。確か、佐々木先生の学校だったかな」
快晴は朝食を摂りながら、動画に夢中の妹を見る。スカートくらい穿けこのバカ。
「……ふ、ふふ。ふふっ、ふふふ……」
だらしなく緩んだ頬を数秒おきに戻そうとして、それでも噛み殺せないらしい。
ぶっちゃけ言ってキモい。一体何を見てるんだろうと、覗き込むほど快晴はバカじゃない。後ろに行ったら蹴られる。馬と一緒だ。だから流れてくる音だけで判断した。
毎日聞いてる竹の音。それから、豹変している吹雪の声。すぐに何の動画か分かった。
「そんなに気持ちいい勝ち方をしたのか?」
羨ましかった。自分はあの日から、一度だって剣道で笑ったことがないのに。
「ううん。……負けたの。完璧に、負けちゃった」
「はっ?」
だったらどうして荒れてないと言いかけて、やめる。吹雪が心臓と左腰を押さえながら、雪のように真っ白な肌を紅潮させて丸くなった。「やっと、見つけた」
長雨の中、やがて吹雪が持つ液晶に刀の雷が落ちた。
人の身には到底放てぬ軌道と咆哮。快晴の心臓が、一際高く鳴って身体を震わせた。
「……吹雪」
知っている。快晴はその音を知っている。
天井から落ち、人生を変えた雷を。瞳の雨を拭った一筋の光を、忘れられるはずがない。
「それ、見せてくれっ!」
春を洗い流すような雨の中。快晴はようやく、探し続けた相手を見つけた。
× × ×
「水上、それ、見せて。資料集、忘れた」
六限の移動教室、日本史の時間。
悠が窓際席で雨の止んだ外を見ていると、隣のちっちゃな女の子に袖をつままれた。
藤野葉月。ボブヘアーにいつも同じ表情の、剣道部の二年女子だった。
「お? はーちゃんの頼みならぜひ。でも隣に女子いるから、そっちに借りていいんだぞ」
「嫌。資料集は、口実。水上と、喋りたい」
無表情で、どきっとすることを言う。
意外に男キラーなのかもと悠は笑い、すぐに机をくっつける。そこに資料集を広げ、座りやすいように葉月の椅子を引いてやった。
葉月が、ミリ単位で目を丸くする。何かに驚いているようだった。
「水上、異性の姉弟、いる? ……女子慣れ、感じる」
「……そうかぁ? 気のせいだと思うけどな。俺、一人っ子だよ。母親と二人暮らし」
「でも、桐桜の藍原先生、『姉ちゃん』って言ってた。藤野、聞いた」
「うあ、それ恥ずかしいから絶対内緒な……。資料集代として」
悠が授業についていって、資料集のページを捲る。自分の歴史も、少し話すことにした。
「瞳は俺が小さい頃から、御剣でずっと一緒にいたから。だから姉ちゃん。でも瞳だけじゃないぞ。他にも、兄ちゃん姉ちゃんはいっぱい居たんだ。……みんなバラバラになっちゃって、最後は俺だけ置いてかれたんだけどな」
「置いて、いかれた?」
「追えなかったんだよ。はじめまして、御剣悠でした。実家は道場です」
「……そう。……だから、あんなに」
続く言葉は何なのか、悠には分からない。考えていると、葉月がフリーダムに資料集のページを勝手に捲っていった。弥生時代が一気に幕末にワープ。微笑ましくて撫でたくなる。
「おーい、はーちゃん?」
「土器、つまらない。女は黙って、幕末」
葉月の小さな手が、ページに癖をつけようとする。しかし、途中で止めた。
「もう、癖、ついてる。水上も、仲間?」
「……恥ずかしいとこばっか見つけんなよ。どうせ俺は、こっちに生まれてたらなーとかたまに考えちゃう永遠の中二病だよ。かっこわる」
「……そんなことない。試合中だけは、かっこよかった。乾吹雪、ざまあ」
小さな指で、腕を突かれた。
一々ドキドキさせられて悔しいから、悠は少しやり返してみる。
「だけは余計。……だろ? はーちゃん、結婚する?」
「嫌。水上、タイプじゃない。そういうの、千紘にやって。うざい」
何の慈悲もなく一刀両断。吐血する思いで天井を見上げていると、チャイムが鳴った。
ああ。今日も授業が終わってしまった。
悠は大きなため息をつくが、対照的に葉月の顔は気持ち輝き出す。
「行く。また、遊ぼ。水上で遊ぶの、面白い」
「……タイプじゃないんじゃなかったの?」
「女子は別腹、無限」
そう言って彼女は、自分が座っていた机から、隠していた自分の資料集を取り出した。
悠が固まる。とどめとばかりに、葉月は滅多に見せない満面の笑みを解禁してきた。
「おいしかった。また、部活でね」
とことこ去っていく葉月の姿を、正視できない。つい窓の外を見る。
「……都会の女の子、レベル高すぎだろ。みんなこんな感じなの?」
雨露を宿した葉桜が瑞々しい。始まりの四月も、もうすぐ終わり。
「……くそードキドキする。地稽古でやり返しとくか……」
水上悠は、剣道部に入っていた。
× × ×
「ラスト一本な、やしろん。延長なし、二言なしだぞ」
「うるせえ、わかってるッつの! つかやしろんって言うんじゃねえ!」
元気いいっすねー、と呆れて笑い、悠は道場上手で竹刀を構える。
時計をちらりと脇見した。本日の練習も終盤。お互い相手を取って組み手する稽古、地稽古の終了まであと十分だ。区切りは太鼓の音で行うものもあれば、こうやってお互い申し合わせるものもある。
最後の一本勝負は、基本ガチ勝負。
ただ、自分より目下の人間と戦う場合は、わざと最後の一本を取らせてやることも多い。
「ほぉら胴ぉ―――――ッ! はい即死ー。やしろんスペランカーかよ。お疲れー」
悠は面倒だからやらない。ガラッガラの隙として面を晒したら八代が飛び込んできたので、容赦なく爆弾のような返し胴を炸裂させた。『アホは死ね』。シンプルな御剣の教えだ。
「ぐ、くっ……! てめえ、もう一本だ!」
「ダメ。さっき二言なしって言ったじゃん。そもそも命は二つないんだぞ。軽率すぎ」
「で、でもよ……まだ時間あるからいいだろ!?」
「いやー。お客さん、後ろの列見てみ」
人外アトラクション水上悠、既に三人待ち。今日は本当に休み無しでフル稼働だ。
やっぱり新設って人気あるんかねえと自嘲して、八代を諭す。
「ちゃんと頭使って出直しな、ランク九十。……あ、あとさっき言ったやつ、頼めるか?」
「……ちっ。わぁったよ! 男に二言はねえ!」
「よし。そういうとこ好きだぞ、やーしろん♪ その顔であと三十分は働けるぅー」
うるせえ殺すぞ! ときゃんきゃん騒いでるのを無視して、悠は刀を納めた。次の相手が連続で来ようとするが、一旦右手を突き出し差し止め、後輩の元に走る。
用具庫の有りモノを無理矢理探してきたから、胴のサイズが合っていない。けれど身体ピッタリの白道着や、裾を下ろした纏のお下がり白袴が、よく似合っていた。
「道着姿、意外と似合ってるぞ。後輩」
「わざわざおちょくりに来たんですか暇ですねっ! どうせ防具に着られてますよ!」
面から何までフル装備の史織が、ぎこちない動きでぷんすか怒る。防具は動きづらいのだ。
「伝令に来た。このあとやしろんに来てもらうから、あいつで避ける練習しときな。あいつここで一番素早いから、ドカッと経験値貰えるはずだ。……試合、出るんだろ?」
「う。はい、生意気ですけど。……わかりました。八代でガマンします」
「ははっ、相変わらず生意気だな。頑張れ。満足、させてくれるんだろ?」
ひっそりと意趣を返す。面の中で、史織が真っ赤になっていた。
「む、蒸し返さないで下さいよ! 先輩、ほんっと最低! はやくどっか行ってください!
……私、一人で大丈夫ですから!」
振り回してきた史織の竹刀を笑いながらひょいっと躱して、悠は自分の位置に戻った。
「ゆーくん、遊ぼ! 早よ!」
「出たな妖怪関西弁。さっさと祓ってやるぞ。……ちっひはまあ、七十ってとこ?」
「えっ? 何が? 体重!? うちそんな重ないよ!?」
「いや、顔面偏差値。大好き、ちっひ」
「うあ―――――っ! うるさいうるさいうるさい! 早よやるでっ!」
じゃれつく犬。弾ける竹刀。
それを見届けて、女子主将の纏は腕を組み、壁にもたれた。
そのまま見学中の一年生たちを見る。新入部員の女子は、史織を含めて三人。男子も八代と奴を入れたら三人だ。みんな、よく入ってくれたものだと思う。……それから。
「どうした、立花。具合でも悪いのか?」
「江坂。……新入部員を見てたのよ。よく入ったもんよね、と思って」
「確かにな。本当に嬉しい誤算だ。人が多いに越したことはない」
「そっちもそうだけど。……あんた、今の水上と八代見てた?」
「ん、ああ」
決まり技は面返し胴。相手が打ってくる面を右斜めにした竹刀で受け、そのままカウンターで胴に打ち込む技だ。避けながら打つ抜き胴よりは安全だが、受ける、打つの二動作が必要になるため、速さがないと絶対に決まらない。
「あたし、目がおかしくなったのかな。受けるのと返すのと、同時に見えたのよね」
「奇遇だな。俺は耳も狂った。音が重なってたぞ。というか今も響いてる」
「そ。超常現象水上ファイル、大ヒット放映中ね。……ねえ、あんたに聞きたいんだけど」
纏は気が短い。ミステリーを読む時は、考えずに次々先を読んでしまいたい。
「一体あんた、どうやってあいつを入れたわけ? そんなに口説くの上手かった?」
「……なに? 操ったのはお前じゃなかったのか? お得意の口車ゴールド免許とやらで」
「あんな大型特殊の免許取った覚えないわよ。だってあんた、何か話してたじゃない」
「……ああ。アレか」
纏に問われ、江坂は苦笑する。篭手を着けた手で喉を押さえると、嫌な光景が蘇った。
「いや。俺は袖にされてしまったよ。文字通り、引導を突きつけられてな」
「……何よ。何なの? 犯人なし? そんなオチってあり?」
「考えても分からんものは仕方がないだろう。……望みも言わんしな。謎だ、あいつは」
二人揃って、千紘対応中の悠の姿を見る。
「はいめーん! おしまーい。ちっひアツくなるとすぐ出小手やおまんがなー」
「ううう……! なんで今の擦り上げれんねん!? インチキやインチキっ!」
遊ばれている。女子部のエースが。大きな息を吐いてから、纏は目を細めてみる。
どうして入ってくれたのか。そんな謎よりも、遥かに大きなミステリー。
「……そもそもこんなに強いのに、どうして辞めてたのかしらね」