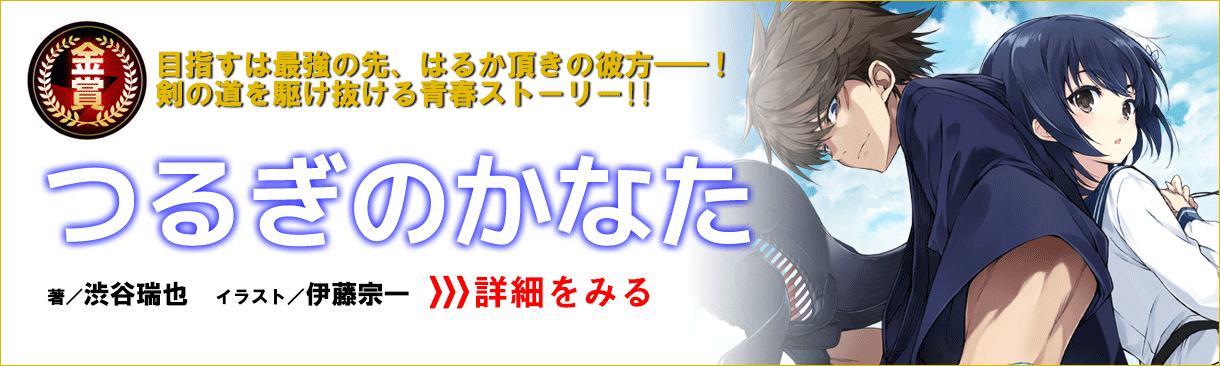× × ×
「見学に来た奴、全員に入部届を書かせましょ。大丈夫、円香の胸でも揉ませれば一発よ」
「いいわけないよう!? わたしの胸はご新規さん向け十連ガチャじゃないんだよっ!?」
「うっせーわねー。胸くらいイイじゃない別に。減るもんじゃないし」
「減るよう! 色々減るってば! 纏が自分のを揉ませればいいじゃない!」
「えー。あたしの胸は高いのよ。あんたほど無いし。やっぱり無駄に余ってるところから配るべきじゃない?」
「人の胸を外れみたいに言わないでよう! 好きで余ってるわけじゃないんだからね!?」
部活紹介が終わり、練習前の剣道場。
女子剣道部副部長、幸村円香は憤慨していた。白道着の右肩に、ひとつ結びで乗せているセミロングの髪が怒りでぶんぶん揺れる。牛乳石鹸のような匂いが香った。
「あーもー、贅沢言うんじゃないわよこのわがままボディ。手段なんて選んでる場合? とにかく部員入れなきゃ話になんないの。男女最低一人ずつ、特に女子! 部活滅びるわよ!」
女子剣道部部長、立花纏は長椅子の上で偉そうに足を組み、竹刀の先で円香を指した。端正な彼女の狐顔が不機嫌に歪むと威圧感が出る。が、円香には効かない。剣先を掴んで、にこっと笑った。
「でも、ぜったい纏のせいだよねえ。女子が来ないの。……悔い、改めよーね?」
「……な、何言ってんのよ、こーんな美人が部活にいるのよ? 人が来ないのは剣道とあんたたちのせいでしょ!」
「へー? そっか、そうだよねえ。美人会長さんが居るんだもんねえ。うんうん、全部わたしたちのせい。道場の鏡さんも、世界一きれいなのは纏って……あれあれ? おかしいなー。すっごく明るい髪色が映ってるんだけど。気のせいだよねえ? こんな見た目してたら、誰も寄って来ないもんねえ。毛先のパーマもきっと幻だよねえ。そんな性格みたいに曲がった毛先、あるわけないもんねー。ねえ? 校則の権化、『自称』美人かいちょーさーん?」
円香の圧力に身を引き、纏が震える。また腹黒狸を起こしてしまった。
「……に、人間、外見だけじゃ」
「外見って、中身の一番外側だけどね。とーぜん、心が綺麗な会長さんはそこもちゃんとしてるんだよねえ?」
「………………………………ぅるさぃ」
「あれれー? どうしたの纏、元気ないねえ。旦那さん呼んで慰めてもらおっかー?」
「だ、旦那って何よ! 江坂は関係ないでしょ!?」
「あれあれー? 誰も江坂くんとは言ってないよー? ねえねえどうして? どうしてそう思ったのかなあ? それより最近進捗どうなの? ねえねえ、早く教えてよう。ねえねえ」
纏はしばし真っ赤になってやられっぱなしになる。が、ついにキレた。
「うが――――っ! うるっさいッ! ぶん殴るわよ!」
「きゃー♪ 助けて千紘―♪」
円香は纏から逃げ、道場奥で話している二年生の塊に突っ込んだ。その中から千紘をチョイスし、ためらうことなく盾にする。
「えっ? なになに? ちょっ、巻き込まんとってやユキさん!? クロちゃん助けて!」
「同情するから金をくれ」
「なんでそれだけで金取んねんっ! ひぃいい、痛いの嫌やぁ! きのっちぃ!」
「ちっひー死んでも悠が入ればプラマイゼロだよなー。なあ、埋め合わせどうするよ?」
「あほ! 先に助けろ! うちが埋められてまうやろが! ほんま最悪やこの二年コンビ! ……うう。ゆーくん、はよ来てぇ!」
そうやってしばらくみんなで遊んでいると、道場奥の用具庫の扉が開いた。竹刀を整えた江坂が戻ってきたのだ。
「よし、そろそろ体操を始めるぞ。……二宮はなぜボロボロなんだ?」
「うちが一番知りたいですよそんなん! ……あ、ぶちょー。はーちゃん、委員会でかなり遅れる言うてました」
はいっと手を挙げ、この場にいない最後の二年生、藤野葉月の不在連絡をする。江坂が分かったと頷くと、円香がきょろきょろと辺りを見回した。
「あれっ、八代くんはどうしたのかな? 一年生って、もう授業終わってるよねえ?」
「ああ、用具庫にいる。竹刀袋の中身を全部高校用に入れ替えるそうだ。……しかし、一年か。どうにか他にも確保しないとな。まずはメンバーを揃えなければ、前回の成績を超えるなど夢物語だぞ」
剣道の団体公式戦は、五人制だ。
足りないポジションは二本負けの不戦敗になる。これはかなりのハンデとなるから、最低三人でも出られるとはいえ、まずは全員揃えなければ始まらない。
藤宮高校剣道部は現状、男子四人、女子四人、である。纏の瞳がめらっと燃えた。
「何度でも言ってやるわ。絶っっっ対、最低でも男子一人と女子一人を入れること。特に経験者は、殺してでも入部させるのよ! 分かってんの江坂!」
「……分かっている。一々うるさいぞ。大体だな、お前がそんな厳つい見た目をしているから」
「あんたにだけは言われたかねーのよ!」
纏が江坂相手にまた暴れる。
そんな剣道部の様子を知る由もなく、深瀬史織がついに剣道場への扉を開いた。
「こ、こんにちは。……あの、剣道部の、人たちですか?」
一瞬の静寂。それから、大熱狂が巻き起こった。
「うわあっ、可愛い子だあ! きゃー! ふ、副部長の幸村です。見学ですかっ!?」
「は、はい」
「……あたしより可愛いんだけど。何、この嬉しいのに喜べない気持ち。歓迎したくないわ」
「お前は十秒前の自分を殴ってこい。……部長の江坂だ。ありがとう。こんなむさ苦しいところに、本当によく来てくれた」
華々しく迎え入れられる史織を見て、悠も続く。道場の中へ、ひょこりと顔だけ出した。
「おおっ、ゆーくん! ほんまに来てくれたんやー!」
「悠、おまえマジでいい奴だなー。騙してこんなとこに呼んで悪かった!」
すぐに、城崎と千紘が喜色満面で迎え入れてくれる。それが嬉しい。
「いいよ。見るだけって約束だからな」
来て良かった。悠は素直にそう思う。
見学用の長椅子に座るよう促されたが、今は二人と話したい。道場へと足を踏み入れる。
両足を揃えて、鋭角十度くらいの礼をしてから。それは完全に無意識から出た所作だった。
「……あっ」
冷や汗が背筋を流れ落ちてから、悠はようやく自分がしでかしたことに気が付いた。
道場に入る時、礼をしろ。
去るときは、正面に背中を見せず、礼をしろ。
そんなことが身体に染み付く理由は、この世に一つだけしかない。
部員全員が、殺人鬼めいた笑顔を浮かべる。
――お前。経験者、だな?
「しまっ――」
ピラニアの水槽に叩き込まれたような悠の断末魔が、道場全体に響き渡った。
× × ×
「死ぬかと思った……」
「熱烈歓迎でいいじゃないですか。私は情熱的なの、嫌いじゃないですよ?」
「……俺は愛情表現は控えめがいい」
史織と悠は、部員に誘導された長椅子に座って見学を始める。練習は素振りと体操が終わり、部員全員が面をつけ始めたところだった。
「今から何するんですかね?」
「切り返しだろうなー。で、終わったら大体基本打ち。技打ち。打ち込み。終わったら休憩した後、地稽古っていう組み手みたいなのをやる。それも終わったらかかり稽古して、もっかい切り返しして終わり、かな。大体どこの道場も、基本の流れ自体は変わらないはず。あとはこれにどんな肉付けするかだけど、それは……。あ、ほら始まった」
道場の上手、つまり入り口から一番遠い最奥の位置に立った江坂が、部員が二人一組になったのを見届け、号令をかけた。
「礼」
面と籠手を着け、防具を完全装備した部員が互いに一礼する。三歩歩いてから左腰に構えた竹刀を抜き、そのままキャッチャーがミットを構えるような格好でその場に座った。両かかとは地面から浮いている。互いの剣先は触れる程度の間合いで交差して、僅かにぶつかり合う。かちり、と竹の擦れ合う音が道場に響いた。
これは蹲踞という儀式で、練習も試合も剣道は必ずこの動作から始まる。
全員が蹲踞から立ち上がるのを確認し、江坂が小さく一呼吸。空気が通った雄々しい声を、腹の底から引き出した。
「切り返し、始めッ!」
「しゃああああああッ!!」「ヤァあああッ!」「おぉおおあああ!!」
道場が、闘争心で満たされる。
近くでいきなり風船が割れたように、史織はびくりと身体を震わせる。いきなり人が獣に変わったような感覚に驚いているのだろう。一方の悠は、微動だにしていなかった。
「……久しぶりだな。稽古見んの」
部員の叫び声をそよ風のように受け、悠は顎に右手を当て稽古を見始めた。
目の前で、円香が竹刀を構えている。かけ声を発して闘気を纏った彼女が、正中線を起点に竹刀を振りかぶる。そして綺麗な放物線を描くよう、相手の頭に向かって目一杯振り下ろした。
「めぇんっ! りゃああっ!」
重く、けれど心地よい快音が、地鳴りを呼び込むような踏み込みと共に道場へと抜けていく。
その音を引き連れて、円香は気勢の乗った体当たりを相手にぶつけて下がらせる。「はあァッ!」大きく振りかぶって右面、その次は切り返して左面を進みながら打っていく。
荒々しく、だけど綺麗に。そしてできるだけ速く。
元立ち(受ける側)は鋭く切り替えされる左右の面を、地面と垂直に構えた竹刀で互い違いに防御する。道場はたちまち、竹刀がぶつかりあう花火のような破裂音でいっぱいになった。
前に右、左、右、左。四本打ったら今度はバックしながら右、左、右、左、右――。
最後に相手と間合いを取って、一足一刀に入り直す。それから面打ちで抜けて振り返る。
切り返し。『剣道の大事な要素が全て入っている』と言われる代表的な練習だ。
どんな道場でも稽古は切り返しから始まり、最後に切り返しをして終わるようになっている。
「す、凄いですね。あんなにドンって踏み込んで、足痛くないんですか?」
「……ちゃんと踏んでれば痛くない。足の裏が奇声発せる面の皮と同時に厚くなってく」
悠が、目を細める。焦点を、『八代』という垂れネームが付いた男に合わせた。さっき聞いた話だと、入ったばかりの一年生らしい。速くて荒い切り返しをしていた。
「あッ、やべ! 今のミスった! もっかい打っていいすか!」
やかましい。よく吠える犬みたいだ。
最後に抜ける面打ちがご不満だったらしく、黒瀬という男にワンモアをねだっている。すごく嫌そうに彼が構え直したところを見ると、ダルかったのだろう。悠にも気持ちが分からないでもなかった。「ッしゃああ――――――メェぇえんっ!」
今度こそ、重いストレートのように圧のある大きな面打ちが決まった。速度の塊が黒瀬の横を抜け、スケーターがジャンプするように振り返る。右踵に着けたサポーターに焦げ付くような摩擦がかかっていて、隣に座る史織が感嘆の息を漏らしていた。
「はやい……。一番、はやかったかも。おんなじ一年生なんだ」
「んー。一年ってことは……今年、十六歳、か? ……んー」
いきなり低くなった悠の声に、史織がまたびくりとする。自分のように目が悪いわけでもないのに、遠くを見るみたいに目を細めている。視線が鋭くて、少し怖い。
どうしたのだろう。嫌がってた割に、来てからは結構楽しそうだったのに。……もしかして。
「あの、先輩。……無理矢理連れてきて、すいませんでした」
「ん、え? どうした? 無理矢理? なんで?」
「だって、やっぱりつまらなさそうですもん。……私がごねたから、気を遣ってくれてたんですよね?」
史織が、またやってしまったと渋面を作る。どうにも自分はわがままなのだ。努めて出さないようにしているのに、たまに抑えられなくて漏れてしまう。そんな風にへこんでいる自分にさらに気を遣ったのか、悠は苦笑して首を振っていた。
「いや、そんなことない。気なんか遣ってないよ。来て良かったって思えた。本当だぞ? 引っ張ってきてくれてありがとうな」
会ったときからずっと、真っ直ぐ丁寧に気持ちを伝えてくれてどきっとする。けど、そんな人だからこそ逆に分からない。
「じゃあ、どうしてそんなに不機嫌そうだったんですか?」
「……さあなー。内緒。でも、今は不機嫌というよりヘコんでるだけ」
「……へこむ?」
苦笑する悠は、一向にこちらを見ようとしてくれない。
「後輩相手に気も遣えなかったから。駄目だよなー、俺」
「べ、別にそこまで気にするほどのことでもないと思いますけど……」
答えが返ってこない。彼はまた、頬杖を突いてつまらなさそうに遠くを見ている。
その姿はまるで、飼い主に先立たれた猫のように寂しそうだった。
× × ×
「ゆーくんゆーくん。楽しんどるー?」
悠が呆けて練習を見ているうちに、時間は吹っ飛んでいってしまったらしい。自分たちのもとに、面を外した部員たちがやって来た。
「……ちっひ。剣道が楽しいわけないだろ? 毎日やってるならわかるだろ」
「あっはっは、まあな! しんどい! あつい! 帰りたい!」
教室で会っても道場で会っても、千紘は喜色満面元気マシマシ油カラメだ。その後ろでローテンションの黒瀬が、しみじみと悠の意見に首肯していた。
「わかる。わかりみしかねぇんだよなあ……。基本的に終わってんだよなぁ、剣道って」
「大体打って反省打たれて感謝とかどんだけドMなのよって話よ。終わってるわね」
「かばえる点が皆無だな。ハマるやつはどうかしている。夏は暑いし、冬は寒い。しかも裸足だぞ。正気の沙汰とは思えん」
男女部長の江坂と纏までそれに続く。悠はほっとした。
「えっ、あの、ちょっと、みなさん剣道部ですよね? す、好きでやってるんですよね?」
ひとりだけ、史織は戸惑っていたが。副部長の円香が、史織の肩をぽんと叩いて首を振る。
「深瀬ちゃん、落ち着こうよ。剣道部の人間が剣道好きなわけないでしょ?」
「いやいやいやいや!? 何言ってるんですか!? 急に日本語が不明なんですけど! わ、私一年生ですよ? もっといいとこアピールしましょうよ! 誘い方おかしいですって!」
おかしくない。むしろ親切だ。
悠のその気持ちを、城崎が代弁してくれる。
「そりゃ入ってくれたら嬉しいけど、一応ほんとのこと言っとかなきゃな。すぐ辞められちゃったら意味ねえし。大体さー、頑張ってもモテねえんだぞ? 球技みたいに見せる場ないし、奇声出すし!」
「あほ、それはきのっちやからモテへんねん。うちを見てみろ!」
「モテてねえじゃん!」
「ああっ、これや! これこれ! この扱いを待っとってん! ゆーくんも見習って!」
「でもちっひ可愛すぎて俺嘘つけないし……」
「だからそれをやめろて言うてるんやろぉっ!」
暴れる千紘の攻撃を笑いながら躱す悠に、江坂が話しかける。
「どうだ、水上。剣道部は。地獄の道連れは多い方がいい」
「……うーん。好きじゃないんで、剣道。もうたくさんです」
前へと踏み込まれて、悠は無意識のうちに一歩下がる。追撃を仕掛けるように、円香がずいっと踏み込んだ。
「そんなこと言わずに! だってもったいないよっ! 経験者なんでしょう? わたしすっごい羨ましいよ! やろうよ剣道! ひとりだけ逃げるなんてずるいよう!」
「に、逃げ……。い、いや! 本当に俺は」
なかなか煮え切らない態度でいると、悠の耳に舌打ちが一つ聞こえた。
音源の正体を追うと、『八代』の垂れネームを着けた男だった。
「やる気ないヤツ入れても無駄じゃないっスか。経験者っつっても、どーせ弱いんでしょ。嫌なら先輩たちも辞めたっていいんスよ」
尖った犬歯も相まって、なんか飢えてる犬みたいなやつだなと、若干悠には面白い。
一年期待の星、八代操。
性格のように尖った髪をがしがし掻いて、彼は冷水機を求めて道場外へと消えていった。学年が離れていれば、多少の生意気なんてご愛嬌だ。悠が去りゆく八代をニヤニヤ見つめている一方で、同い年の史織は上手く流せなかったようだ。眼鏡をくいっと上げて光らせている。
「……生意気ですね、あいつ。きっとモテないと思います」
何がおかしいのか、聞くなり纏が隣で爆笑していた。
「はいはい、あんたそーいう娘ね! ようこそ剣道部へ!」
「しおりん、典型的やなー。よー一言多いって言われるやろ? うちもうちも!」
「千紘は一言じゃ済まないでしょう? あ、でも女の子の友達少なそうだよね、史織ちゃん」
纏、千紘、円香の女子三人にいきなり斬られ、史織は思わず唸って心臓を押さえる。
「い、いきなりなんですかっ! そ、そんなこと全然、当たって……る……? あれ……?」
震える史織を見かね、部長の江坂が助け舟を出した。日頃女子陣と接する身として、色々思うところがあったのだろう。
「その辺りにしておけ。せっかく見に来てくれたのに、二度と来てくれなくなっても知らんぞ。水上も、今日は是非、最後まで見ていってくれ。試合稽古をするんだ」
江坂の発言に、悠が目を瞬かせる。剣道部は普段、組み手のようなものをやることはあっても、試合稽古は中々やらない。それをする、ということは。
「近いうちに練習試合とか公式戦でもあるんですか?」
「おお、流石よく分かっているな。来週の日曜、練習試合をやることになってな」
「……来週の日曜? あれ、案内、は?」
悠のじとっとした両目が、千紘と城崎の二人を睨む。かすれた口笛がハモっていた。
「水上、深瀬。剣道は勧めづらいが、剣道部はいいところだぞ。ぜひ気に入ってくれ」
江坂の言葉も右から左。悠はにっこり笑顔で、二人に言った。
「くたばれ。やっぱり剣道部なんて大っ嫌いだ」
× × ×
その日の夜。悠は自室のベッドで寝転がりながら、携帯でLINEを立ち上げた。
[城崎 俊介]今日、悪かったなー。ホント急に入っちゃった試合なんだよ
[Yu.M]いいよ、不可抗力なら仕方ない! じゃあそろそろ寝るんで
[千紘]待ってゆーくん、振り替えいつにする? 来週以降やったら、練習休みの日に!
[Yu.M]そのことだけど、もういいや! 東京は自分で行くよ。俺なら一人でも大丈夫だ。
[Yu.M]じゃあ、また。来週日曜はよろしく
悠は目を閉じる。自分で打った最後の一文に唸ってしまった。
この流れは良くない。確実にずるずる引き込まれている。……しかし。
「反則だよなあ。この名前出してくんのは……」
悠はLINEを操り、友達一覧からその名前をタッチする。
藍原瞳。懐かしい姉ちゃんの名前だった。悠は寝落ちするように目を閉じて、今日の試合稽古の見学途中にあったことを思い出す。
道場に、優しげな熊が入ってきた。
思わずそう錯覚するほどの、縦にも横にも大きい体躯だ。部員全員が一斉に「こんにちはっ!」と礼をする。
『うん。止めなくていいから、続けてください』
歳のほどは五十を超えているだろうか。髪には白髪も交ざっている。しかし、低く通る声や立ち振る舞い、そして澄んだ光が灯る双眸は、歳の衰えというイメージからは縁遠い。一度見たら、忘れられそうにない。
『……あの。佐々木先生、でしたよね。確か』
だから悠は、忘れていない。彼の仏のような笑顔が、悠を歓待した。
『ええ。……お久しぶりです、悠くん。来ていたんですね』
『はい。どうもヘンテコな縁があるみたいで。……そうか。この学校、だったのか』
悠は慌てて言葉を探そうとする。しかし、何を話せばいいのかわからない。そんな悠の様子を佐々木は悟り、達人らしく先手を取った。巨体を折り曲げて、恭しく。
『頼みがあります、悠くん』
『ちょっ!? あ、頭上げてくださいよ!?』
『藍原くんに、会いたくありませんか』
悠は、目を丸くする。会いたい名前をこんなに急に出すのは、反則だと思った。
『来週の日曜。彼女が、教え子を連れてここに来る。だから、会いに来ませんか。お願いします。君の時間を、私にください』
どうか、と。その男は願うように言った。
『君に、『剣姫』を見て欲しい』
「……けんき、ねえ」
薄く笑って、悠はスマホをベッドに落とす。ヘンテコな縁だ。早く断ちたい。
このまま寝てしまおうと目を閉じた瞬間、控えめなノックが自室の扉を揺らした。
「悠。取引先の人に茶菓子を貰ったんだが、一緒にどうかな。ホットミルクを入れるぞ」
母は、おそるおそる扉を開く。ぎこちない笑顔で提案すると、同じ顔が返ってきた。
「いや、太るからいいや。帰宅部だし。今日はもう寝るよ」
「そ、そうか。じゃあ、お茶はまたの機会にしよう。必ず。……悠。学校はどうだ? 何か心配事はないか? ア、アレだぞ。頼りない母だが、いつでも頼ってくれていいんだぞ?」
「……うん。ありがとう。いつか、かーさんに甘えるな」
言葉の真意を、母は受け取る。逃げるように扉を閉めようとした。
「待って、かーさん。……俺、来週日曜出かけてくる。部活見てくるよ」
うん、知っているよ。
そんな言葉を、飲み込んだ。
「分かった。頑張るんだぞ。……私も、頑張ってみる」
扉を静かに閉める。そして、そのまま背中と頭を預けた。
いい息子だ。わがままも言わないし、どこに出しても恥ずかしくない。……ただ。
「私のせい、ですよね。……お義父さん」
震える手で頬を押さえる。そしてもう片方の手で、ポケットの中の携帯を握った。きっと共犯者から連絡が入っているだろう。後ろめたい。それでも、やめるつもりはなかった。
「大人、だものな。……私は、魔王でいいんだ」
『だいじなもの』は捨てさせない。たとえ、どんな手段と道具を使っても。
[藍原瞳]頑張ります。今度こそ、絶対に。