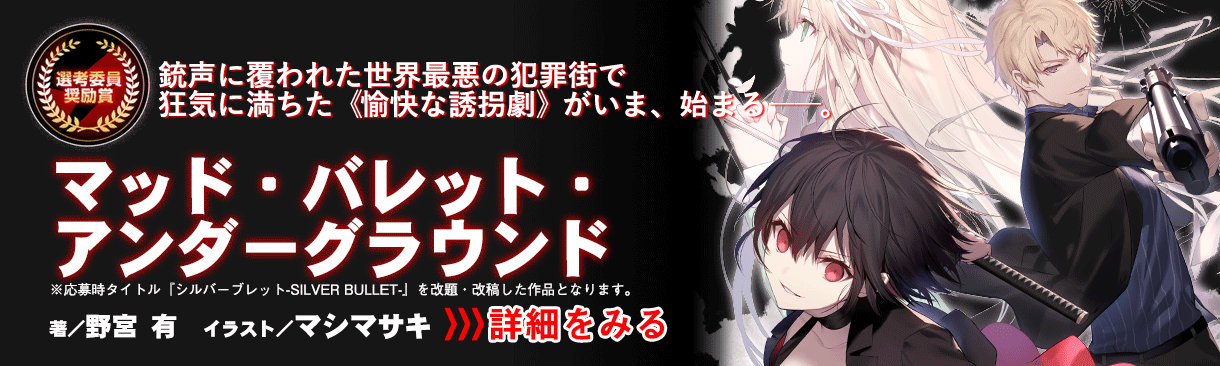※本ページ内の文章は制作中のものです。実際の商品と一部異なる場合があります。
ビルとビルの隙間から覗く細長い青空を仰ぎ、俺は溜め息を吐き出した。雲の切れ間から漏れる淡い光が路地裏に射し込み、眼前にそびえる灰色の壁の上方を切り取っていた。
壁を蹴る音と罵声で現実に引き戻される。俺の唇は意識を離れて勝手に動き始めた。
「ある商人が人喰いの蛮族どもに囲まれたとき、そいつは『私を見逃してくれたら三億エル支払おう』と言った。それからどうなったと思う?」
返答は無いようなので、そのまま続けてみることにした。
「蛮族のひとりはこう言った。『そんな紙切れ食ったら、腹を壊しちまうだろうが』ってな。結局、その商人はぶっ殺されて蛮族どもの糞に変わったってわけだ」
肩を竦めながら締めくくると、俺の前に並んでいる三人分の眼が一様に憤怒に染まった。男たちの周りの温度が一気に跳ね上がる。逃げ場の無い路地裏で、この状況は苦行に等しかった。
「その下らねえ冗談とお前が借りた五百万エルに、どんな関係性があるんだよ? なあ、ラルフ・グランウィード!」
ご丁寧にフルネームで罵倒してくれた借金取りのガスタは、唾が顔に掛かる距離まで禿げ面を近付けてきた。顔か頭か分からない部分に浮いている大袈裟な青筋に噴き出しそうになるが、全力で堪える。そんなことで借金を増やすのは得策ではない。
「つまりあれだ。お金なんて紙切れに過ぎないんだから、借金もまたあって無いようなもんだと思うわけです」
「ところが残念、ココは法治国家だぜ。もしかして俺が蛮族に見えるか? もし見えるなら、良い眼科を紹介してやる」
「わお、すげえ親切。親切ついでに、借金も帳消しにしてくれたら助かるな」
語尾にハートマークが付きそうな勢いで言うと、ガスタは黒塗りの拳銃を突きつけてきた。回転式の弾倉には六発の銃弾が入っており、撃鉄もちゃんと起こされている。銃身の向こうには、若ハゲ野郎の嫌らしい笑みが浮かんでいた。内心で唾を吐きながら、俺は両手を上げる。
「降参降参。今振り込むから待ってろ」
俺は黒いスーツのポケットから携帯を取り出す。携帯を操作して電子通貨をガスタの口座に振り込むふりをしながら、電話張から番号を検索する。左手を降参のポーズにしたままで、俺は通話ボタンを押した。
「さっさと来いよ、相棒」
俺の合図に呼応して、背にしたビルの屋上から若い女の影が降ってきた。五階建てのビルから飛び降りたイカレ女に、ガスタたち借金取りの視線が奪われる。その隙を突いて俺が禿げ頭を突き飛ばした頃には、紅い眼をした黒髪の女が、音もなく俺の真横に降り立っていた。あの高さから飛び降りたのに、女は涼しい顔をしている。
「リザてめえ、何時集合だと思ってる」
俺は呆れとともに零す。やっと事態を把握したのか、取り巻きの一人が声を荒げた。
「ななな何でだよッ! てめえっ、なな何で、どうやってあの高さから!」
今にも失神しそうなほどに錯乱する男を蹴飛ばして、リザは飛翔した。黒革のジャケットに赤いミニスカートという攻撃的な格好の相棒は、華麗な宙返りをかましてアスファルトに着地。露骨に不機嫌な表情で俺の横に並んだ。
「この状況で何を格好つけてんだよ。モテたくて必死か?」
「助けに来てやってんのに礼も言わないとかマジなんなの? あとで絶対殺す」
耳に障る悲鳴と共に、金貸しのごつい顔面が次々と俺たちから遠ざかっていく。突然の増援に興を削がれたのか、ガスタは逃げる部下の肩を掴もうともせずに得物を仕舞った。他の連中とは対照的に、大して驚く様子はない。借金取りの悪態が路地裏に溶ける。
「これだから嫌なんだ、化物相手の商売はよぉ。なあラルフ、てめえいつになったら借金返すつもりだ? てめえらなんざ明日にでもくたばっちまいそうな連中だろうが」
「熱心なストーカーどもには悪いが、俺には男色癖なんてもんは無いんでね。気色悪いから、地獄にまでは取り立てに来るなよ?」
俺が皮肉を言うと、ガスタは鼻で嗤いながら口許を歪めた。俺たちに背を向けて歩き出しながら、若ハゲ野郎は吐き捨てる。
「はっ、自分がろくでなしだって自覚はあったのか」
やけに胸に突き刺さる捨て台詞に、俺は気の利いた冗談を返すことが出来なかった。隣を見ると、リザは欠伸を噛み殺していやがる。足下に転がっていた空き缶を踏み潰して、路地裏を後にする。ゴミ袋を漁る黒い鳥の群れが、俺たちを嘲るように啼いていた。
愛車のグリムス三〇二Aに乗り込むと、俺は煙草に火を点けた。一五歳の頃から十年間は吸っているダフトフラック・スタンダードの濃厚な煙が車内を満たしていく。大して美味いわけでもない安い銘柄を好んで吸っている物好きは、周りでは俺くらいなものだ。有害物質が肺を満たしていくのを感じながら、助手席のリザに話しかける。
「一時間半の遅刻だ。倒産しかけの企業ならクビになってるだろうし、初デートの女になら余裕で振られてる。しかも、てめえがなかなか来ないせいで借金取りに出くわすという悲劇まで起きたわけだ。幸運すぎて涙が出るね」
「は? 知らねえし。てか何急に呼び出してんの」
「場所指定してきたのはてめえだろうが。わざわざイレッダ地区から出るのがどれだけ面倒臭えと思ってんだよ」
「はいはいご苦労様。で、用件は何」
「グラノフが回してきた、いつもの腐れ仕事だよ。そんくらい把握しとけ」
「まーどっちでもいいや」リザの口許が邪悪に歪む。「ちょうど暴れたかったんだよね」
三世代も前の古いエンジンが嘶き、廃車同然の車体が揺れる。ハンドルを回して車を車道に乗せながら、欠伸をしている相棒を一瞥した。
リザ・バレルバルトは黒いビニール袋を車内に投げ捨て、紅い瞳を眠そうに細めていた。長袖の黒いジャケットの袖から出た細い手首には、銀製のブレスレットが巻かれている。陶器のように白い肌からは生気を感じ取ることができない。この国ではあまり見ない黒髪は首元あたりで切り揃えられており、髪の間から覗く鋭利な紅い眼はどこまでも深い。
不安定で妖しさを孕んだ美貌。無駄にスタイルが良いことも含めて、攻撃的で近寄りがたい女というのがリザの第一印象だった。俺も目つきの悪さに金色の短髪、左耳だけに付けたピアスという風貌から「コンビニ強盗でもやらかしてそうな顔」と揶揄されたことがある。だがこいつはそれよりさらに上の、ある種の不吉さを孕んだ印象を周囲にバラ撒いている。
それにしてもだ。今のこいつの、酒場にでも出掛けるような服装はこれから向かう仕事場には相応しくはない。黒いスーツの下に防弾チョッキまで装備している俺とは正反対だ。
「これから仕事に向かうってのに、随分とラフな格好だな。死んでも葬儀代は出せねえぞ」
「蠅を殺すために武装するような特大のバカは、あんたの他には居ないと思うけど」
「一九のガキが油断してんじゃねえよ。相手はあのフィルミナードから〈銀の弾丸〉を二発も奪った連中だ。カイから貰った情報にはねえが、厄介な番犬を雇ってる可能性も覚悟しとけ」
「私はむしろそんな展開がいーけどね。てか虫を駆除するだけじゃつまんない」
呆れながら見ると、リザは見るからに新品のケースから、見るからに新品のミュージック・ディスクを取り出していた。近くの大型店の袋が転がっていることから考えると、たった今買ってきたのだろう。わざわざ市街地に呼び出してきた理由もやっと分かった。
「まさかとは思うけど、遅刻の原因はそれか? 暴徒による襲撃にあったとか、道で困ってるお年寄りを助けてたとかではなく?」
「〈ディジーズ〉の新譜の発売日が今日だったのを思い出したから、急いで買いに行ってただけ。仕事が終わるまで待ってたら、いつ聴けるかも分かんないじゃん」
「その優先順位は、一体どういう仕組みになってんだ? このクソ女、もう溺れてしまえ」
「これでも店を出て直ぐに約束を思い出したの。むしろ感謝してほしいんだけど?」
「なあリザ、責任ってやつを自覚した経験はあるか? 罪悪感って言葉くらいは知ってる?」
「あーもー黙って聴こえないから。何昼間っからテンション上がってんだよ」
殺意と紫煙が混ざった溜息を吐き出す。大音量のロックンロールが鳴り響き、俺の舌打ちを掻き消した。
波濤のように押し寄せては後ろに流れていく窓の外の景色は、都会の喧騒を表していた。色鮮やかな看板が生えた高いビルが乱立し、歩道には平日の昼間にも関わらず人が溢れている。
学生やスーツを着た勤め人が急ぎ足でどこかに向かっているすぐ側で、ボロボロの服を着こなしたホームレスが行き場もなく蹲っていた。極彩色の布切れを着て奇妙な踊りを披露している、新興宗教の信者どもと思しき一団もいた。島の外に住んでいるリザを迎えに来るたびに思うことだが、相変わらずエルレフには統一感が無く、正気と狂気が乱立しているように見える。
「いつも言ってるが、リザ、早くイレッダ地区に引っ越せよ。いくら同じエルレフ市内とはいえ、イレッダから中心街まで来れば片道二時間はかかる。往復なら四時間だ。なあ、四時間だぞ? 仕事の度に迎えに来てやってる俺の辛さも少しは考えてくれよ」
「いっつも言ってるけど、ライブ・ハウスもCDショップもないような街になんて絶対住めないから。そこらへんも考慮してくれる?」
「なら朗報だ。イレッダなら、銃声やら人の悲鳴やらが大音量で聴き放題。ずっと聴いてると、もれなく発狂してしまうのが難点だけど。……というかそもそも、俺やお前のような人間がこうして昼間の大通りを進んでること自体が、かなりイカレた状況だからな」
「役所に賄賂を贈れば悪党でも部屋を借りられるって現実の方が、イカレてると思うけど?」
「その賄賂は誰が振り込んでると思ってんだ。クソっ、一ヶ月以内に引っ越せよ。絶対だぞ」
バレシア皇国で第二の都市であるエルレフは、俺やリザのようなろくでなしどもでも受け入れてくれる寛容な街だ。まともな人間であれば、貞操観念のない街だと嘆くかもしれない。
大昔から貿易の街として栄えてきたエルレフ市にはどの段階からか、外資系の犯罪組織が大量に流入し始めたのだ。その中には〈銀の弾丸〉を多数保有する大組織も含まれており、この街における幻想と現実の境界線は消去されて久しい。
悪夢のような幻想は人々の心を捻じ曲げ、倫理観や価値観を崩壊させていった。もともと糞塗れな黒社会に至っては、抵抗することもなく幻想に溺れてしまった。それが生んだのが、増殖する墓標と、俺たちのようなハイエナどもだ。
一度警察の記録を盗み見たことがある。その電子資料によると、〈銀の弾丸〉が登場したここ三十年の間に、バレシア皇国における殺人事件の被害者数が年間七万人弱という途方もない段階に到達していた。つまり、かつての紛争地域に匹敵する量の殺人が、他国と戦争状態にあるわけでもない平和な先進国で行われているのだ。明らかに尋常な数字ではない。
車は、黄昏に染まる海の上を走っていた。
今渡っているのは噂好きの連中が〈墜落への道〉と格好つけて呼ぶ全長二二五六メートルの大橋だが、正式名称はとっくに忘れた。そして橋の終点にあるのは、悪名高き地獄の番外地、エルレフ市イレッダ特別自治区――通称〈成れの果ての街〉である。海の上を無法地帯に向かって一直線に進む古い車は、確かにどこかへと墜落しているようにも見えた。
「入るのは簡単だが外に出るのは難しい街、ね」
反対車線に発生している大渋滞を眺めながら、思わず呟いていた。
イレッダ地区に入る際はデータ通信による簡単な入島手続のみで済むが、エルレフ市街の方に行くのは容易ではない。身体検査、所持品の確認、経歴の調査など、過剰に過剰を重ねたような検閲が橋の入り口で執り行われているためだ。俺のように警察に協力者がいる場合を除けば、犯罪者が正規のルートで島を出るのはほぼ不可能である。
人工島に上陸してからも、しばらく車を走らせる。橋の向こうのエルレフ港が遠くに見える海に近い土地に、古臭いネオン灯の看板を掲げた合法非合法様々な店が並んでいた。
クズども御用達の観光名所としても有名なネブル通りには、数々の娼館や賭博場、安価な武器を扱う玩具屋に、人工の幸福を人々に配る麻薬専門店と、法律に喧嘩を売っているとしか思えない店が、偽装しているとはいえ大通りに存在している。そこでは秩序や倫理は淘汰され、欲望と混沌が我が物顔で闊歩していた。全くもって、気が滅入る光景だ。
「人工島に初めて来たときは、この通りも映画のセットか何かにしか見えなかったよ。ここを爆撃で滅ぼそうと訴えてる過激派連中に、あの時ほど賛同した瞬間はないね」
俺の舌打ち混じりの感想に、リザが冷たく笑って同意する。
「まあ、確かに。こんな街を抱えてて、バレシア皇国もよく法治国家を名乗れてると思うわ」
「イレッダ地区で生まれ育った奴も何人かいるそうだ。その一人が島の外で人を殺して捕まった時、そいつは終始警察に対して不満を述べていた。俺が親から習った法律じゃあ殺人は三人までならセーフだった、二人殺したくらいで逮捕される理由が全く分からないってな」
「はっ、ぜんぜんジョークに聞こえないのが笑える」
そもそもイレッダ地区とは、リゾート地だか工業地帯だかを作る目的で埋め立てられた人工島だ。政府主導の一大事業だったが、開発中に起きた大事故や、計画を主導していた政治家どもの不正が発覚し、プロジェクトは頓挫。当時のエルレフ市長が暗殺されたのをきっかけに、イレッダ地区は大小さまざまな建築物や道路だけを残して無人島と化した――というのが、教科書にまで乗っている史実である。それから何がとち狂って今のような有様になったのかは謎だ。俺がガキの頃にはすでに、紛争地域を除けば世界一危険な場所であると言われていた。こんな犯罪集団そのもののような通りに、警察がほとんど介入できていないのが好例である。
「着いたぜ」