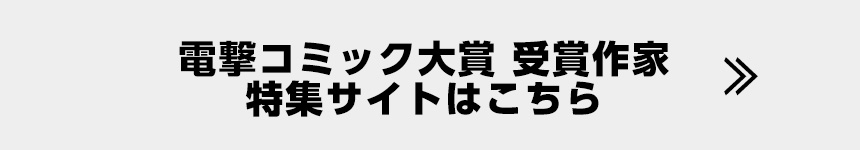オリンポスの郵便ポスト
★二日目
翌朝。日の出前に私たちは出発した。
気温三度。吐く息が白くなる。防寒着を着込み、私はスクーターに跨る。これで日中はまた三十度近くまで上がるのだから嫌になる。夜間のうちに溜まった真っ赤な砂埃を排気筒が一気に吐き出し、分厚い四輪タイヤを駆動させてスクーターが走る。
相変わらず、クロは口数が少なかった。それでも、昨日までとは違って重苦しい空気ではなかった。サイドカーでクロは膝の上に紙を広げて、一生懸命、何か下書きをしているようだった。邪魔したら悪いと思い、声を掛けなかった。推敲する時間なんて山ほどある。胸のうちに溜まった想いは二百年分もたまっているのだ。もしも、クロが郵便ポストの入り口に入らないほど、分厚い手紙を書いてしまったらどうしようとか、私は余計な心配をしていた。
日が昇り、赤土の荒野を照らす。気温も急激に上がり、私は防寒着を脱ぎ捨てる。
頃合いを見計らい、私はスクーターを停め、地図を広げる。もらった方位磁石と、ペンとを手に、地図の上にルートを書き込む。旅は思った以上に順調だった。これならば、あと数日のうちにこの高原地帯を抜けることができそうだ。
「おや、これは……」
クロが何かに気付いたように、スクーターの運転席を指差した。彼が興味を示したのはコンソールに搭載した古めかしいカセットデッキだった。地球でも古い時代に用いられていた磁気テープを使ったアナログの記録メディアだ。大気中にマイクロレベルの微小なダストが舞うこの星では、光学ドライブを用いたデジタルメディアよりも耐久性の面で重宝されている。とは言っても、今のこの星の技術レベルではその両方とも、故障したドライブの修理はできても、改めて新品を製造することはできないのだが。
「え……これですか。元々は地図データの読み出しに使っていたものらしいですが、もうほとんど使っていませんよ」
「今でも動きますか」
「ええ……定期メンテナンスは受けているので、たぶん……」
「それならば、申し訳ありませんが、これをかけてみてはくれませんか」
何故か、クロの声が嬉しそうに弾んでいた。彼が小さな荷物の中から取り出したのは、さらに古めかしいカセットのテープだった。表面は汚らしく黄ばみ、ラベルの文字も消えてもう読めない。私は言われるまま、デッキにカセットを挿入し、再生用のスイッチを押した。
しばらくの沈黙の後。ノイズの向こうから聞こえてきたのはピアノの鍵盤を叩く音と引き込まれるように美しい歌声。せせらぎにも似た緩やかな音程の中に時折、垣間見せる真の強さを感じさせる強い女の人の声だ。劣化し、擦れきった音色はしかし、私の胸に深く突き刺さった。
真っ青な泉のように透きとおった音色は荒涼とした赤い大地とは対照的だった。
「古い地球の歌です。火星に持ってくることができた私物なんて、ほとんどこれくらいです」
「綺麗な歌声……思わず聞き惚れてしまいそう」
「双子の兄妹のユニットです。妹の方は若くして亡くなれましたが。ああ、でも良かった。再生できるデッキが故障して、ずっと聴けませんでしたから。あ、迷惑でしたでしょうか」
私は首を振って答えた。
「迷惑だなんて。何だか音楽を聞くと、元気が出てくる感じがします。ほら、郵便配達の仕事なんて孤独との戦いみたいなものだから。ずっと、一人で、何もない大地を駆けるだけだから。時々、すごく寂しくなって、嫌になるんです」
「そうですよね。私も、旅の間は何度もこの曲に励まされましたから分かりますよ」
「クロさんは元々、エアリーの人ではなかったのですか」
「以前はエリシウムにいました。エアリーまではキャラバン隊に同伴して来ました」
「エリシウム……大きな街ですよね。私も以前、住んでいたことがありましたよ。とは言っても、ずっと病院に入っていただけなんですけど」
「何か大きな病気でも?」
「小さいころに大きな怪我をしまして……リハビリも兼ねて。でも、今は大丈夫ですよ。それからは、郵便配達の仕事をすることになって、エアリーの郵便局に配属されました」
「お若いのに立派です。では、ご家族とは」
「ええ、ちょっと……今は事情があって両親とは別々に暮らしていて……」
「それは寂しいですね」
嘘は言っていない。ちっぽけな罪悪感から私は目を逸らした。
「そうですね……もう何年も会っていませんから。夜寝る前に少し思い出したりしますね」
「ああ、それなら、エリスさんもご両親に手紙を書かれてはいかがでしょう」
クロの提案に、私ははっと気づかされる。
「手紙か……そうですね。この旅が終わったら、書いてみることにします。ああ、でも、何を書けばいいんだろう。ずっと会っていないから何を書けばいいか。頭に浮かばないです」
「そうです、そうなんです! 私も先ほどからずっと考え込んでいるのですが、ちっとも言葉が浮かんでこないのです。伝えたいことは山ほどあるのですが、いざ、ペンをとってみると、考えが纏まらなくて。手紙って書くの、難しいですよね」
クロの膝の上に広げられたノートには、時節の挨拶から何度も何度も書き直したような跡が残っていた。確かに私も、もう何年も人が書いた手紙を届ける仕事をしているが、自分が手紙を書くようなことは数えるほどしかない。
「それならこの旅で、お互い一緒に考えませんか。手紙に何を書くのかを」
そう言いながら、クロは少し嬉しそうだった。その間もスピーカーからは音の割れたメロディーが絶え間なく流されていた。ずっと会えない恋人に宛てたラブソングだった。運命が二人を分かつ。いつか再び会えることを信じて――。歌の中の彼女が恋人に宛てて手紙をしたためるシーンを私は勝手に想像した。そんなこと、歌詞には一つもないのに。
大丈夫だよ。きっと会えるよ、きっと。だから信じて前を向こうよ。私はカセットテープの歌姫に心の声でエールを送った。
――それはこの世界で独りぼっちになった私自身に対する励ましの言葉でもあった。
再び、私はスクーターを停める。目の前には大地を穿つ巨大なクレーターが口を開いて待っていた。私は三度、地図を見返したが、該当するような地形は記されていなかった。と、なれば、地図の測量後にこの場所に隕石が落ちたということになる。規模からすれば、落ちたのは一メートルにも満たない、小石みたいなものだろう。私はスクーターの座席の上に土足で立ち上がって、双眼鏡を手に覗き込んだ。思った通り、地図に記されない大小のクレーターがおもちゃ箱をひっくり返したように、あちこちに散らばって広がっていた。
「八十年前の隕石雨(メテオストーム)の跡ですね」と隣でクロが言った。
「改めて見ると、やっぱりすごいですね」
似たような大災厄の痕跡はこの星のあちこちで見られる。古い地図と比較すると、山一つが消え、地形そのものが変わってしまっていることも少なくはない。
「八十年前。一晩に数百から数千の隕石がこの地に降り注ぎました。いわゆる《彗星の夜(コメットナイト)》です。多くの開拓集落が壊滅し、大気中に巻き上げられた粉塵が全土を覆いました。まるで、この星全体が巨大な砂塵嵐(ダストストーム)に襲われたように、太陽の光は夜も昼もなく遮られ、急激な気温の低下を招きました。当然、各地の植物用プラントは壊滅し食料不足に陥り、政情も混乱しました。結果としてこの星の全土を巻き込む内戦に発展するまで時間はかかりませんでした」
私は何も言わず、クレーター原を迂回するルートを取った。
この星の文明の時計は数百年のレベルで逆戻りした。その端緒とも言える《彗星の夜(コメットナイト)》。しかし、なぜ一夜で数千の隕石が一度に降ってきたのか、その災厄の原因は今なお、はっきりしない。その後の混乱で原因調査どころではなくなったというのが実情だ。ただ、昔からこの災厄が人為的に引き起こされたものではないか、というのが巷での共通理解だ。
その推論は、軌道から外れた小惑星群が流れ星となって、この星に降り落ちたというものだ。では、何故、百単位に及ぶ小惑星が軌道を外れたのか。火星が回る外側、木星との間の軌道を周回する小惑星帯は、かつて一つの岩石惑星になり損ねた無数の星の欠片の集まりだ。当時、レアメタルやヘリウム3などの資源獲得を名目に地球側が開発を進めていた事実もある。当時の技術ならそのうちの一部の軌道を人為的に修正することも、決して不可能なことではない。
何かの事故か、はたまた明確な悪意を持った攻撃か。問いただそうにも、地球と唯一、交信できていた通信施設も、隕石の下敷きになってしまった。あれからもうじき一世紀、地球側からの接触は未だない。この星は見捨てられたのだと、今ではみんなが信じるようになった。
もう、今更、知るすべもない真実なんてどうでもいい。あの日見た悪夢を思い起こさせるような場所になんかにずっといたくはなかった。だから私は逃げるように、ただ無心にひたすらスクーターを走らせた。そうやって日が沈み、また昇る。それが幾度も繰り返され、旅は続く。